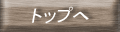供 出
旅のあれこれ

供 出
| 青森市の雪中行軍遭難銅像、東京都千代田区の楠木正成像、大村益次郎像。港区の有栖川宮熾仁親王の銅像 |
|
昭和16年(1941年)8月、札幌市の中島公園に「木下成太郎先生」の像設置。金属回収令で供出されることがなかった。 大正14年(1925年)、旧養育院長渋沢栄一銅像を建立。昭和18年(1943年)金属供出のためにコンクリート製の代替像が作られが、供出されないままに終戦を迎えた。 明治40年(1907年)4月4日、東京帝国大学にベルツ先生、スクリバ先生のブロンズ像を建立。戦時中軍需資材として供出されることになり、大学ではセメントでコピーを作ったが、供出前に戦争が終わりブロンズの像は残った。 昭和13年(1938年)、大日本帝国憲法発布50年を記念して国会議事堂内に板垣退助、大隈重信、伊藤博文の銅像を設置。 明治13年(1880年)、金沢の兼六園に日本武尊像を建立。戦時中の金属供出を免れる。 誕生寺の守護大仏は江戸期鋳金仏中の最優秀作として戦時金属供出にも却って保存方を命ぜられたほどであった。 昭和13年(1938年)5月、小倉の到津遊園地内に桃太郎像が建設された。戦時中、同園長の阿南哲朗氏がこの像を守り。金属回収を免れた。 |
|
昭和10年(1935年)2月16日、誕生寺に日蓮聖人御幼像を発願。戦時供出されたが、ほとんど無傷で発見され誕生寺へ還り、昭和21年(1946年)8月27日元のように安置された。 昭和13年(1938年)11月13日、高島公園の諏訪護国神社に永田鉄山中将像を建立。戦時下の金属類回収令で供出され代わりにコンクリート像が置かれたが、戦後招魂社の土蔵から梱包状態で発見され、昭和40年(1965年)4月11日に元の位置へ復元された。 |
|
昭和13年(1938年)11月12日、旭川市の常磐公園に岩村通俊の像除幕。昭和18年(1943年)7月10日、金属供出。昭和26年(1951年)10月5日、コンクリート製で除幕式。平成3年(1991年)、ブロンズで制作。 大正15年(1926年)5月14日、北海道大学にクラーク像建立。昭和18年(1943年)6月、金属回収令により供出。昭和23年(1948年)10月、再建立。 明治44年(1911年)、奥州市の水沢公園に後藤新平の銅像が大熊氏広の作によりに建立されたが太平洋戦争の際応召、昭和46年(1971年)4月22日、旧台座の上に日本ボーイスカウト初代総長の姿の銅像を建立。 昭和13年(1938年)、奥州市の水沢公園に斎藤實の銅像が建設されたが、昭和19年(1944年)に応召。昭和38年(1963年)10月、復元。 昭和5年(1930年)5月、秋田市の秋田鉱山専門学校に小花冬吉先生の胸像建立。戦時中に供出され、昭和25年(1950年)10月、再建。 昭和10年(1935年)、仙台市の青葉城に伊達政宗卿騎馬像建立。小室達(とおる)制作。昭和19年(1944年)1月、金属徴用で姿を消した。昭和39年(1964年)10月9日、復元除幕。 大正15年(1926年)8月28日、喜多方市の示現寺で瓜生岩子の銅像除幕式挙行。戦争で供出され、昭和30年(1955年)、再建。 明治34年(1901年)、山形市の豊烈神社に水野三郎右衛門元宣像銅像を建立。昭和18年(1943年)、供出。昭和21年(1946年)、現在の塑像を再建。 昭和4年(1929年)、郡山市の開成山大神宮に阿部茂平衛銅像建立。昭和18年(1943年)供出。昭和28年(1953年)11月、再建された。 大正8年(1919年)9月、浅草寺境内に市川團十郎の銅像を建立。昭和19年(1944年)11月30日、金属類回収のため供出。昭和61年(1986年)11月3日、再建。 昭和8年(1933年)、常盤橋公園に青淵澁澤榮一の像を建立。金属供出のために撤去。昭和30年(1955年)11月、再建。 大正15年(1926年)、渋澤榮一翁の寿像は如水会館修復の時に再制作されたが、戦時中に供出。昭和26年(1951年)11月14日、復原。 大正3年(1914年)、東京駅丸の内側に井上勝君像建立。本山白雲作。金属供出に伴い撤去。昭和34年(1959年)、朝倉文夫作により再建。 渡辺長男氏の旧太田道灌像は旧東京市庁舎から撤去、供出された。昭和33年(1958年)、都庁舎に太田道灌像設置。製作者は朝倉文夫氏。 昭和9年(1934年)4月21日、渋谷駅正面に忠犬ハチ公像設置。昭和19年(1944年)10月、金属供出として撤去。昭和23年(1948年)8月14日、再建。 昭和15年(1940年)、高橋是清翁記念公園に高橋是清翁像設置。戦時中の金属供出のため撤去。昭和30年(1955年)、再建。 明治42年(1909年)、横浜市の掃部山公園に井伊直弼像建立。藤田文蔵制作。昭和18年(1943年)、金属回収によって撤去。昭和29年(1954年)、再建。 明治41年(1908年)10月、善光寺の護摩堂(現在の経蔵)前に如是姫像建立。昭和19年(1944年)2月、台座を残して供出。昭和23年(1948年)10月、現在の如是姫像が再建された。 昭和12年(1923年)11月、忠犬タマ公建立。太平洋戦争中に供出。昭和34年(1959年)4月10日、再建。 大正8年(1919年)、岐阜公園に板垣退助像除幕。昭和18年(1943年)、金属供出のため撤去。昭和25年(1950年)、新像除幕。 大正13年(1924年)、第四高等中学校に「溝淵先生」の像設置。戦時中供出されたが、昭和34年(1959年)、再建。 大正14年(1925年)12月24日、足羽公園に橋本左内銅像建設。昭和19年(1944年)、銅の回収のため撤去された。昭和38年(1963年)10月7日、左内公園に橋本左内銅像建立。 明治43年(1910年)、彦根市の尾末公園に井伊直弼の像竣工。昭和19年(1944年)、金属供出により回収。昭和24年(1949年)11月、再建。 明治26年(1893年)10月、京都の常盤ホテルに前田又吉銅像建立。第二次世界大戦時に供出された。令和元年(2018年)6月2日、再建。 昭和3年(1928年)11月8日、「高山彦九郎皇居望拝之像」建設。渡辺長男作。金属供出のため撤去された。昭和36年(1961年)、再建。伊藤五百亀作。 昭和10年(1935年)5月11日、知恩院三門南に「風災学童慰霊塔」竣工除幕式挙行。昭和19年(1944年)、軍需資材として供出され、撤去された。昭和35年(1950年)、「師弟愛之像」再建。 大正11年(1922年)、福山城に阿部正弘之像を建立。武石弘三郎制作。第二次世界大戦時に供出。昭和53年(1978年)4月、阿部正弘之像を再建。陶山定人制作。 昭和10年(1935年)、広島市の比治山公園に加藤友三郎像建立。昭和18年(1933年)、金属供出により銅像は撤去された。平成20年(2008年)8月、中央公園に銅像再建。 大正元年(1912年)12月25日、山口市の高田公園に井上馨銅像除幕式。戦時中に供出。昭和31年(1956年)、再建。 明治33年(1900年)4月、山口市の亀山山頂に毛利敬親像・吉川経幹像・毛利元蕃像・毛利元純像・毛利元周像の除幕式。明治39年(1906年)10月、毛利元徳像の除幕式が執り行われた。昭和19年(1944年)、これらの銅像は供出される。昭和55年(1980年)、毛利敬親公の銅像が再建された。 昭和8年(1933年)、下関市の東行庵に山県有朋公像建立。金属供出で影を消したが、平成27年(2015年)春、新しく青年志士山県狂介像として復元。 昭和11年(1936年)4月、下関市の日和山に高杉晋作の銅像が建てられた。昭和18年(1943年)、金属供出のために接収。昭和31年(1956年)、高杉晋作没後90年を記念して陶製の像を再建。 昭和6年(1931年)、松山市の道後公園内に秋山真之像建立。昭和18年(1943年)、金属供出で撤去。昭和38年(1963年)、石手寺境内に再建。昭和43年(1968年)、梅津寺に移転。 昭和11年(1936年)、松山市の道後公園に秋山好古の騎馬像建立。昭和18年(1943年)、金属供出で撤去。昭和45年(1970年)1月、梅津寺に立像として再建。平成17年(2005年)、「秋山兄弟生誕地」に騎馬像復刻。 大正2年(1913年)、高知城に本山白雲の山内一豊公之像を建設。平成8年(1996年)9月20日、銅像の原型をもとにして再建除幕された。 大正12年(1923年)12月5日、初代板垣退助先生像除幕。昭和18年(1943年)9月2日、壮行式が行われ、供出。昭和31年(1956年)5月11日、再建除幕。 大正4年(1915年)、福岡市の西公園に平野二郎國臣像建立。昭和18年(1943年)、戦時供出。昭和39年(1964年)、平野國臣百年祭で再建。 大正9年(1920年)、福岡市の金龍寺に貝原益軒先生銅像建設。太平洋戦争の為、供出。昭和40年(1965年)10月、再建。 大正2年(1913年)、鍋島直正公像建立。武石弘三郎作。昭和19年(1944年)、戦時下の金属供出で撤去された。平成29年(2017年)3月4日、鍋島直正公像除幕。 明治36年(1903年)、大村市の玖島城に大村純熈公像創建。昭和56年(1981年)5月、復元。 昭和12年(1937年)3月21日、大分市の神宮寺浦に大友宗麟像建立。金属回収の為、台座を留めるのみ。昭和33年(1958年)4月、再建。 昭和12年(1937年)、西南戦争60年を記念して谷干城の像建設。第二次世界大戦中に金属提供され、昭和44年(1969年)に明治100年を記念して再建された。 昭和10年(1935年)4月、加藤清正銅像製作。昭和19年(1944年)4月、金属供出で撤去。昭和35年(1960年)4月、再建。 |
|
大正12年(1923年)5月、三宅坂に寺内元帥騎馬像設置。昭和18年(1943年)、銅像供出で撤去される。昭和25年(1950年)、台座に広告記念像建設。 成田山公園の七代目団十郎と六世団蔵の銅像は戦時中供出された。昭和18年に八代目団蔵は七代目団蔵の追善供養の為、台座の上に虚子の句碑を建てた。 明治44年(1911年)10月、大倉喜八郎は伊藤博文の銅像を建設、第二次世界大戦中に金属供出され、現在では大倉山公園に銅像の台座だけが残る。 広島市の千田小学校にあった二宮尊徳先生幼時之像は戦時中に供出されたままになっていた。昭和60年(1985年)4月27日、台座に「平和の女神」の像を設置。 |
|
大正2年(1913年)4月19日、芝公園に板垣退助像建立。本山白雲制作。昭和20年(1945年)3月10日、東京大空襲の中で金属供出され、再建されなかった。 明治37年(1904年)7月15日、本山白雲の後藤象二郎銅像が東京芝公園に建立される。金属供出により撤去。再建されなかった。 |
| 浅草寺の時の鐘は東京大空襲で火を浴びたが無事に残り、今なお昔のままの姿を見せている。 |
|
所沢市山口観音の鐘は大戦末期に供出されたが、昭和49年(1940年)に鋳造された。 昭和18年(1943年)、明石市月照寺の梵鐘は戦時供出。昭和53年(1978年)、再鋳された。 高松市法然寺の梵鐘は金属供出に提供されたため、昭和24年(1949年)、改めて鋳造された。 |
|
行田市大長寺の大仏は戦争で供出。平成8年(1996年)に復元したそうだ。 兜町の日証館は金属回収のため暖房設備やエレベーターなどが取りはずされ、供出された。 明治38年(1905年)頃、日比谷公園に鶴の噴水を製作。戦時中の金属回収で台座が石造りとなった。 大正11年(1922年)10月13日、宇治市の万福寺に田上菊舎の句碑を建立。句碑の銅板は第二次大戦中に供出。平成17年(2005年)8月、復元。 大正15年(1926年)、広島市の猿猴橋架設。装飾品は金属回収令により供出され、代替えである花崗岩が使用された。平成28年(2016年)、架け替え当時の姿へ復元。 昭和9年(1934年)、関門ふく交友会は「波のりふくの像」を建立。昭和19年(1944年)、金属供出により取り払われた。平成2年(1990年)9月29日、世界最大のふく像除幕。 |
|
道すがら虎の門より櫻田へかけて立連りし官衙の門墻を見るに、今まで鐵の鑄物なりしを悉く木製に取りかへたり。日比谷公園の垣は竹になしたり。此れ米國より鐵の輸出を斷られたる爲なるべく貧國物資の欠乏察するに餘りあり。過日荒物屋に物買ひに行きしに魚串金網はりがねの類久しき前より既に製造禁止となれる事を知りぬ。役人軍人輩の銅像をも取拂ひ隅田川の橋梁を昔の如く木製になさば物資の缺乏を補ひ、且又市街の醜觀を減ずべく一擧兩得の策たるを得べし。
『斷腸亭日乘』(昭和16年8月19日) |
|
市内の堀割にかゝりし橋の欄干にて鐵製のものは悉く取去られてその跡に繩をひきたり。大川筋の橋はいかゞするにや。夜中はいよいよ歩かれぬ都となれり。
『斷腸亭日乘』(昭和18年12月28日) |