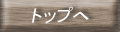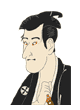
青葉城址〜伊達政宗卿騎馬像〜

|
東日本大震災で仙台城跡の石垣が崩れたため、仙台シティループバス「るーぷる仙台」は東北大学工学部経由の迂回コースを通って、青葉城本丸会館駐車場へ。 |

|
仙台藩祖伊達政宗卿騎馬の銅像が森の都仙台の青葉山につくられたのは昭和10年のことである。ときの宮城県青年団が郷土の彫刻家小室達(とおる)氏に託して制作した。19年1月太平洋戦争による金属徴用でその姿を消したが、28年10月新たに卿の平服姿をかたどった白色セメント立像を小野田セメント株式会社が制作して市に贈った。 たまたま騎馬像の原型が柴田町に保存されていることがわかり、銅像再建を望む声が高まったので、37年10月本協会法人改組の記念事業として復元を企てたところ、幸いに宮城県・仙台市・柴田町の支援と県内外の熱心な協賛を得て事業もはかどり、ここに卿の雄姿を復興することができた。 経済の開発と文化の発展につくした英雄の風格は郷土繁栄の象徴として、その遺徳とともに永遠にたたえられるであろう。 昭和39年10月1日
社団法人 仙台市観光協会 |
|
昭和28年(1953年)6月18日、小室達は53歳で逝去。 昭和28年(1953年)10月、白いセメント製の「伊達政宗立像」設置。柳原義達制作。 |

|
晩翠は本名を林吉といい明治4年(1871年)仙台市北鍛冶町の質商土井七郎兵衛の長男として生まれた。 明治11年、培根小学校(今の木町小学校)に入り、のち立町小学校に転校、仙台英語学校、旧制第二高等学校を経て、明治30年東京帝国大学英文科を卒業、明治33年母校二高の教授として帰仙した。 その間、31年に不朽の名作「荒城の月」を詩作発表、続いて第一詩集『天地有情』を処女出版した。島崎藤村の『若葉集』におくれること2年の明治32年、晩翠の28才から29才にかけての頃であった。 のち6つの詩集や数多くの随筆など出版した。 昭和22年日本芸術院会員、24年仙台市名誉市民に推され、翌25年、文化勲章を受章され、昭和27年10月19日、仙台市本荒町の晩翠草堂で情熱の詩人としての81年の生涯を閉じられた。 この碑は昭和27年、晩翠会等によって建てられたものです。 |

| 春高楼の花の宴 めぐる盃影さして |
|
| 千代の松が枝わけいでし むかしの光いまいづこ |
|
| 秋陣営の霜の色 鳴きゆく雁の数見せて |
|
| 植うるつるぎに照りそひし 昔のひかりいまいづこ |
|
| 今荒城の夜半の月 変わらぬ光たがためぞ |
|
| 垣に残るはただかづら 松に歌ふは唯あらし |
|
| 天上影は変わらねど 栄枯は移る世の姿 |
|
| 写さんとてか今もなほ ああ荒城の夜半の月 |
|
「荒城の月」は鶴ヶ城と青葉城をモチーフに作詞されたということで、「若松城」にも「荒城の月碑」がある。 昭忠碑は平成23年3月11日の東日本大震災において再び被災、頭部金鵄が落下するなど大きな損傷を受けた。 |