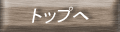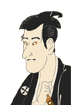
|
飛鳥の岡本の宮に天の下知らしめす天皇の元年己丑の、九年丁酉の十二月己巳の朔の壬午に、天皇・大后、伊予の湯の宮に幸す |
|
熟田津に船乗りせむと月待てば潮もかなひぬ今は漕ぎ出でな |
|
天皇蒲生野に遊猟せられた時、額田女王の作られた歌 あかねさす紫野行き標野行き野守は見ずや君が袖振る |
|
皇太子答御歌 紫のにほへる妹を憎くあらば人妻故に我れ恋ひめやも |
|
麻續王の伊勢国伊良虞の島に流(はなた)へたまひし時、時(よ)の人の哀傷(かなし)みよめる歌 |
|
打麻(うつそ)を麻續の王海人なれや伊良虞が島の玉藻苅ります 麻續王のこの歌を聞かして感傷(かなし)み和へたまへる歌 うつせみの命を惜しみ波に湿(ひ)で伊良虞の島の玉藻苅り食(は)む 天皇幸于吉野宮時御製歌 淑き人のよしとよく見てよしと言ひし吉野よく見よ良き人よく見 藤原宮御宇天皇代天皇御製歌 春過ぎて夏来るらし白栲の衣干したり天の香具山 楽浪の志賀の辛崎幸くあれど大宮人の舟待ちかねつ 楽浪の志賀の大わだ淀むとも昔の人にまたも逢はめやも 高市連黒人が近江の堵(みやこ)の旧(あ)れたるを感傷しみよめる歌 古の人に我あれや楽浪の古き都を見れば悲しき 楽浪の国つ御神のうらさびて荒れたる都見れば悲しも |
|
君が行き日長くなりぬ山尋ね迎へか行かむ待ちにか待たむ 君が行き日長くなりぬ山たづの迎へを行かむ待つには待たじ 内大臣藤原卿娶釆女安見<兒>時作歌一首 我れはもや安見児得たり皆人の得かてにすとふ安見児得たり 天皇大殯之時歌二首 かからむとかねて知りせば大御船泊てし泊りに標結はましを やすみしし我ご大君の大御船待ちか恋ふらむ志賀の唐崎 有間皇子自傷結松枝歌二首 磐白の浜松が枝を引き結びま幸くあらばまた帰り見む 家にあれば笥に盛る飯を草枕旅にしあれば椎の葉に盛る 長忌寸意吉麻呂見結松哀咽歌二首 磐代の岸の松が枝結びけむ人は帰りてまた見けむかも 磐代の野中に立てる結び松心も解けずいにしへ思ほゆ 大寶元年辛丑幸于紀伊國時<見>結松歌一首 後見むと君が結べる磐代の小松がうれをまたも見むかも 天離る鄙の荒野に君を置きて思ひつつあれば生けるともなし |
|
近江道の鳥篭の山なる不知哉川日のころごろは恋ひつつもあらむ 安倍女郎歌二首 いまさらに何をか思はむうち靡き心は君に寄りにしものを 我が背子は物な思ひそ事しあらば火にも水にも我れなけなくに 額田王思近江天皇作歌一首 君待つと我が恋ひ居れば我が宿の簾動かし秋の風吹く 来むと言ふも来ぬ時あるを来じと言ふを来むとは待たじ来じと言ふものを 大伴坂上郎女歌二首 黒髪に白髪交り老ゆるまでかかる恋にはいまだ逢はなくに 山菅の実ならぬことを我れに寄せ言はれし君は誰れとか寝らむ 大納言大伴卿和歌二首 ここにありて筑紫やいづち白雲のたなびく山の方にしあるらし 草香江の入江にあさる葦鶴のあなたづたづし友なしにして 大伴宿祢家持初月歌一首 千鳥鳴く佐保の川門の清き瀬を馬うち渡しいつか通はむ 言とはぬ木すらあじさゐ諸弟(もろと)らが練りのむらとにあざむかえけり |
|
み吉野の象山の際の木末にはここだも騒く鳥の声かも ぬばたまの夜の更けゆけば久木生ふる清き川原に千鳥しば鳴く 明石潟潮干の道を明日よりは下笑ましけむ家近づけば 風吹けば波か立たむとさもらひに都太の細江に浦隠り居り 帥大伴卿宿次田温泉聞鶴喧作歌一首 湯の原に鳴く葦鶴は我がごとく妹に恋ふれや時わかず鳴 冬十一月大伴坂上郎女發帥家上道超筑前國宗形郡名兒山之時作歌一首 大汝(おほなむぢ)少彦名の神こそは名付けそめけめ 名のみを名兒山と負ひて吾が恋の千重の一重も慰めなくに 同坂上郎女初月歌一首 月立ちてたゞ三日月の眉根掻き日長く戀ひし君に逢へるかも 大伴宿祢家持初月歌一首 ふりさけて三日月見れば一目見し人の眉引き思ほゆるかも 帥大伴卿和歌一首 やすみしし我が大君の食す国は大和もここも同じとぞ思ふ 市原王悲獨子歌一首 言問はぬ木すら妹と兄とありといふをただ独り子にあるが苦しさ 世間を常なきものと今ぞ知る奈良の都のうつろふ見れば 岩綱のまた変若(を)ちかへりあをによし奈良の都をまたも見むかも |
|
佐保川の清き川原に鳴く千鳥かはづと二つ忘れかねつも 娘子らが放(はなり)の髪を由布の山雲な棚引き家のあたり見む ちはやぶる鐘の岬を過ぎぬとも吾(あ)をば忘れじ志加の皇神(すめかみ) 覊旅作 ちはやぶる鐘の岬を過ぎぬとも我れは忘れじ志賀の皇神 橘の島にし居れば川遠み曝さず縫ひし吾(あ)が下衣 年魚市潟(あゆちがた)潮干にけらし知多の浦に朝漕ぐ舟も沖に寄る見ゆ 譬喩歌(弓に寄す) 陸奥の安達太良真弓弦(つら)はけて引かばか人の吾(わ)を言(こと)なさむ 三国山木末に住まふむささびの鳥待つごとく我れ待ち痩せむ 南淵の細川山に立つ檀弓束巻くまで人に知らえじ たらちねの母がそのなる桑すらに願へば衣に着るといふものを 豊国の企救の浜辺の真砂土真直にしあらば何か嘆かむ |
|
志貴皇子の懽(よろこ)びの御歌一首 石激(いはばし)る垂水の上のさ蕨の萌え出る春になりにけるかも 湯原王鳴鹿歌一首 秋萩の散りの乱ひに呼びたてて鳴くなる鹿の声の遥けさ 藤皇后奉天皇御歌一首 我が背子とふたり見ませばいくばくかこの降る雪の嬉しくあらまし 大伴坂上郎女柳歌二首 うち上る佐保の川原の青柳は今は春へとなりにけるかも 山上臣憶良詠秋野花歌二首 秋の野に咲きたる花を指折りかき数ふれば七種の花 萩の花尾花葛花なでしこの花をみなへしまた藤袴朝顔の花 大宰帥大伴卿(おおとものまえつぎみ)の冬の日に雪を見て京師を憶ふ歌 沫雪のほどろほどろに降りしけば平城(なら)の京師(みやこ)し思ほゆるかも 藤皇后奉天皇御歌一首 我が背子とふたり見ませばいくばくかこの降る雪の嬉しくあらまし |
|
大寳元年辛丑冬十月太上天皇大行天皇幸紀伊國時歌十三首 藤白の御坂を越ゆと白栲の我が衣手は濡れにけるかも 検税使大伴卿登筑波山時歌一首 今日の日にいかにかしかむ筑波嶺に昔の人の来けむその日も 豊国の香春は我家紐児にいつがり居れば香春は我家 勝鹿の真間の井見れば立ち平し水汲ましけむ手児名し思ほゆ 藤井連遷任上京時娘子贈歌一首 明日よりは我れは恋ひむな名欲山岩踏み平(なら)し君が越え去なば 藤井連和歌一首 命をしま幸くもがも名欲山岩踏み平(なら)しまたまたも来む |
|
ひさかたの天の香具山この夕霞たなびく春立つらしも 春霞流るるなへに青柳の枝くひ持ちて鴬鳴くも 春は萌え夏は緑に紅のまだらに見ゆる秋の山かも 萩の花咲きたる野辺にひぐらしの鳴くなるなへに秋の風吹く 思ひ出づる時はすべなみ豊国の由布山雪の消ぬべく思ほゆ |
|
寄物陳思 大船の香取の海にいかり下ろしいかなる人か物思はずあらむ 白真弓石辺の山の常磐なる命なれやも恋ひつつ居らむ 紀伊の海の名高の浦に寄する波音高きかも逢はぬ子ゆゑに 思へども思ひもかねつあしひきの山鳥の尾の永きこの夜を |
|
豊国の企救の浜松ねもころに何しか妹に相言ひそめけむ 霍公鳥飛幡の浦にしく波のしくしく君を見むよしもがも 衣手の真若の浦の真砂地間なく時なし我が恋ふらくは 問答歌 白栲の袖の別れを難みして荒津の浜に宿りするかも 草枕旅行く君を荒津まで送りぞ来ぬる飽き足らねこそ 豊国の企救の長浜行き暮らし日の暮れゆけば妹をしぞ思ふ 豊国の企救の高浜高々に君待つ夜らはさ夜更けにけり |
|
信濃なる菅の荒野にほととぎす鳴く声聞けば時過ぎにけり 相模道の余綾の浜の真砂なす子らは愛しく思はるるかも 多摩川にさらす手作りさらさらになにぞこの子のここだ愛しき 武蔵野の草葉もろ向きかもかくも君がまにまに我は寄りにしを 足(あ)の音せず行かむ駒もが葛飾の真間の継橋やまず通はむ 信濃道は今の墾り道刈りばねに足踏ましなむ沓はけ我が背 信濃なる千曲の川のさざれ石も君し踏みてば玉と拾はむ 新田山(にひたやま)嶺にはつかなな我(わ)に寄そり間(はし)なる子らしあやに愛(かな)しも 上つ毛野久路保の嶺ろの葛葉がた愛しけ子らにいや離り来も 利根川の川瀬も知らず直渡り波にあふのす逢へる君かも 伊香保ろのやさかのゐでに立つ虹の現はろまでもさ寝をさ寝てば 上毛野伊香保の沼に植ゑ小水葱(こなぎ)かく恋ひむとや種求めけむ 伊香保夫(せ)よ奈可中次下思ひどろくまこそしつと忘れせなふも 伊香保風吹く日吹かぬ日ありと言へど吾(あ)が恋のみし時なかりけり 下毛野三鴨の山の子楢のす目妙(まぐは)し子ろは誰が笥か持たむ 会津嶺の国をさ遠み逢はなはば偲ひにせもと紐結ばさね 安太多良の嶺(ね)に伏す鹿猪(しし)のありつつも吾(あれ)は至らむ寝処(ねど)な去りそね 伊香保ろの傍(そひ)の榛原(はりはら)我が衣(きぬ)に着(つ)き宜(よら)しもよ絹布(たへ)と思へば しらとほる小新田山(をにひたやま)の守(も)る山のうら枯れせなな常葉(とこは)にもがも 陸奥の安太多良真弓弾き置きて撥(せ)らしめきなば弦(つら)著(は)かめかも 鎌倉の見越しの崎の岩崩えの君が悔ゆべき心は持たじ 左努山に打つや斧音の遠かども寝もとか子ろが面に見えつる 恋ひつつも居らむとすれど木綿間山(ゆふまやま)隠れし君を思ひかねつも >真久良我(まくらが)の許我(こが)の渡の柄楫(からかぢ)の音高しもな寝なへ子ゆゑに 坂越えて安倍の田の面に居る鶴のともしき君は明日さへもがも 逢はずして行かば惜しけむ真久良我(まくらが)の許賀(こが)榜ぐ船に君も逢はぬかも 足柄(あしがり)の土肥(とひ)の河内に出づる湯の世にもたよらに子ろが言はなくに |
|
海原を八十島隠り来ぬれども奈良の都は忘れかねつも 志賀の浦に漁りする海人家人の待ち恋ふらむに明かし釣る魚 可之布江に鶴鳴き渡る志賀の浦に沖つ白波立ちし来らしも 今よりは秋づきぬらしあしひきの山松蔭にひぐらし鳴きぬ 夕されば秋風寒し我妹子が解き洗ひ衣行きて早着む 天飛ぶや雁を使に得てしかも奈良の都にこと告げやらむ |
|
かくのみにありけるものを猪名川の沖を深めて我が思へりける 安積山影さへ見ゆる山の井の浅き心を吾(あ)が思(も)はなくに 大船に小舟引き添へ潜くとも志賀の荒雄に潜き逢はめやも 豊前國白水郎歌一首 豊国の企救の池なる菱の末を摘むとや妹がみ袖濡れけむ 豊後國白水郎歌一首 紅に染めてし衣雨降りてにほひはすともうつろはめやも 弥彦おのれ神さび青雲のたなびく日すら小雨そほ降る 弥彦神の麓に今日らもか鹿の伏すらむ皮衣着て角つきながら |
|
かきつばた衣に摺り付け大夫の着襲ひ猟する月は来にけり 馬並めていざ打ち行かな渋谿の清き礒廻に寄する波見に 立山に降り置ける雪を常なつに見れども飽かず神(かむ)ながらならし 玉桙の道の神たち賄はせむ我が思ふ君をなつかしみせよ うら恋し我が背の君はなでしこが花にもがもな朝な朝な見む 二十一年春正月の二十九日、よめる歌 東風(あゆのかぜ)甚(いた)く吹くらし奈呉の海人の釣する小舟榜ぎ隠る見ゆ |
|
天平勝宝二年三月一日の暮(ゆふへ)に、春の苑の桃李の花を眺矚(み)て作る二首 |
|
春の苑紅にほふ桃の花下照(で)る道に出で立つ美人(をとめ) 吾が園の李の花か庭に散るはだれのいまだ残りたるかも 吾が園の李の花か庭に降るはだれのいまだ残りたるかも 堅香子草(かたかご)の花を攀折(を)る歌一首 もののふの八十娘子らが汲み乱ふ寺井の上の堅香子の花 天平勝宝二年三月二日 遥聞泝江船人之唱歌一首 朝床に聞けば遥けし射水川朝漕ぎしつつ唄ふ舟人 礒の上のつままを見れば根を延へて年深からし神さびにけり |
| 便附大帳使取八月五日應入京師因此以四日設國厨之饌於介内蔵伊美吉縄麻呂舘餞之于時大伴宿祢家持作歌一首 |
|
しなざかる越に五年住み住みて立ち別れまく惜しき宵かも 廿三日依興作歌二首 春の野に霞たなびきうら悲しこの夕影に鴬鳴くも 我が宿のい笹群竹吹く風の音のかそけきこの夕かも 廿五日作歌一首 うらうらに照れる春日にひばり上がり心悲しも独し思へば |