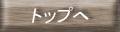放生津八幡宮〜大伴家持〜


|
天平18年(746年)大伴家持卿が越中の国司として赴任、奈古之浦の風光を愛して、豊前の国宇佐八幡神を勧請して奈古八幡宮を興す。後、北条時政が再興したと伝えられる。 |

|
俳聖芭蕉は元禄2年(1689年・46才の春、門人曽良とともに「奥の細道」の旅に立つ。)7月14日(現8月28日)滑川から富山へ寄らず神通川を渡り海老江を過ぎ松原を通って放生津に入り、氷見の担籠(たこ)への道を尋ねたが、「へんぴな所で泊る宿もなかろう」といわれ心もとなく高岡への道を辿る。この句は、このとき詠んだものという。 句碑は芭蕉の百五十回忌の天保14年(1843年)9月、郷土の俳人子邁が翁をしのび建碑する。
放生津八幡宮 |
|
『諸国翁墳記』に「芭蕉遠忌塚 越中放生津東之町端ニ建有礒高吟 無名天遊毫催主俳名碑之裏ニ彫而記」とある。 |
|
大正14年(1925年)8月27日、荻原井泉水は放生津八幡宮で芭蕉の句碑を見ている。 |
|
私達は船で放生津潟を一周してから、町へ上った。町の八幡宮の境内に芭蕉の句碑があるというので、そこへも案内された。 早稲の香やわけ入る右は有磯海 芭蕉翁 百五十回遠忌 天保十四年建之
『随筆芭蕉』(市振を過ぎて) |
|
場所は異るが、富山湾に面した新湊町は、いにしえの放生津である。元禄二年秋、奥の細道の途次、芭蕉は那古の浦で擔籠(たこ)の藤浪を探ろうと、その所在を尋ねたが、ここから五里の磯伝いにわけ入る山陰で、一夜の宿を貸す海士の苫屋もあるまいといわれ、ついに思いとどまった。那古は即ち奈良時代の那呉の入江、万葉の歌によって名高い。大伴家持の歌を刻んだ碑が、新湊町の放生津八幡神社にあり、同じ境内にはまた、 早稲の香やわけ入る右は有磯海 芭蕉 の句碑も建って居る。社域は即ち有磯海の波うつところである。 |
| 昭和44年(1969年)9月、加藤楸邨は放生津八幡で芭蕉の句碑を見ている。 |
|
放生津八幡に入ると、荒れ気味の海がテトラポットに当って、洞然たる音を立てると、却ってどこかぼんやりしてしまう。境内には大伴家持の大きなや歌碑や宗祇の句碑があるが、いつも見る芭蕉の句碑 わせの香や分入右は有磯海 が私の記憶するあたりには見あたらない。そのあたりには十月はじめに行われるこの八幡の祭礼のために」やってきた香具師(やし)達の自動車がいくつも並び天幕を張って生活しているのが見えるばかりだ。傍に寄って天幕の中を覗くと、その横手に天幕の太綱をがんじがらめに巻きつけて支柱がわりにされているのが芭蕉の句碑である。これは古く中程から割れていたのをつなぎあわせたものだ。この調子だとまた破損がひどくなりそうである。 |

|
天平20年(748年)正月29日作歌
巻十七(4017) 東風(越俗語、東風謂二之安由乃可是一也) 伊多久布久良之 奈呉乃安麻能 都利須流乎夫禰 許藝可久流見由 (安(あ)ゆの風 い多久(たく)吹くら志(し) 奈呉能(の)海人能(の) 釣春流(する)小舟 こ幾(き)隠る見遊(ゆ)) 早春の「奈呉之浦」の景、「東風」は、当市では「アイの風」と呼び、北から吹いて豊かな海の幸を運ぶという。
放生津八幡宮 |