『奥のほそみち画冊』(小杉未醒)
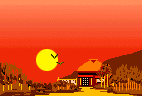
| 昭和7年、 | 春陽堂出版。 |
||||||||||||||||||||||
| 昭和30年、 | 龍星閣再版。 |
|
年来この奥の細道に興味を持つて居たところから、昭和2年の10月に思ひ立つて、友人岸浪百草居と、ほぼ本文に從つてあるいて見ました。 |
|
新緑の日光参りをすまして、芭蕉翁と曾良とは宇都宮より奥州街道へのかねに曲る本道を經ず、斜めに鹽谷郡を突切つて羽黒に向ふ、野みち村みち、途中の矢板に出るまでに、絹川を渡り船生玉生などの村村がある、
矢板あたりから那須野の分になるであらう、羽黒の町は下野の國の東端、奥州街道より大分に右に外れて、那珂川の岸にあり、今以て一風情ある趣、あの邊は常陸の國境に近く、那珂川は流れて水戸を經て海に入り、やゝ舟運の便あり、 |

|
雲巌寺は山に倚り渓に臨み、今もよしありげな大寺、黒羽より近き處にある、
黒羽より那須温泉へ行く道は、現在は畠ばかりなれど、歩いて見れば、さすがに名高い那須野が原の平濶、風物何となく一荒れ荒れた趣を持つて居る、次第に上つて那須火山の膝の上あたりに温泉場、殺生石は二つの谷川の合流點、磧の中に在つて、今も虫などの骸落ち居り、或時學生が、ステツキで砂中に穴を作つて、鼻をつけて嗅いで見て、其まま倒れたと云ふから、いつまでも九尾の狐の呪毒は殘つて居ると見える、 |

|
橋一つ渡つた處に、4、5軒の部落、其處に一本の老杉あつて、高さ一間ほどの塚の上に立つ、即ちみちのくの、安達が原の黒塚なるもの、そのかみ草木生ひ茂つて遠く望めば黒々と見えたで此名あるか、杉の木の下に二尺ほどの立札、朱色に塗つて白字で達筆に黒塚と記してある、その朱も白も古び燻んで見えた。 |

|
飯坂から福島の方へ、電車路を少し行つて、右へ折れると、朝風の吹き通る赤松林、村になつて、行き留まつた處に、瑠璃光山醫王寺、處は信夫郡平野村、山門を入つて右に庫裏本堂、すぐに行つて大杉林の下に古い墓共、字はすべて剥落して見えず、正面に大いなるを佐藤勝信の墓とし、右に二つ並びたるを子供の嗣信忠信の墓とする。 再び飯坂に出て、夜前の宿の前を過ぎ、伊達の大木戸あつたあたりなる、伊達の驛まで行つて汽車を待つ、此の飯坂に於て、土座にむしろ敷きたる、あやしき貧家に芭蕉翁は持病を抱いて明かした。今の飯坂は東北屈指の温泉場、昨夜の暮、何處に泊らう、あの柳のある家にしようと云つた其宿は、此町の第3、4流のものか知れぬが、川に臨んで三層をたゝみ、なかなか立派な構え、夜は酒くみかはし、朝も朝酒名物箱入納豆をしたゝかに参つて、鼻唄交りに立つて來た、 |
|
小春日和の仙臺で、二人のしるべをたづねる、一人は大學病院の杢太郎博士、それと連れ立つて他の一人の小宮氏を訪ふ、 船は瑞巌寺の下に着く、松島は是で二度目、松島元より扶桑有數の奇景にちがひないが、何故か二度共さやうに強くはわが心を惹かず、芭蕉が此處と並稱したる出羽の象潟は、水涸れて田圃となつて居ても、その事に却つてわが幻想を助くるが如く、しめやかにあはれに眺めあかした、 日和山は北上川の岸に長く延びて立つ丘陵、上には石の巻神社愛宕社、松古りて静かなる眺め、 |
|
芭蕉翁の、夏草やの句碑は、此の毛越寺の池畔に、行疫神の石碣と並んで立てゝあつた、行疫神なるものを、石碣に刻したるは珍らしいと思ふ、
しかしながら芭蕉翁がまことに夏草やの感興あつたは、此處ではなく、毛越寺から停車場に戻つて、尚線路を越えて北上川の岸なる高館の岡でなくてはならぬ、
高館は名の如くの高丘、今は杉林茂り陰氣なる處、秀衡が跡の田になつたあたりから、先づ4、5町あるか、さらば泰衡共が、判官討ちを企てゝも、どうで知れぬ筈なし、知れなば何とか手段ありさうなもの、よくよくの運とあきらめて腹を切つたか、などと思ふ事既に芭蕉翁と等しき、判官びいきの爲でもあらう、岡の頂に堂あつて色白の男の甲冑姿、餘り上作ではない等身の判官像が祠つてある、堂の直下の岸は北上川の曲り角に當つてザラザラと崩れて居たが、古い地圖では、ずつと向ふの、名所束稲山の方に流れがあつたやうす。 奥州では、人の祠堂に像を作る習ひあつたか、前文佐藤兄弟の嫁女の甲冑堂もあり、此處でも、金色堂近くの辨慶堂には武藏坊立往生の泥塑、六尺ばかりの大入道の、色黒く逞ましく、分別臭きが、七つ道具を森の如く負ひなし、大薙刀をついて波型を踏んで居る、 |
|
鳴子の温泉は、今は繁盛ながら、案内記を見ても遂近年の發展、芭蕉翁の頃はほんに微かな山の湯であつたらう、尿前の關の跡は今も在つて、温泉から半里ほど、大谷と荒尾の二溪合流の處、山ふところの陰氣な小村、關守の遊佐氏は昔からの家柄、今は落魄したと云ふ、
是から直ぐに中山越にかゝる、以前は馬で荷を運ぶほどの路、今は自動車も樂に走る、我等は徒で秋日和のどかに、千尺ばかりの峠故、汗もかゝぬ程で過ぎた、細道の本文、のみしらみ馬の尿する山家に宿つたのは、此の峠と鵜杉の村の間と思はれる、封人の家の封人を註して、國境の役人とあれば、陣森堺田あたりでもあるか、三日の荒天で山中逗留と云ふは、溪川の出水で橋でも落されたか、
村の若者の反脇差を横たへ、樫の杖をつきたてたるを案内にして、今日こそいかなる恐ろしき事に會ふかと、小心翼々として越した山路即ち龜割峠、見受けるに、さやうな深山とも思はれず、細道本文の此段は、讀む者をして若干の好奇心を催さしむる處、蕉翁捨身の風流であるが、蕉翁元來かみがた生れで、山馴れせず、多少の恐怖観念あつた爲、文章却つて凄壯異常となつたかも知れぬ、 |


|
しづけさや岩にしみ入る蝉の聲、此句は思ふに杜甫の、伐木丁々山更幽の七字より數段優れたものであらう、此句より立石寺を想望し來つて、さてその山寺(此邊では專ら立石寺を山寺と云ふ)の山門を入れば、にぎやかな見物衆物賣りの店も並び、細道導者には、大分に當ての外れた景氣、 |
|
古口と云ふ小驛で、新庄酒田間の夜汽車を降り、此邊に宿屋はありませんかと聞けば、驛長さんが、わざわざ出て来て、あれを突き當つて曲つて、それから左側に、かめ屋と教えて呉れた、突き當りは、雲すきに山の形が見えるばかり、 仙人堂、大杉のむら立つ中に、陰々として苔をかついだ茅の屋根、船を寄せて、しとみ格子から差し覗くと、天狗の面など飾りあり、何を祀つたものやら、船頭に問へば、唯、御仙人様だと云ふ、常陸坊海尊の傳説もあつたと覺えて居る、同じく義經の話も此の川筋にあつた筈、白糸の瀧、さらさらと山を下つて直ちに川に入る、 |

|
門を入れば坂となつて下つて谷川に擬宝珠の橋がかゝり、右なる崖に瀧落つ、第二の門五重の塔、杉の木は生ひ茂り神さび、磴道(とうどう)に苔深く次第に登り坂、 |

|
芭蕉翁を此地で待ち受けて、專ら世話を燒いたと云ふ圖司左吉俳名呂丸なる人、是れ當時芭蕉流俳道の爲には、此地方の鎮臺を承つたものであらうか、七年後に桃隣の行つた時は、既に故人となつて居た話、まめやかに芭蕉翁をあるじしたる、別當會覺阿闍梨も亦並々の坊さんではないと見える、芭蕉をはなむけして、忘るなよ虹に蝉なく山の雪の句など、素人の藝ではあるまい、 |

|
日本海の潮がせまい水口、汐越しと稱する處から出入する、底淺き入江、ぐるりと廻つて三里足らず、九十九の島あり、八十八の浦曲あり、島ごとに松生へ、松の下にねぶの木多く、夏となれば、かそけき紅白の花を着ける、其の島々の松と合歡の木は今もあるが、文化年間鳥海山噴火の餘勢で、地盤の隆起の爲に、入江の水は日本海へ放下されて、底の藻草も乾き、小魚共も途方に暮れたであらう、 |
|
鼠が關に立寄る、關の跡は内務省製コンクリートの大きな碑立ちあり、すぐに濱邊で、一山脈の突端、關跡をめぐつて海に入る、出羽越後の境、相當要害の場所であつたらう、 |

|
大蓮華山の餘脈、延びて越後越中の境に到つて、日本海の風濤に斷たれて連綿たる岩壁をない、即ち親不知子不知の難所、市振の里は、此處より漸く越中の平野に出でようと云ふ處、山と海にはさまれて在る、新潟の二人の娼婦にたよられて、芭蕉翁モヂモヂと氣の毒さうに云ひことはる、一つ家に遊女も寝たりと咏んで、自身あはれに興深く思はれたやうす、 |
|
山中温泉こほろぎ橋の袂で、からりと晴れた山を眺めつゝ、ひるめしを喰つて、湯には入らず、吉崎の入江に向ふ、山中の湯の宿の主人俳諧巧者のほまれあつた者の記事、細道本文にあるが、此の湯の宿は今以て引つゞいて居ると云ふ話、此處で御伴の曾良は腹をやんで別れ去る、ひそかに思ふに、温泉で腹を病んだなら、寧ろ留まつて療養すべきと思ふに、伊勢まで行つてしまつたとは又どう云ふものか、 秋のあはれ入かはる湯や世の氣色、ゆきゆきてたふれ伏すとも萩の原、よもすがら秋風聞くやうらの山、曾良の三句此際に於て少しく悲愴に過ぐと思ふが、さやうな行違ひ若しあつたとしても、つまり旅中のわがまゝ、いくばくもなく大垣で此の同行再會の時に及べば、只長途の思ひ出をなつかしむのみであつたらう。 |
|
加賀の国山中の湯より、大聖寺の町に出て全昌寺を訪ふて見る、曾良が師匠に別れて、百餘日の侍者の生活を放たれ、しみじみと只一人の秋の風を、よもすがら聞いたお寺、(中略)曾良一宿のあくる夜、翁も此寺に一泊す、一夜のちがひならば、同行ありてもよささうなもの、此頃は此寺雲水なども多かつたと見え、若き僧ども紙硯かゝへ、階のもとまで追ひ來つたとあるが、今は静かなやうす、 |

|
越前福井より輕鐵で永平寺に行く、お寺は立派なお寺、参詣の人々の爲に、玄關に俗の5、6人も机をひかへ、今普請で中々のにぎはひ、よく新聞で、管長争ひの騒ぎを見るほどの、富有熱閙寺、杉の木立の間に、唐風の建築、山門前の晝食に蕎麥をしたゝめ、又福井へ取つてかへす、福井から武生、此の福井の城下端れに、蕉翁は笠を傾けて、舊知等哉のわびずまゐを見付けあるいたであらう、 |

|
再び武生驛にかへつて、汽車で敦賀の港に向ふ、細道の旅も終りに近づいて、かへり見れば見殘した處も少からず、
彼の奥州の武くまの松や、野田の玉川沖の石、かつみかつみと歌枕尋ねあるくまでの心はないが、出羽の尾花澤、月山、湯殿山、越後の出雲崎、加州に入つて、石山の石より白しと咏んだ那谷の觀音などは、とりどりに見處あつたらうと思はれる、 |
|
敦賀彎の朝晴れに、先づ氣比の神宮に參つて、波止場に出て昨夜頼んで置いた石油發動船の釜の燒くるを待つ、右手の丘の直ちに海に臨めるは、南朝のあはれを留めた金が崎の古城、 |

|
これにて我等の細道の旅終りを告げる、金が崎古城の中程のお茶屋で、夜汽車までのひま潰しに、牛鍋で一盃傾けた、其時南朝新田方の勇士海上三里を泳ぎ渡つたが、此下の磯にでも上つたか、此處は要害の切處だが、いざ落城となれば袋の鼠で逃げ場なからう、皇子方はいたはしかつたと、語る語る眠くなり、さし入る小春の日影あたゝきに手枕して、同行二人、思ひ思ひの夢に入り去る、あすは東京に着くばかり。 |
|
附記 芭蕉翁をよろこび、旅行を樂しむ人に、此の細道のコースをおすゝめしたきもの、私の行程は歸りの夜汽車を入れて11泊ほど、平泉象潟へ廻れば2泊も延びるか、來迎寺の代りに出雲崎へ行き、岡本村の時間を那谷の觀音に向くべきであらう、行嚢の中に若干の參考書を収めて行つたが、就中大藪寅亮氏著「奥の細道の新研究」の一書に便る事多かつた。 |

