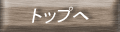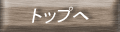〜芭蕉の句碑〜

あやとりはしからこおろぎ橋へ。

こおろぎ橋から大聖寺川を見下ろす。

蟋蟀橋
元禄時代以前からかかっている橋で、山中温泉の代名詞ともいえる名勝です。
この付近は岩石が多く、行く路は危なかったので(行路危)と言われ、また秋の夜可憐に鳴く蟋蟀の声にちなんで名付けられたとも言われています。
四季を通して山中を訪れる多くの人の目を楽しませてくれる山中八景の一つです。
蟋蟀橋を渡ると、北枝の句碑があった。

子を抱いて湯の月のぞく猿かな
出典は『卯辰集』。
明治21年(1888年)6月、建立。
芭蕉の句碑があった。

かゝり火に河鹿や波の下むせひ
出典は「真蹟懐紙」。
『卯辰集』には「いざり火にかじかや波の下むせび」とある。
河鹿は河鹿蛙ではなく、鰍(かじか)。魚である。
明治31年(1898年)、建立。
八景の内竈馬(コウロギ)の橋は巖石にかゝりてみなき
|
る水のかしこにくたけ爰に泡まく黄石公か沓も流れつ
|
へし
|
|
こうろきの夢に渡ルや橋の霜
| 涼菟
|
大正14年(1925年)8月31日、荻原井泉水は山中温泉を歩いて蟋蟀橋にやってきた。
町の中を通りぬけると、佳い流がある。それまでは町の裏を流れながら旅館に依って隠されていた大聖寺川である。川は谷をなして深く潜み、或る所では青い淵となって澱んでいる。その上に橋脚をY字形にせってもたした橋が架っている、蟋蟀橋とて、山中第一の名勝と云はれている。
『随筆芭蕉』(山中の湯)
昭和2年(1927年)10月、小杉未醒は「奥の細道」を歩いて、こおろぎ橋に立ち寄った。
山中温泉こほろぎ橋の袂で、からりと晴れた山を眺めつゝ、ひるめしを喰つて、湯には入らず、吉崎の入江に向ふ、
昭和6年(1931年)1月7日、与謝野晶子は山中温泉を車で一巡する。
青雲と白雲の來て舞ふ谷のこほろぎ橋と思ひけるかな
「深林の香」
昭和53年(1978年)、樋口可南子はポーラテレビ小説「こおろぎ橋」でデビューしたそうだ。
私は見ていないから、よく分からない。
「かがり吉祥亭」へ。
私の旅日記〜2008年〜に戻る