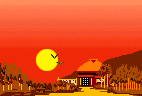佐場野の里医王寺をたつね判官殿のむかしをとふて宝物を拝むに安宅の関の有さまそまつ思はるゝ
|
寛延4年(1751年)、和知風光は『宗祇戻』の旅で医王寺を訪れた。
次信忠信の墓は伊達の郡鯖野の里有医王寺ニ両子の武勇如金剛喩草木迄モ赤キハ悪カラメト思ヒヤリテ
モミヂ(※「木」+「色」)する木々もや塚のにくからむ
宝暦2年(1752年)、白井鳥酔は医王寺を訪ねている。
○しのふの里なる佐藤庄司か城跡を尋ぬ醫王蜜院に杖を引て刹裡に建る所の兄弟か遺碑を見る誠に矢しまの次信吉野の忠信を感して
殘る名に跡さきはなし花紅葉
明和元年(1764年)、内山逸峰は医王寺で弁慶の遺品を見ている。
同く近きあたりに佐橋村といふ有。そこに瑠璃光山医王寺とて真言宗の寺あり。外に薬師堂有。佐藤庄司が守本尊也、弁慶が手跡の金(紺)紙金泥の大般若経一巻、并に笈も有。
寛政3年(1791年)6月1日、鶴田卓池は医王寺を訪れている。
壱り十一丁藤田 壱り七丁桑折
鯖野村医王寺 什物義経ノ笈太刀弁慶ガ太刀アリ
鯖野村ニ佐藤庄司カ館ノあとアリ 南殿ノさくらと云アリ
古木也
正岡子規は医王寺に行かなかった。
昭和2年(1927年)10月、小杉未醒は「奥の細道」を歩いて、医王寺を訪れた。
飯坂から福島の方へ、電車路を少し行つて、右へ折れると、朝風の吹き通る赤松林、村になつて、行き留まつた處に、瑠璃光山醫王寺、處は信夫郡平野村、山門を入つて右に庫裏本堂、すぐに行つて大杉林の下に古い墓共、字はすべて剥落して見えず、正面に大いなるを佐藤勝信の墓とし、右に二つ並びたるを子供の嗣信忠信の墓とする。
昭和43年(1968年)、水原秋桜子は医王寺を訪れている。
福島、医王寺
卯の花や判官主従のこす笈
佐藤嗣信、忠信用鎧
卯の花やみちのくぶりの大鐙
『殉教』
『奥の細道』 〜東北〜に戻る