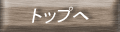那谷寺〜重要文化財〜
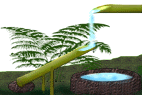


|
養老元年(717年)、泰澄法師自生山岩屋寺開創。 寛和2年(986年)6月22日、花山天皇は右大臣藤原兼家の謀事によって出家させられる。 永延2年(988年)、花山法皇は那智山青岸渡寺に御幸され西国三十三ヶ所第1番札所として定め、谷汲山華厳寺を第33番札所の満願所と定められた。 永祚元年(989年)、花山法皇は北陸へ御巡幸、西国三十三ヶ所の第1番那智山の「那」と第33番谷汲山の「谷」をとって自生山岩屋寺を「那谷寺」と改めた。 |


|
元禄2年(1689年)8月5日(陽暦9月18日)、芭蕉は山中温泉で曾良と別れ、北枝とともに那谷寺を訪れている。 |
|
山中の温泉に行ほと白根か嶽跡にみなしてあゆむ左の山際に觀音堂あり花山の法皇三十三所の順禮とけさせ給ひて後大慈大悲の像を安置し給ひ那谷と名付給ふと也那智谷汲の二字をわかち侍しとそ奇石さまざまに古松植ならへて萱ふきの小堂岩の上に造りかけて殊勝の土地也 |


|
那谷寺に踏み入ると、木立暗く、べたべたの落椿だ。更に進むと右に岩の小丘がある。苔蒸したその岩を負うて、碑が二つ並んでいる。 一つは句碑だ。大きな三角形、大きな字 石山の石より白し秋の風 他は「翁塚」で、「奥の細道」の那谷寺の条を刻み、その最後を「石山の石より白し秋の風」で結んでいる。この句は相並ぶ碑に重ねて出ているのだ。
『句碑をたずねて』(奥の細道) |
|
元禄9年(1696年)、竹内十丈は山中温泉から那谷寺を訪れたようである。 |
|
山中の温泉より那谷にまうてけるか、小松より行程二里はかり、麓の人里も那谷村とかいふなる。それより入て圓通大師の御堂を拜むに、諸堂は皆國君の作りみかゝせ給ひて、莊嚴の美を盡させたまふ。山の姿云はかりなし。百尺の石を疊むて削出すかことく、峨峨としてかつ玲瓏たり。此那谷の石のたゝすまゐ、都の石山よりもまされりと云傳へしか、古翁一とせ此山に詣給ひしに、石山の石より白し秋の風といふ句を、今猶おもひ出られて |
|
其石の白みに馴て躑躅かな |

|
元禄16年(1703年)秋、岩田涼菟は山中温泉から那谷寺を訪れている。 |
| 那谷の觀音は湯本より三里はかりの道也桃妖の |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主おくり來て名殘をしたふ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石山の石より白し秋の霜 | 翁 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 此句も此處にての事なるへし |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見上たり撫たり岩に蔦かつら | 涼菟 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
享保6年(1721年)、露川は門人燕説を伴い那谷寺に参詣している。 |
| 北國の名山那谷寺にまふでゝ、折ふし |
|||||||||||||||||||||
| むら雨を聞く。 |
|||||||||||||||||||||
| 那谷寺の雨や廬山の蝉の聲 | 同 |
||||||||||||||||||||
| 石山の圖や吹立て雲の峰 | 無外 |
||||||||||||||||||||

|
明和8年(1771年)、加舎白雄は北陸行脚の旅で那谷寺を訪れている。 |
|
那古山に登る。こや花山法皇御願みちさせ玉ひ西国三十三所の霊場をこの一字に籠給ひし石と。山のいしより白し秋の風、爰に至りてふたゝび一唱三嘆、 夏山や巡礼泣て石の露 |

|
明治42年(1909年)9月29日、河東碧梧桐は那谷寺に参詣した。 |
|
九月二十九日。雨。 出発前の寸閑を偸んで、一人那谷寺に詣った。紀州の那智谷汲の両観音を勧請したので、字も那谷と書き、読み方までも「ナタ」という。石山の石より白しとは口についた芭蕉の句であるが、それよりも境内の椿、楓の森に、物寂びた奥行のあるような感が深かった。今十日もたつと紅葉が宜しゅうございます、と案内に立った車夫がいう。予は却って幹の苔づかぬのはない古木の山椿に、真紅の花をつけた、一木々々盛りこぼれるほど咲き満ちたおどろな森の景を眼前に思い浮べた。 |
|
大正14年(1925年)8月30日、荻原井泉水は那谷寺を訪れている。 |
|
大悲殿も又、山の中腹の岩窟に象嵌したように造ったもので、その前にさし掛けてある舞台の屋根が遠くから仰いで見られる。今は板葺であるが、芭蕉の頃は「萱ぶきの小堂」であったのであろう、これも「岩の上に造りかけて」ある形で、そこへは自然石の階段を上るのであった。岩窟の中の内陣は御厨子の前の荘厳道具が灯籠の明りでうっすりと光り、詣拝の者僅かに二、三人の膝を容れられる位の狭さだった。境内に六重塔を建てて芭蕉塚と称するものもあった。
『随筆芭蕉』(小松という所) |

|
昭和6年(1931年)1月7日、与謝野寛・晶子夫妻は那谷寺を訪れている。 |
|
いにしへの法皇の夢なほここに御寺となりて殘る山かな 那谷寺の石を撫でつつなほこれに通へる身とは思はれぬかな 護摩堂のみやびやかなり護摩法に歌をば代へて仕へまつらん
「深林の香」 |
|
昭和8年(1933年)11月9日、与謝野寛・晶子夫妻は再び那谷寺を訪れている。 |
|
那谷の山もみぢのなかの幹さへもほのかに岩の白さなるかな 那谷寺のもみぢのかげの岩山に在りて明るし今日おもふこと 金沢の友送り来て那谷寺の紅葉のもとになほ語るかな この度は紅葉の時に来あはせてまた賜はりぬ那谷寺の酒 那谷寺の紅葉のかげにわが友と云ふ別れこそ明るかりけり 那谷寺の秋に澄みたる心には謙信の琴さやかにも鳴る |

|
昭和23年(1948年)6月、中村草田男は那谷寺に参詣している。 |
|
「奥の細道」の旅に於ける芭蕉の「石山の石より 白し秋の風」の吟をのこせる那谷寺に詣づ。 柿落花石山への道すでに白 石山仰ぐ白き夏日の路溜(みちだま)り 石山の面(おも)に夏木の枝揺る影 芭蕉の旅路森へ抜けけん巖すずし 石山裾むかしを繋ぎ花菖蒲
『銀河依然』 |
|
昭和44年(1969年)8月29日、荻原井泉水は再び那谷寺を訪れ山代温泉泊。 |
那谷寺 |
|
| 時、処、ひぐらしの鳴きそうな、鳴く | 八月卅日 |