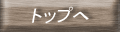『奥の細道』〜東 北〜

夏草や兵共か夢の跡

医王山金剛院毛越寺

天台宗別格本山である。
慈覚大師円仁開基。
芭蕉の句碑
『奥の細道』〜東 北〜

夏草や兵共か夢の跡

医王山金剛院毛越寺

天台宗別格本山である。
慈覚大師円仁開基。
|
寛保2年(1742年)4月13日、大島蓼太は奥の細道行脚に出る。10月6日、江戸に戻る。 |
|
高舘毛越寺懐古 礎をかぞへあまして秋の暮 |


|
記念句集『古にし夢』(安永2年刊・烏明序)によれば、明和7年の建立だそうだ。 |
|
天明6年(1786年)1月27日、菅江真澄は毛越寺の旧跡を見ている。 |
|
廿七日 毛越寺のふる蹟見なんとて田の畔づたひして、礎の跡なンどにいにしへをしのぶ。 廿八日 毛越寺の衆徒某二人、日吉ノ山に登り戒壇ふみにとて旅立ければ、此法師たちに、故郷に書(フミ)たのむとて、 ふる里を夢にしのぶのすり衣おもひみだれて見ぬ夜半ぞなき と、そのふみにかき入れたり。
「迦須牟巨麻賀多(かすむ駒形)」 |

|
はせを翁の姪(ママ)碓花坊也寥禪師は伊賀の産にしてみちのく柴田郡舟岡に錫をととめ律梁のあたり風流にあしをととめる事年あり此の禪師や翁終焉の折夏草の遺草を記念と送られしを常に懐にしてはなさす幸ひこの地に杖引のおりからその真跡を石に彫付夏草塚とよへりけりしかはあれとも星うつり物かわりて泥土集りて石埋み青苔なめらなにして文字さたかならすされはこたひ新たに石をもて石にならぶこれ名と利とにほこるにあらすたゝもろ邦の風士訪ひ安からん事を思ひ其流れを汲の徒後世に翁の徳を挑ん事をねがふ 時文化三丙寅とし卯月日 櫻川慈眼庵主 素鳥 |
|
素鳥は中尊寺の僧。杉坂百明の友人である。武藏坊弁慶大墓碑に句碑がある。 |
|
昭和2年(1927年)10月、小杉未醒は芭蕉の句碑を見ている。 |
|
芭蕉翁の、夏草やの句碑は、此の毛越寺の池畔に、行疫神の石碣と並んで立てゝあつた、行疫神なるものを、石碣に刻したるは珍らしいと思ふ、しかしながら芭蕉翁がまことに夏草やの感興あつたは、此處ではなく、毛越寺から停車場に戻つて、尚線路を越えて北上川の岸なる高館の岡でなくてはならぬ、 |
|
昭和3年(1928年)7月26日、荻原井泉水は毛越寺で芭蕉の句碑を見ている。 |
|
大泉の池はまんまんとした青黒い水を湛えて、その中から丈の高い凉しい蘆のような草が生えていた。池の畔に―― 夏草や兵どもが夢の跡 芭蕉 この句碑が、旅の人に何かを考えさすように、ぽつねんと立っていた。だが、芭蕉がこの句を作った高館の跡には、あした行って見ることにしよう。
『随筆芭蕉』(平泉に到る) |
|
昭和11年(1936年)6月26日、 種田山頭火は石巻から平泉を訪れた。 |
|
六月廿六日 雨。 早い朝湯にはいつてから日和山の展望をたのしむ、美しい港風景である、芭蕉句碑もあつた。 十時出発、汽車で平泉へ、沿道の眺望はよかつた、旭山……一関。…… 平泉。―― 毛越寺旧蹟、まことに滅びるものは美しい! 中尊寺、金色堂。 あまりに現代色が光つてゐる! 何だか不快を感じて、平泉を後に匆々汽車に乗つた。 |
|
毛 越 寺 草のしげるや礎石ところどころのたまり水 |
| 昭和15年(1940年)6月11日、北原白秋は達谷窟から毛越寺に回って中尊寺へ。 |
|
達谷の巌から毛越寺に廻って、初めて私はその静寂と、古の典雅とに觸れ得た。平らか豐かな規模の中に池が湛へ木立と堂宇が今にもしづかに殘されてあつたのだ。
「初夏東北行」 |
|
昭和28年(1953年)6月19日、水原秋桜子は毛越寺を訪れた。 |
|
六月十八日夜上野発、十九日朝平 泉着。乗合馬車にて毛越寺を訪ふ 軋りいで馬車や雨降る夏柳 喇叭吹き馬車着く梅雨の毛越寺 萍や堂塔亡びまた建たず
『帰心』 |
|
昭和40年(1965年)、山口誓子は毛越寺の句碑を訪ねている。 |
|
毛越寺を入った右手、大泉池をうしろにして、芭蕉の句碑が二基並んでいる。同じ句。 右のは、烏帽子型の自然石。 夏草やつはものどもか夢の跡 左のは、へしゃげた烏帽子型の自然石。 夏草や兵共が夢の跡 右が新碑、左が旧碑。何も新旧二碑が並んでいなくてもいいだろう。と誰も思うにちがいない。私もそう思った。 古碑は高館にあった。絶壁の近くにあった。崖が崩れるので毛越寺に移した。すでに新碑が建っていたから、相並ぶことになった。その説明は一応私を納得させたが、旧碑は、高館に残して置いて欲しかった。あの丘の上にはいくらも安全な土地があるのに。
『句碑をたずねて』(奥の細道) |

| The summer grass |
| 'Tis all that's left |
| Of ancient warrior's dream. |