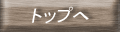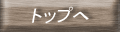芭蕉の句碑
『奥の細道』〜東 北〜

佐くらより松盤二木を三月越し
東北自動車村田ICから県道25号岩沼蔵王線で岩沼に向かう。

東北本線を越えて右折すると、竹駒神社がある。

竹駒神社御社殿

主祭神は倉稲魂神。
日本三稲荷の一社に数えられているそうだ。
平成2年(1990年)11月21日、過激派の暴挙により炎上消失。
平成5年(1993年)9月6日、竣功奉告祭。
竹駒神社
竹駒神社は、第54代仁明天皇の御代承和9年(842年)に参議小野篁(たかむら)が陸奥守に任ぜられて国府に向かうにあたり、奥州鎮護の神として、京都の伏見稲荷の御神霊をこの地に祀りました。
小野篁は小倉百人一首の歌で知られている。
わたの原八十島かけてこぎ出ぬと人には告げよあまのつり舟
承和5年、小野篁が隠岐に流される時の歌である。
2年後の承和7年に都に戻り、さらに2年後陸奥守に任ぜられわけである。
元禄2年(1689年)5月4日(新暦6月20日)、曽良は竹駒明神と武隈の松のことを書いている。
一 四日 雨少止。辰ノ尅、白石ヲ立。折々日ノ光見ル。 岩沼入口ノ左ノ方ニ竹駒明神ト云有。ソノ別当ノ寺ノ後ニ武隈ノ松有。竹がきヲシテ有。ソノ辺、侍やしき也。古市源七殿住所也。
芭蕉は武隈の松のことを書いている。
元文3年(1738年)4月、山崎北華は『奥の細道』の足跡をたどり、竹駒神社に詣でている。
簑輪。笠島。實方朝臣の古墳。形見の薄とむらひ。道祖神の社詣して。武隈の松によりて見る。二木の姿替らず。いと愛度(めでたく)榮えたり。如何と問はばみきと答へんと詠みし事思出て。
武くまや松の二木はみきもよき
と戯れ。武隈明神に詣づ。竹駒明神と額あり。寺をも寳窟山竹駒寺といふ。開山能因法師。陸奥の國に下りし時。武隈の松なかりしかば。尋ね侘けるに。童子の竹馬に乘れるが來りて。松の事教へて。狐と成て去りしとなん。夫より竹馬を寺の名とし。稲荷の社を祭りしといへどいかが。武くま竹こま何時の頃にか書違へたるを。かく事作りたるらめとも思はるゝのみ。
竹駒神社の前に芭蕉の句碑がある。

左が芭蕉句碑(二木塚)
佐くらより松盤二木を三月越し
謙阿句碑と同時に建立。
奥州武隈松にて
桜より松は二木を三月越
奥細道を按するに、元禄二年弥生末七日武江を立て皐月はしめ隈松に至る。依て桜より三月越とその日数を云て夏季慥なるへし。只長途の観想、紙毫に及ふへからす。哥に「武隈の松は二木を都人いかにと問ハミきと答む」
右が謙阿(名月塚)句碑
朧よ里松は二夜の月丹こ楚
寛政5年(1793年)、芭蕉翁百年忌法要を記念して建立されたと伝えられているそうだ。
東龍斎謙阿は古内家の給士にて、俳人青灯下祇川の門に入り、斯道の達才を以て称せられ、夙に正風を汲み芭蕉六世と称した。
祇川は近江の俳人。許六の門人。幻住庵。明和(1764〜1772)の頃、岩沼に住んで俳諧を指導。
安永6年(1777年)8月、義仲寺で死去。
明治30年(1897年)10月11日、幸田露伴は武隈神社を訪れている。
此駅にて汽車を待ち合はす間空しく時を過さんも愚なることなり、笠島の神に詣で実方中將の奥城所をとむらはん暇は無くとも、武隈神社拝みまゐらするほどのことは叶ふまじきにもあらざるべければ、いざいざ参らんとて、車を急がせて行く。大鳥居を望み見て車を下り、神前さして歩み寄りつ、ふと頭を挙げてみれば、鳥居にかゝれる扁額には竹駒神社と記しあり。むかし此の御神竹馬に騎りたまひて此処に来たまひしにより武隈の文字或は竹駒にかふと、聞老志に記せるも思ひ合さる。
境内いと広く、枝垂桜の花は今無けれど眼につくほどなるもありて、随身門などの物古りて寂びたる、いと好し。三條公の筆を揮はれたる翔鳳の二字もいと目出たく、本社の神さびたるもいと尊し。むかしは無智の民ども此の御神を狐なりとや思ひひがめ居けん、畏しと云はんも愚なり。三拝して後、二木の松をも尋ねばやなど云ふ中、時はやせまりぬ、疾く停車場に返りたまはではと車夫の云ひ罵るに、已むことを得で引返せば、危くも汽車は今や軋り出さんとするところなり。とつかはと車を下りて車に入り、漸くほつと息つけば、岩沼の駅は既背後に在り。
「遊行雑記」
武隈の松は竹駒神社のすぐ近くにあったはずだが、私は先を急いで立ち寄らなかった。
中将実方の墓へ。
『奥の細道』〜東 北〜に戻る