
太宰府天満宮〜碑巡り〜

| ・祭神 菅原道真公 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・鎮座 延喜3年2月25日 |
|
菅原道真公は、承和12年6月25日京都の菅原院で御生誕。国家の隆盛と文化の発展に尽され、延喜3年2月25日配所榎寺に於いて清明の一生を終えられ、現在の御本殿の地に葬り、菅聖廟安楽寺天満宮と称えて奉祀す。誠道守護・学業成就・除災招福等の信仰厚く、全国天満宮の総本社とも仰がれる御社であります。 |

|
昌泰4年(901年)に大宰権帥を命じられた菅原道真公が京都を出発される際に紅梅殿の梅に惜別の想いを込めて詠じられたもので、公を慕って一夜のうちに京より大宰府まで飛来したといわれる御神木「飛梅(とびうめ)」(御本殿右側)の由来として有名である。 |

|
大宰府三句 しぐれて反橋二つ渡る ・右近の橘の実のしぐるゝや ・大樟も私も犬もしぐれつゝ |
|
文明12年(1480年)9月17日、宗祇は太宰府天満宮の宿坊満盛院に着く。木屋瀬で天神から扇を得る夢を見たが、実際に扇が与えられた。 |
|
とかく過行程に、御社近く塔婆など見ゆるより、下りて、神前を拝して、宿坊満盛院に至りぬる程、暮はてぬ。今夜は当社の縁起など読ませ奉るほどに、深野筑前守といふ人来る。この郡の郡司也。扇を携へて、心ざす当社にて此扇を得る事、夢の告思ひ合て、いとゞ神慮有難くなむ。 |
|
つとめて、社僧一人を友なひ神前に参る。表の鳥居さし入より、地広く松杉数添ひて、さらぬ、常盤木やゝ繁し。反橋高うして二有。又打橋だつ、その中にあり。池の廻りには千万株の梅の林を成せり。覚えず西湖の境に来るやと覚ゆ。楼門に入ほど神々しくて、左右の回廊いさぎよし。名に負ふ飛梅苔むして、老松の齡にも争へり。抑当社は延喜五年乙丑(きのとうし)に草創有となん。則拝し奉るも、古の御憂まで思ひやられて、看経おぼえず声やみて、只袖のうるほふより外の事なし。西行が「垂(しで)に涙の」と言ひけむも、かゝる折にや。等閑の事はいかゞ思ひ侍れど、たゞ敬神の心一筋にまかせて、 曇りなき跡を慕ひて我見るやたゞこれ西の秋の夜の月 浦風の吹上の秋の面影も波に立ち添ふ池の白菊 神や知る又生れても得ることのあらばと思ふ敷島の道 |
|
慶長3年(1598年)6月27日、石田三成は太宰府を訪れている。 |
|
廿七日には宰府へうつり給ふ。道すがら又みる所どもおほし。かるかやの関は名乗りとがむるさはりなし。四天寺の峰は此うへ也。天拝か岳も見わたし也。都府楼の瓦の色、観音寺の鐘のこゑ、いづれも菅丞相の名句にありとか。其所を尋ぬれば、都府楼は跡かたもなし。瓦の色はもとの土とや成りにけん。観音寺の鐘の響は昔にかはらずやあらん。 |
|
寛文3年(1664年)、西山宗因は豊前の小倉城主小笠原忠真の許に滞在、8月10日頃太宰府安楽寺に詣でた。 |
|
所のさま聞しにまさりて神さび心すめる靈地也。かたへは山につきてふかう入所也けり。並木の櫻、松の林、苺滑かなり。堂塔いらかをならべ宮人軒をつらねたり。樓門高くそびえて朱の玉垣かうがうしき御前に拜したてまつれば、さながら配所のむかしも見る心地してまのあたり御影いますかとおぼえて、泪もたえがたし。 |
|
貞亨2年(1685年)3月、大淀三千風は安楽寺天満宮を訪れている。 |
|
○人々此箱崎のうらを自負して。いかゞ風景はいづこかまされりといひしに。櫻川をうたひながら。 箱崎のふたみが浦の橋立の浪立ならぶ松しまの月。 かくて櫻月日。宰府の神津森に詣むと。修驗門。西河しもと(※「木」+「若」)を引導者にて行。みちすがら苅萱關。思川。染川。三笠森。四王寺。觀世音寺。十府樓。天智帝の舊都うちながめ。やがて宮寺に入り。内院安樂寺廟院といふ台宗。座主持。社僧五十房。社家八宇。一揖方拜のまはり魂をなし。宿坊検校(※共に手偏)坊に着。例の懐筆を染め法樂半軸を。
『日本行脚文集』(巻之四)
|

|
天保14年(1843年)10月12日、菊屋平兵衛が松尾芭蕉の百五十年忌にあたり、 |
|
の辞世より、芭蕉は、若いころに大宰府に参詣した事を記し、再度参拝の夢を持っていたとして、建碑したもの。芭蕉は連歌の先達、宗祇のように筑紫路への旅を夢みていたという。 |
|
昭和41年(1966年)6月14日、高浜年尾はに太宰府文書館にて俳句大会。 |
|
六月十四日 竹敷より壱岐中継にて板付へ 直ちに太 宰府文書館にて俳句大会 島の旅より帰り来て花菖蒲 紫は水に写らず花菖蒲
『句日記』(第二巻)
|

|
元禄9年(1696年)、広瀬惟然は安楽寺天満宮に詣でているようである。 |
|
つくし安楽寺に詣シころ 神法楽のよし これにしの梅のわらひや日の移リ |
|
元禄11年(1698年)7月22日、各務支考は太宰府天満宮に参詣。 |
|
この日宰府にいたる。久留米にありし時、日田の里仙きたる。是ら此地にいざなひ、この天滿宮に詣し(て)この時の風雅のまことをぞいのり奉りける。かくて連歌堂に宿してわがこゝろ猶あかず。曉の月に又詣し侍りて、俳諧の腸をかたむけ侍るに、機感たゞ胸にあつまりて、終に奉納の句なし。 |
|
元禄12年(1699年)9月、向井去来は長崎を出立。途中太宰府天満宮に参詣、句を奉納している。 |
|
宰府奉納 幾秋の白毛も神の光かな |
|
宝永2年(1705年)、魯九は長崎に旅立つ。帰途、太宰府天満宮を訪れている。 |
|
筑前 宰府天神宮にて むら紅葉檜皮をハしる夕日影 |
|
享保元年(1716年)5月24日、露川は門人燕説を伴い太宰府天満宮に参詣した。 |
|
折しも廿四日宰府の天神に詣す。森廣々として廣前物さびわたりて、有難さいふばかりなし。其夜は此地に宿す。 |
| 梅青し御袖こぼれて幾かへり | 居士 |
| 梅若葉拾へ詩の種哥のたね | 燕説 |

| 延喜5年(905年)、廟創建 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延喜19年(919年)、社殿建立。 |
|
明和8年(1771年)、蝶夢は桐雨と太宰府天満宮に参詣した。 |
|
かたへに針貫さしまはしたる梅の古木あり。社僧に問へば、名におえ(へ)る飛梅とこたふ。今も朽ながらみどりの珠をつらねて実をむすびたり 青梅や仰げば口に酢のたまる |
|
天明6年(1786年)8月24日、沂風と祥然は太宰府天満宮の祭礼見物に赴く。蝶酔・梅珠それに尺艾も同行して歌仙興行。『宰府日記』 天明6年(1786年)10月10日、田上菊舎は太宰府を訪れている。 |
|
宰府宿 とし頃願ひし詣叶ひ、ことさら今宵聖廟近きに舎り、こゝに残りし御言の葉も「都府楼纔に瓦の色を看せ観世音寺は唯鐘の声を聞と聞へさせ給ひしなど、人々の物語れる折しも、夜半を告るにも古への情頻りなるより |
| 窓に穿つ其鐘の音も月影も | 菊舎 |
『九州行』
|
|
天明8年(1788年)3月18日、長月庵若翁は太宰府天満宮に参詣して句を残している。 |
|
何事もなくて社頭の春の色
『誹諧曇華嚢』
|

|
寛政元年(1789年)に花臺坊を取次にして建立されたもので、境内中最古の句碑でもある。 |
|
宰府天満宮にて おもひでや桜の一葉を袖の上 |
|
慶応元年(1865年)2月、五卿(三条実美、三条西季知、東久世通禧、四条隆謌、壬生基修)は太宰府の延寿王院に入り、慶応3年(1867年)12月まで滞在した。緊迫の中にも武蔵寺や二日市温泉に憩いを求めた。 |
| 慶應元年(1865年)5月25日、坂本龍馬は太宰府で三条実美、東久世通禧等五卿に会う。 |
|
明治29年(1896年)9月、夏目漱石は夫人と北部九州旅行をして太宰府天神を訪れている。 |
|
太宰府天神 ◎反橋の小さく見ゆる芙蓉哉
9月25日(金)子規宛て書簡
|
|
明治43年(1910年)3月14日、河東碧梧桐は太宰府天満宮の梅林を逍遥した。 |
|
観音寺の国宝になっておる仏像の数々を見て、次で太宰府の盛りの梅の中を逍遥した。 |

|
太宰府天満宮の神域に句碑として立つ除幕式 樟の木千年さらにことしの若葉なり | 五月五日 |
水に横たわる樟の木、朱の橋、詣る |
禰宜を鶴としてわが言葉神に申さく |
若葉はすべて樟の、水音は滝と聞く |
| 昭和6年(1931年)12月27日、種田山頭火は大宰府参拝。
神苑に富安風生の句碑があった。  紅梅にたちて美し人の老 大正7年(1918年)、風生は福岡貯金支局長として赴任。 昭和18年(1943年)、高浜虚子の古稀賀筵で詠んだ句。
昭和54年(1979年)11月17日、建立。 全国で62番目の風生句碑である。 昭和54年(1979年)11月17日、建立。 昭和28年(1953年)、高野素十は太宰府を訪れている。
お石茶屋に吉井勇の歌碑があった。  大宰府のお石の茶屋に餅くへば旅の愁ひもいつか忘れむ 荻原井泉水書 韓国人の観光客が多かった。 2013年〜福 岡〜に戻る 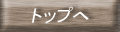 |