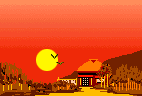
向島百花園〜御成座敷〜

|
文化元年(1804年)、百花園に集まる文人達の発案で隅田川七福神巡りが始まったそうだ。 隅田川七福神は多聞寺(毘沙門天)、白鬚神社(寿老神)、百花園(福禄寿)、長命寺(弁財天)、弘福寺(布袋尊)、三囲神社(恵比寿、大国神)の6箇所。 向島百花園は文化・文政時代、仙台出身の佐原鞠塢(きくう)によって開設された。 |
|
鞠塢から8代目の佐原滋元(しげもと)氏が百花園内で茶店「茶亭さはら」を営業している。 |



|
美知彦(みちひこ) |

|
梅年は江戸四谷の人。原田氏。通称幸次郎。雪中庵對山の門人。八世雪中庵を嗣ぐ。 |

|
永機は江戸の生まれ。穂積氏。通称は善之。別号老鼠堂。父六世其角堂鼠肝に俳諧を学び、其角堂七世を嗣承。 |
|
明治32年(1909年)、正岡子規は百花園を句に詠んでいる。 |
|
百花園 入口に七草植ゑぬ花屋敷
『俳句稿』(明治32年) |
|
大正14年(1925年)、高野素十は向島百花園の伝統行事「虫はなち会」に訪れている。 |
|
百華園蠹放ち 二句 かご燈籠さげて案内や蠹放ち 灯のかげの萩を攀ぢをりきりぎりす
『初鴉』 |
|
大正15年(1926年)5月28日、永井荷風は百花園に遊ぶ。 |
|
芍薬、うつ木、野薔薇の花今を盛りと咲き亂れたり。園主その祖鞠塢が自画像に文晁抱一の題句せし一舳、蜀山人題歌蠣潭画紅梅一幅。鵬齋の尺簡其他を示す。 |
|
昭和7年(1932年)9月15日、向島百花園において東京放送局主宰で中秋の観月会が催された。放送局文芸部長の久保田万太郎が観月会の「肝煎」で、歌の選者は与謝野晶子であった。 |
|
九月十五日。放送局主催中継放送句会。百花園。 ほつほつと屋根ぬれそめし月の雨 歌により句にこぞりたる雨月かな 月無しと極めて芙蓉の花に立つ |
|
九月十五日。句会の句会をラジオで放送するといふ日。 朝から曇りがちで、定刻、百花園に集つた頃はもうお話 にならない降りとなつてゐた。 |
|
昭和9年(1934年)2月4日、高浜虚子は武蔵野探勝会で雪の百花園へ。 |
|
三月節分の未明より降り出した雪は、東京を中心とした武蔵野における本年初めての大雪であつたが、当日は朝からの快晴、寔に恵まれたる雪晴の吟行日和である。向島の雪見といへば、江戸時代から明治にかけて、通人の間には最も風流な催とせられたものと承つて居るが、古老の方々には定めし思ひ出深きものがあらうと考へながら吾妻橋を渡る。
『武蔵野探勝』(雪の百花園) |
|
二月四日、武蔵野探勝会。向島百花園。 四阿の屋根に雪あり枯木中 下駄の雪はたけば杭の動くなり |
|
昭和20年(1945年)3月10日、東京大空襲により焼夷弾の直撃を受け、全園消失。 |
|
昭和32年(1957年)、石田波郷は向島百花園を訪れた。 |
|
久しぶりに百花園を訪ねた。昭和18年仲秋雨月、どしゃぶりでだれも来ない百花園芭蕉庵で友人2、3人と酒を飲んだ以来である。あの夜雨が上がった萩薄(はぎすすき)のくさむらに、園主の佐原さんが雪洞(ぼんぼり)をいくつも並べてくれた。なつかしい志だった。その芭蕉庵も、佐原さんも戦災で失われてしまった。私は雨月の宴後4、5日して大陸に召集され病む身となった。すでに穂の出はじめた薄やはしり咲の紅萩の見られる細道を歩いていると、歳月の思いしきりである。 |
|
今園内の草木百二、三十種、ほとんど昔日にかわらなくなっている。芭蕉庵もこの10月末にはほぼ原型通りに再建されるそうである。名物の萩のトンネルは、青萩が茂って天井部にややすき間がある程度、夕風が起こって萩薄に吹きわたると、さすがに秋の気配がする。8月20日ごろには虫はなち会がある。江戸庶民の愛してきた風雅の伝統が、ここにもはっきり残っている。出口の掲示板に、今、園内に咲いている花の名の木札がかかっていた。コモギギク、ムラサキツユクサ、マツヨイグサ、ハンゲショウ、オイランソウなど15枚。
『江東歳時記』(向島百花園) |

|
御成座敷には、かつて俳聖芭蕉の像が奉られていた「芭蕉の間」があるそうだ。 |
