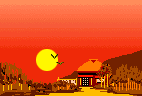下 町〜墨田区
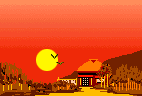
三囲神社〜其角の句碑〜
長命寺から隅田川沿いに歩いて三囲神社へ。

入口の石垣に歌が書いてあった。

いしがきの小石大石持合ひて御代もゆるがぬ松ケ枝の色
日比翁助(ひびおうすけ)は三越百貨店の創始者である。
三囲神社

御祭神は宇迦之御魂命。
隅田川七福神の起点で恵比寿と大黒天を祀る。
隅田川七福神は多聞寺(毘沙門天)、白鬚神社(寿老神)、百花園(福禄寿)、長命寺(弁財天)、弘福寺(布袋尊)、三囲神社(恵比寿、大国神)の6箇所。
小梅村田の中にあり。(故に田中稲荷とも云ふ。)別当は天台宗延命寺と号す。神像は弘法大師の作にして、同じ大師の勧請なりといへり。文和年間三井寺の源慶僧都再興す。慶長の頃迄は今の地より南の方にありしを、後この地に移せり。当社の内陣に英一蝶の描ける、牛若丸と弁慶が半身の図を掲けたり。
『五元集』
牛島みめぐりの神前にて、雨乞するものにかはりて、