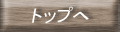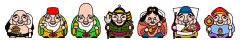
|
文化元年1月 廿一日 雪 帰雁見知ておれよ浮御堂 文化元年2月 廿五日 晴 北風吹 |
|
巣兆ノ婦人例ならぬとて、乙二、道彦とおなじく千住におもぶく。かへるさ穏(隠)坊の家をよ所に見なして、 |
|
わか草や誰身の上の夕けぶり わか草と見るもつらしや夕けぶり 廿六日 晴 月船と登東叡山 棒突も餅をうりけり山桜 御山はどこ上つても花の咲 文化元年3月 十三日 晴 南吹 穀雨三月中未一刻ニ入 中村二竹、古郷に赴けば、本郷追分迄おくる。 霞み行や二親持し小すげ笠 卅日 晴 一日も我家ほしさよ梅[の]花 文化元年4月 十一日 雨 午刻ヨリ晴 行々しどこが葛西の行留り 文化元年5月 十日 朝曇 晴 流山ニ入 夜雨 刀禰川は寝ても見ゆるぞ夏木立 十六日 午下刻雨 南風 小松菜の見事に生て蚊やり立 文化元年7月 二日 晴 富津ニ入 秋立や身はならはしのよ所[の]窓 おく露やことしの盆は上総山 七日 戌刻雨忽晴 我星は上総の空をうろつくか 木に鳴はやもめ烏か天川 大乗寺地獄画 秋の風劔の山を来る風か 秋の風我は(が)参るはどの地獄 文化元年8月 廿七日 村雨 流山ニ入 秋の夜や隣を始しらぬ人 廿八日 雨 越後節蔵に聞へて秋の雨 文化元年9月 一日 晴 亦洪水加三寸。根本といへる邑の圦樋より切込。 蕣(あさがほ)やたぢろぎもせず刀根の水 二日 晴 亦洪水加六寸。 |
|
水ハいよいよ増つゝ、川添の里人は手に汗を拳(にぎ)り、足を空にして立さハぐ。今切こミしほどの圦樋(いりひ)・彼堤とあはれ風聞に胸を冷して、家々のおどろき大方ならず。 |
|
魚どもの遊びありくや菊の花 夕月や流残りのきりぎりす 七日 晴 押つけ村に逝 |
| そのかみ天和の比(ころ)となん、鶴を殺して従類刑せられし其屍を埋し跡とて、念仏院といへる寺あり。二百年の後に聞さへ魂消るばかり也。況縁ある人においてお(を)や。 |
|
見ぬ世から秋のゆふべの榎哉 植足しの松さへ秋の夕哉 十五日 晴 布川祭 |
| 今夜は鶴殺しのたい夜なりとて、念仏院に其回向あれば、かいわい群集大かたならず。天和より四万三千日にあたるとなん。比(ころ)しも秋風寂々として小田の雁さへ昔おもはれてかなしく、我も念仏一遍のたむけなす員(かず)には入りぬ。 |
|
地内にて 君が世やかゝる木陰もばくち小屋 廿六日 雨 昼ヨリ晴 祗兵とゝもに、相生町見に行かへるさ両国茶店にて、 橋見へて暮かゝる也秋の空 廿九日 曇 元三大師御遷宮拝みに、祗兵同道して 末枯(うらがれ)やむごひ(い)直(値)踏の柱員(かず) 蓮[の]葉[の]青きも見へ(え)て初時雨 文化元年10月 十二日 晴 小金 翁会 布川二入 芭蕉忌に先つゝがなし菊の花 廿日 晴 江戸入 廿一日 晴 家財流山ヨリ来 見なじまぬ竹の夕やはつ時雨 寝始る其夜を竹の時雨哉 廿五日 雨 与雨十詣浅草観音 散木葉ことにゆふべや鳩の豆 木がらしの吹留りけり鳩に人 おく山茶店にて 初紅葉どれも榎のうしろ也 正統寺にて 散紅葉流ぬ水は翌のためか 文化元年11月 十四日 晴 はつ雪や竹の夕を独寝て 廿七日 晴 随斎会出席 はつ雪に白湯すゝりても我家哉 文化元年12月 九日 晴 布川元貞来 其寛来ル 来るも来るも下手鶯よ窓の梅 窓あれば下手鶯も来たりけり 廿一日 晴 油 立川通御成 梅がゝやどなたが来ても欠茶碗 廿五日 雨 野松来 夜丑刻雷 始雪 文化2年1月 一日 晴 心可と佃島住吉の旭おがみに行く。 年立や日の出を前の船の松 欠鍋も旭さす也是も春 十日 晴 文国宿 梅屋敷 只の木はのり出で立てり梅[の]花 十一日 晴 亀井天神宮 御桜御梅の花松の月 文化2年2月 三日 晴 道彦と上野へ登る 清水舞台にやすらふ 春の日[を]背筋にあてることし哉 八日 晴 霜 梅咲くや見るかげもなき己が家 黒門の半分見へ(え)て春の雨 十日 晴 禁足 梅咲くや見るかげもなき門に迄 廿九日 雨 其角百年忌 春の風草にも酒を呑すべし 文化2年5月 廿六日 晴 五月雨におつぴしげたる住居哉 宵々はきたない竹も螢哉 文化2年6月 一日 晴 浅草不二詣 背戸[の]不二青田の風を吹過る 文化2年8月 十五日 酉ノ刻陰る 戌刻雨 十五夜や田を三巡の神の雨 文化2年閏8月 十日 晴 布川ニ入 問屋仁左衛門の祈事アリ 鎌ヶ谷原 先の人も何も諷(うた)はぬ秋の原 文化2年10月 十二日 晴 馬橋ニ入 ばせを忌や丸こんにやくの名所にて 十五日 晴 棒島の罪人 其日流山ニ入 ちとの間は我宿めかすおこり炭 炭くだく手の淋しさよかぼそさよ 廿二日 雨 小金原 冬枯や親に放れし馬の顔 文化3年1月 廿三日 晴 徳満寺地蔵参詣 段々に朧よ月よこもり堂 文化3年3月 十三日 むら雨 南風吹 竹阿十七回忌 長応院に参る ○古き日を忘るゝなとや桜咲文化 文化3年4月 二日 晴 双樹と深川ニ入 かんこ鳥しなのゝ桜咲にけり 十三日 晴 布川ニ入 翠兄母悼 今からは桜一人よ窓の前 今しがた此世に出し蝉の鳴 文化3年5月 十九日 晴 勝山浄蓮寺ニ入 鯨見物 小盥(こだらい)も蓮(はちす)もひとつ夕べ哉 痩梅(やせうめ)のなりどしもなき我身哉 廿一日 晴 わざわざに蝶も来て舞ふ夏花(げばな)哉 文化3年6月 一日 晴 浦賀ニ渡 白毛黒クナル藥クルミヲスリツブシ毛ノ穴ニ入 涼風もけふ一日の御不二哉 二日 晴 夜雨 夕立の祈らぬ里にかかるなり 文化3年7月 蕣(あさがお)の下谷せましと咲にけり 朝顔や再生と秋を咲 廿四 晴 送野逸 大桜さらに風まけなかりけり 文化3年8月 十二日 大雨 気に入らぬ家も三とせの月よ哉 文化3年9月 9日 九 晴 与二野逸一到二金町一記 杭に来て鷺秋と思ふ哉 文化3年10月 赤子からうけならはすや夜の露 文化4年1月 一日 晴 はつ春やけぶり立るも世間むき 元日も爰(ここ)らは江戸の田舎哉 沙汰なしに春は立けり草屋敷 二日 晴 鶯にかさい訛はなかりけり 文化4年2月 十七日 晴 随[斎]会 影ぼふし我にとなりし蛙哉 木母寺の夜を見に行春の雨 文化4年3月 一日 晴 曇 此日花御堂作るとて道に童ども銭をとる 流山ニ入 小金原 雉なくやきのふ焼れし千代の松 よるハとしや野べは鳥鳴桜咲 廿一日 晴 双樹と方々遊参。湯島円満寺木食寺也。補陀殿ト有。イゝ蔵横丁天満宮、牛天神、波切不動、法化(華)山伏、小石川伝通院。 藪の蜂来ん世も我にあやかるな 文化4年5月 廿七日 晴 成美会止ム 於十時庵恒丸会有 此月に扇かぶつて寝たりけり 文化4年10月 十二日 晴 小金ニ入 ばせを忌や時雨所の御コンニヤク 文化4年11月 十四日 晴 南原にて可候に別る 雪の山見ぬ日となれば別哉 文化5年2月 三日 晴 木母寺は暮ても雉の鳴にけり 文化5年3月 廿七日 巳刻より晴 木母寺は夜さへ見ゆる時鳥 文化5年4月 八日 晴 松井と灌仏参 藤棚もけふに逢けり花御堂 十八日 晴 蚊の出て空うつくしき夜也けり 古わらぢ螢[と]ならば角田川 |
|
文化5年6月 十四日、晴 熱田明神の祭有、千住秋香庵中飯。小菅村水戸橋ふしん、舟渡し。新宿より高須村といふ所に堤有、去卯六月三日洪水に破れて、新堤によし簀引はりて餅など売有。足を休。 六月や草も時めくわらじ(ぢ)茶屋 文化5年12月 十五[日] 晴 板橋山城屋 雪雹(ひさめ)うしろ追うれて六十里 |
|
文化6年1月 一日 寅刻ヨリ辰刻迄晴天 不二南吹 巳刻霰 午刻晴大風 |
|
思旧巣 梅さくや寝馴し春も丸五年 |
|
十日 晴 木母寺の明り先より帰ル雁 |
|
文化6年2月 五[日] 晴 死下手の此身にかゝる桜哉 |
|
文化6年5月 十四日 晴 身の上の鐘と志りつつ夕涼 文化6年5月 一日 申八刻雨 寒 浅見参 涼風はどこの余りかせどの不二 不二の草さして涼しくなかりけり マタグ程の不二へも行かぬことし哉 蟷螂が不二の麓にかゝる哉 |
|
文化3年 九月九日、空寒からず熱からず、すゝむ足おのづから軽く、心の霧も晴るゝ心ちして先小梅堤にかゝる。刈れる小田有、いまだ刈らざる有。作らぬ菊も折しり顔にさきて、さすがに暮秋のおぼぶきを残す。 風吹いてそれから雁の鳴にけり 同行もおなじ優婆塞にて八十の叟なれば、物のわきまへも一かたならず。秋の草木のあはれをもたゞにや見過すべき。我は常々行かふ道にしあれど、けふは格別の風情を添ふ たやすくも菊の咲たる川辺哉 午刻ばかりに金町に至る。爰の祭りは必ことざまのてぶりもやあらんと、久しくより心にかけて、漸ことし見る日を得るはけふ也けりと、老ほこりにほこり来ぬるに、さはなくて世間にありふるゝ操狂言といふものにぞありける。二人は興ざめて、ふたゝび見るべくもあらず。只松の小陰によりて、痩脛の疲れをさする。 草花に汁鍋けぶる祭哉 秋の日の袖に傾けば、かへる期のせかれて、もと来し道をいそぐ。 日短かは蜻蛉の身にも有にけり 又人にかけ抜れけり秋の暮 灯のとぼる家、とぼらざる家のあちこち見ゆる比(ころ)、庵にかへる。 雁下りてついと夜に入る小家哉 文化4年8月 渋村、わく(たカ)や市左衛門に舎る。かねて約束なれば、先、湖光、完枝に逢て歌仙などす。 即興 せい出して山湯のけぶる野分哉 小男鹿の水鼻ぬぐふ紅葉哉 文化6年1月 夜酉の刻の比(ころ)、火もとは左内町とかや、折から風はげしく、烟(けぶり)四方にひろがりて、三ヶ日のはれに改たる蔀畳のたぐひ、千代をこめて餝(かざり)なせる松竹にいたる迄、皆一時の灰塵(燼)とはなれりけり。されば人に家取られしおのれも、火に栖焼れし人も、ともにこの世の有さまなるべし。 元日や我のみならぬ巣なし鳥 礎や元日しまの巣なし鳥 家なしの此実も春に逢ふ日哉 随斎のもとにありて乞食客 一茶述 文化6年2月 |
| 二月八日 於葛斎会 |
||
| 正月はくやしく過ぬ春の風 | 一茶 |
|
| 猫鳥鳴ておぼろ始る | 恒丸 |
|
文化6年3月 東岸寺藤勧進 藤棚やうしろ明りの草の花 |