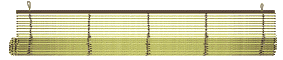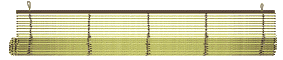2006年〜下 町〜
伝通院〜於大の方〜
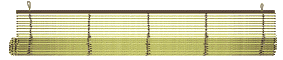
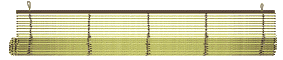
春日通り(国道254号)伝通院前から伝通院(HP)へ。

伝通院本堂

正式には無量山傳通院寿経寺。
浄土宗の寺院で、関東十八檀林のひとつ。
応永22年(1415年)、浄土宗第七祖了誉聖冏上人無量山寿経寺という名で開創。
徳川家康の生母於大の方の菩提寺。於大の方の法名「傳通院殿蓉誉光岳智香大禅定尼」にちなんで院号を伝通院とした。
1ヶ月前に来た時はまだ桜も咲いていなかったが、今は新緑。
本堂の階段両脇で躑躅が盛りである。
まだ牡丹の花が咲いていた。

文化4年(1809年)3月21日、小林一茶は秋元双樹と小石川伝通院を参詣している。
廿一日 晴 双樹と方々遊参。湯島円満寺木食寺也。補陀殿ト有。イゝ蔵横丁天満宮、牛天神、波切不動、法化(華)山伏、小石川伝通院。
藪の蜂来ん世も我にあやかるな
大慈寺、善心寺、神齢山護国寺、観音開帳山開き。
『文化句帖』(文化4年3月)
於大の方の墓の前には卯の花が咲いていた。

伝通院には於大の方を始めとして多くの著名人が埋葬されている。
小泉千樫の墓があった。

明治19年−昭和2年(1886−1927)名は幾太郎。号は椎南荘主人、樫老人など。千葉県生まれ。正岡子規を中心とする根岸派に親しみ、子規の没後、伊藤左千夫に師事して「アララギ派」の有力な歌人となる。のちに「青垣会」を結成し、後進の育成に当る。門下生には三ヶ島葭子、松倉米吉などがいる。
主著として「川のほとり」、その他自選歌集がある。
平成元年3月 東京都文京区教育委員会
また伝通院は夏目漱石の『それから』や『こころ』に出てくる寺である。
ある日私はまあ宅(うち)だけでも探してみようかというそぞろ心から、散歩がてらに本郷台を西へ下りて小石川の坂を真直に伝通院の方へ上がりました。
電車の通路になってから、あそこいらの様子がまるで違ってしまいましたが、その頃は左手が砲兵工廠の土塀で、右は原とも丘ともつかない空地(くうち)に草が一面に生えていたものです。私はその草の中に立って、何心なく向うの崖を眺めました。今でも悪い景色ではありませんが、その頃はまたずっとあの西側の趣が違っていました。
『こころ』(下・10)
昭和3年(1928年)11月4日、牧水七七忌に伝通院で追悼会が東京創作社主催で行われた。
昭和15年(1940年)の牧水十三回忌も伝通院で営まれたそうだ。
慈眼院へ。
2006年〜下 町〜に戻る