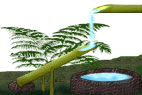下 町〜文京区〜
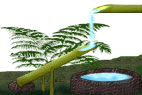
追分一里塚跡〜小林一茶〜
東京メトロ南北線東大前を出て言問い通りに向かうと、本郷通りと国道17号の分岐点がある。

日光御成道(旧岩槻街道)と中山道との分かれ道「本郷追分」である。
追分一里塚跡

追分一里塚跡(区指定史跡)
一里塚は、江戸時代、日本橋を起点として、街道筋に1里(約4km)ごとに設けられた塚である。駄賃の目安、道程の目印、休息の場として、旅人に多くの便宜を与えてきた。
ここは日光御成道(旧岩槻街道)との分かれ道で、中山道の最初の一里塚があった。18世紀中ごろまで、榎が植えられていた。度々の災害と道路の拡張によって、昔の面影をとどめるものはない。分かれ道にあるので、追分一里塚とも呼ばれてきた。
ここにある高崎屋は、江戸時代から続く酒屋で、両替商も兼ね「現金安売り」で繁昌した。
中山道分間延繪圖による(文化年間1804〜1817)

−郷土愛をはぐくむ文化財−
文京区教育委員会
森鴎外の小説『青年』冒頭で、「小泉純一」が歩いた道である。
小泉純一は芝日蔭町の宿屋を出て、東京方眼図を片手に人にうるさく問うて、新橋停留場(ていりゅうば)から上野行の電車に乗った。目まぐるしい須田町の乗換も無事に済んだ。さて本郷三丁目で電車を降りて、追分から高等学校に附いて右に曲がって、根津権現の表坂上にある袖浦館という下宿屋の前に到着したのは、十月二十何日かの午前八時であった。
森鴎外『青年』
文化元年(1804年)3月13日、小林一茶は故郷の柏原に帰る中村二竹を本郷追分まで送った。
十三日 晴 南吹 穀雨三月中未一刻ニ入
中村二竹、古郷に赴けば、本郷追分迄おくる。
中村二竹は一茶の門弟。中村太三郎。信州柏原の酒屋桂屋与右衛門の長男。
家を弟に譲り俳人となる。漂泊に身をまかせ、行方不明のまま客死したそうだ。
下 町〜文京区〜に戻る