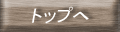赤間神宮〜碑巡り〜


|
建久2年(1191年)、安徳天皇の御霊を慰めるため、阿弥陀寺に御影堂を建立。 |
|
文明12年(1480年)9月10日、宗祇は筑紫の旅の途中で阿弥陀寺に泊まった。 |
|
かくて赤間関早鞆の渡りに至る。塩の往き交ひ矢の如くして、音に聞しにかはらず。二の迫門(せと)を隔て向ひは豊前の国なり。そのあい(ひ)だ十余町と見ゆ。此地の宿りは阿弥陀寺と言へり。 |


|
天正15年3月太閤秀吉は、安徳天皇廟前に先帝御影を拝して献詠。是より先大阪の築城に全国より礎石を集めしむ。即ち肥前国竜造寺隆信、弐百余の石を献ぜむと海峡に至るや関門の急潮に逡巡。日ならず、城既に成るを聞き是を海中に投じて去れりと。潮音星霜380歳、昭和42年12月運輸省第4港湾建設局是を引揚げ赤間神宮に献ぜらる。以て往古の秀吉が志を蘇らしめむと石組を図るや、市民崇敬会奉賛し□宮神鎮の磐境竣成す。 昭和47年10月 |
|
慶長3年(1598年)6月14日、石田三成は九州下向の際阿弥陀寺を訪れているようである。 |
|
十三日の朝、一里ばかりを過ぎて、又舟にて関門(セキノト)へ着き給ひぬ。あくる日もここにとどまり給へり。阿弥陀寺と云ふ寺に、平家の一類入水の所のしるしとて、其御影ども堂にあり。安徳天皇の尊形は木像にて、八歳の御わらはすがた、まことにさりぬべきさまなり。さきざき一見の人々の短冊どもあり。其人まなにはあらねど、心のうちの手向ぐさに、 沈みけんよはひ八重のしほあひの浪は昔にかへる袖かな |
|
昭和13年(1938年)7月、山口誓子は赤間神宮に詣で平家一族の墓を弔った。 |
|
私はそこから電車でひき返して赤間宮に詣で、木下闇に平家一族の墓をとむらうた。 宮居は海峡を見下ろしてゐるので、石段を詣でさがつて来ると、鳥居の中に、また民家の屋根の上に青潮がたうたうと流れてゐた。はやい速力で鉄船が通り過ぎた。
『東京日日新聞』(昭和13年7月27日) |
|
昭和45年(1970年)7月、山口誓子は赤間神宮に詣で、朱の楼門を見た。 |
|
赤間神宮 龍宮の門南風を奉る
『不動』 |
|
寛永10年(1633年)10月、西山宗因は熊本から上京の途中、阿弥陀寺を訪れている。 |
|
あるじのをのこにつれて、そのわたりの海のほとりを見ありきて、阿弥陀寺といふ山寺にまかりぬ。そこに平相国の一門、知盛下の公卿上臈、女房、入水のすがたを、左右の障子に写し、 帝の玉体を木像にあらはしたるをふし拝み奉る。いたましきかな、玉楼金殿の内にあふがれ給て、かゝる遠国波島の渚にあとをのこし給ふことよ。
「肥後道記」 |
|
寛文5年(1665年)3月8日、西山宗因は豊前小倉から下関に渡る。9日、阿彌陀寺を訪れた。 |
|
時ハやよひの八日日暮かたに赤間関にをしわたる。九日風あしけれはおなし所にあり。日もなかくつれづれなれは、阿彌陀寺という山寺に寿永の帝入水の玉躰并に平氏の公卿上臈女房の畫図ありときゝてまうてゝおかむ。おりしも花のちるをみて 世にうみにしつむむかしの面影を花にのこして吹あらし哉 誹諧即興 やれ嵐南無阿弥陀寺の花盛
『西国道日記』 |
|
貞亨元年(1684年)6月、大淀三千風は阿弥陀寺を訪れている。 |
|
又の日をのをの袖ひきあひて。かの平氏入水のむかしをなんとて。松壽山阿彌陀寺にまうでし。うす墨の松のひまより見れば。筆海文島畫軸をのべ。彩雲彫岩仙閣を見る。やゝこなたにむきて。安徳天皇御影堂。まだいはけなきおほん像。其外供奉の一門かぎりのすがたを。古法眼が筆にとゞめたり。むかしを今のあはれさ。泪もさらにとゞめがたし。 |

|
『諸国翁墳記』に「月花塚 暫くは花の上なる月夜可南 長州赤間関連中建之」とある。 |
|
元禄11年(1698年)9月7日、各務支考は西国旅行の帰路、阿弥陀寺を訪れている。 |
|
阿彌陀寺といふ寺は、天皇・二位どのゝ御影より一門の畫像をかきつらねて、次の一間は西海漂泊のありさま、入水の名殘に筆をとゞめたりと、この寺の僧の繪とき申されしが、折ふし秋の夕の物がなしきに、人はづかしき泪も落ぬべき也。 屏風にも見しか此繪は秋のくれ |

|
寿永4年(1185年)3月24日、源平壇ノ浦合戦に入水せられた御年8歳のなる御幼帝をまつる天皇社にして下関の古名なる赤間関に因みて赤間神宮と宣下せらる。 |


|
その昔、この阿弥陀寺(現・赤間神宮)に芳一という琵琶法師あり。 夜毎に平家の亡霊来り。いづくともなく芳一を誘い出でけるを、ある夜番僧これを見、あと追いければ、やがて行く程に平家一門の墓前に端座し、一心不乱に壇ノ浦の秘曲を弾奏す。あたりはと見れば数知れぬ鬼火の飛び往うあり。その状芳一はこの世の人とも思えぬ凄惨な形相なり。さすがの番僧慄然として和尚に告ぐれば一山たちまち驚き、こは平家の怨霊芳一を誘いて八裂きにせんとはするぞ、とて自ら芳一の顔手足に般若心経を書きつけけるほどに、不思議やその夜半、亡霊の亦来りて芳一の名を呼べども答えず見れども姿なし。暗夜に見えたるは只両耳のみ、遂に取り去って何処ともなく消え失せにけるとぞ。 是より人呼んで耳なし芳一とは謂うなり。 |

|
宝永2年(1705年)、魯九は長崎に旅立つ。帰途、平家一門の墓所に詣でている。 |
|
平家の人々の墓所に詣てゝ 御一門昔となたの花すゝき |
|
明和8年(1771年)5月、蝶夢は阿弥陀寺を訪れている。 |
|
阿弥陀寺といふ寺に先帝の宸影よりはじめ、一門の画像を安置す。卵塔かずかず見えてあぢきなし。 |
|
文化2年(1805年)10月17日、大田南畝は阿弥陀寺を訪れて安徳天皇の木像を拝見する。 |
|
海上三里ばかりにして下の關につく。午の時ばかりなるべし。やどりにいらずして阿彌陀寺にゆかんとて、西南部(ナベ)町より右に曲り、東南部町を過て左に門あり。聖衆山の額をかく筆者未詳唯山の印あり右の山に八幡宮あり。左の門をいりて堂あり。秘密塲といふ額あり。左にならびたてる堂にいりて、安徳天皇の御木像を拜す。 |
|
昭和3年(1928年)10月、高浜虚子は赤間神宮に参拝している。 |
|
七盛の墓包み降る椎の露 昭和三年十月 赤間宮参拝。 |
|
昭和4年(1929年)6月16日、高浜虚子は赤間神宮に詣でる。 |
|
六月十六日。下関著。赤間宮に詣る。 七盛の墓を包みて椎の露 |

|
昭和30年(1955年)10月、安徳天皇崩御七百七十年に「ホトトギス」下関同人建立。 |
|
昭和3年に来宮、七盛塚を覆うほどに茂る椎の木を見て詠める句。その後戦災でこの木は焼失。昭和30年に虚子は再度来宮、その句を筆でしたためていただき、石碑にしたものである。 |
|
下関市阿弥陀寺町赤間神宮境内に、平家の戦歿者を祀った遺跡があり、これを七盛塚という。昭和三十年十月、安徳天皇崩御七百七十年に当るというので、この塚の前方に虚子翁の右句碑が建てられた。高さ約五尺六寸、幅二尺の自然石に刻む。 |
|
昭和33年(1958年)4月29日、虚子は三度赤間神宮を訪れている。 |
|
下關、赤間神宮。宮司の先導で參拜。七盛の塚。嘗つてあつた椎の大木は、隣の春帆樓が戰災を受けた際、類燒。 七盛の墓包み降る椎の露 虚子 といふ舊作も昔となつた。 從來娼妓によつて行はれることによつて有名であつた先帝祭は今年はカフエーの女で行はれた。衣裳、鬘等從前通り、外八文字も上手に踏んだとの事。 |
|
昭和40年(1965年)、山口誓子は赤間神宮に虚子の句碑を訪ねている。 |
|
門司の和布刈神社へ私は行ったことがない。 対岸の下関は知っている。春帆楼に泊ったこともある。赤間神宮へ行って平家一門の墓を弔い、そこに立っている虚子の句碑 七盛の墓包み降る椎の露 も見た。「七盛」は、「盛」の字のつく平家の人々だが、「平家物語」には、教盛、経盛、資盛、有盛、行盛と知盛、一盛足りない。 「七盛塚」の標示には、行盛を加えず、清経、教経を入れて、「七盛」とする。標示に偽りあり。 私の祖先の時忠は生捕りになった。
『句碑をたずねて』(四国・九州路) |
|
昭和49年(1974年)11月4日、高浜年尾は赤間宮へ。 |
|
同日 九州同人会 平尾台マルワランドより和布刈神 社、関門橋、赤間宮、山口銀行四階 岬宮の末社は一社石蕗盛り 七盛の墳やうつろに秋深し |