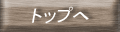唐招提寺~碑巡り~



|
それより招提寺にいりぬ。此間久しく開帳ありて、けふを限りなるよし聞ゆ。まうでくる人多し。門の額は唐招提寺とかけり。孝謙帝の宸翰なり。講堂の内、開帳の書画霊宝品々あげてかぞふべからず。此比取出して人に見する品々を目録一巻としてうる。諸堂の内見つくしてのち、寺門を出づ。凡此寺は聖武の御時、唐僧鑑真和尚創立せり。今に至て星霜をふる事九百七十九年、幸にして一度も回禄の災にあはず、諸堂皆創立のまゝなり。世に類なき古代の梵刹也。 |

|
おほてらの まろきはしらの つきかけを つちにふみつつ ものをこそ おもへ |
|
「つきかげ」 上代の歌には「月光」を「つきかげ」と詠みたる例多きも、作者は、この歌にては、月によりて生じたる陰影の意味にて之を歌ひたり。作者自身も「光」の意味にて「かげ」を用ゐたる四五首ありて、別にこれらをこの集中に録しおけり。人もし言語を駆使するに、最古の用例以外に従ふべからずとせば、これ恰も最近の用例以外に従ふべからずとするとに等しく、共に化石の陋見と称すべし。 |
|
木立の深い裏門かた小径をぬけて私たちは金堂の脇へ出た。宵闇はすでに濃く、秋草同人の歌碑もさだかでない。 おほてらのまろきはしらのつきかげをつちにふみつつものこそおもへ 秋草同人 この「つきかげをつちにふみつつ」の一節がことに好きである。私は一人金堂へ石段をのぼり、その丸い柱の一つに背をよせた。かうして背をもたせるにはこの柱はなんといふよい丸みをもつてゐるのであらう。どう向きをかへても太い柱は快く安定して背を支へてくれる。日ごろの何といふことなしの不安感も爪先から大地へぬけてゆくやうな気がする。
「唐招提寺」 |

|
唐招提寺 なく雲雀松風立ちて落ちにけむ 再び唐招提寺 蟇ないて唐招提寺春いづこ
『葛飾』 |
|
この句もその場で詠んだものではない。 唐招提寺の金堂を出て、附近を散歩していると、木の芽がようやくひらいて、若葉になりかけた時季で、簷(ひさし)の下がほのかに染まっているようである。美しいなと思って眺めていたら、ごこかで蟇の鳴く声がきこえた。おそらく菖蒲の萌えはじめた池にいるのだろう。蟇はきらいなものの一つで、その声も不気味なのだが、この時はさほどうとましいものとは思わなかった。
『水原秋櫻子自選自解句集』 |

|
開山堂なる鑑真の像に とこしへ に ねむりて おほせ おほてら の いま の すがた に うちなかむ よ は |

|
俳人松尾芭蕉が貞享5年(1688年)陰暦4月8日当寺に詣で鑑真和上を拝しての句。 |
|
『諸国翁墳記』に「若葉塚 南都招提寺境内 □□山社中 靑々・万鬼・兎月・□□」とある。 |
| 昭和3年(1938年)10月、会津八一は唐招提寺を訪れる。 |
|
唐招提寺にて せきばく と ひ は せうだい の こんだう の のき の くま くれ わたり ゆく |
|
昭和4年(1929年)4月2日、高浜虚子は星野立子を連れて唐招提寺へ。 |
|
四月二日。奈良見物。東大寺、唐招提寺、薬師寺等一巡。 鹿のゐる馬酔木の奈良に来りけり |
|
翌朝、比古、三千女、洛水の三人が早く来られて、五 人で自動車の廻れるだけ奈良を見物する。まづ東大寺、 それから西大寺に行く。一本の枝垂桜が美しい蕾をいつ ぱいにつけて境内にあつた。唐招提寺は金堂に向つて左 手の方に池があつたやうにおぼえてゐる。 金堂のほとりの水に菖蒲の芽 |
|
昭和5年(1930年)2月末、北原白秋は南満州鉄道の招きにより中国東北部を旅行。4月8日、妻子と奈良を回っている。 |
|
昭和5年(1930年)5月6日、荻原井泉水は唐招提寺で芭蕉の句碑を見ている。 |
|
金堂の後ろに講堂がある。礼堂に続いて舎利殿がある。その間を行くと――道は砂地で、雨を吸ってすがすがしい――後ろの丘に掛けて一むらの若葉がこんもりと茂っている中に小さな堂がある。開山上人の堂である。正面の石段の前、梅の若葉の蔽うている中に、一基の句碑がある。 若葉して御目の雫ぬぐはばや 芭蕉
『随筆芭蕉』(奈良の若葉) |
|
昭和10年(1935年)、水原秋桜子は唐招提寺を訪れている。 |
|
唐招提寺 蕨萌えわづかの築地のこりたる
『秋苑』 |
|
昭和14年(1939年)9月30日、星野立子は唐招提寺で居待月を見る。 |
|
秋の夕方の若草山はおだやかに眺められた。彼岸花の 太い茎に夕日が当つて色が染つてゐるやうに見える。蚊 がどんどん増して来る。今宵は居待月である。坂を登つ たり下りたり、あちこち歩きながら月の出を待つ。どん どん暗くなつて来る。遠くから畦道を来る自転車の灯が まつ赤に見えて来る。美しい月が出る。 唐招提寺。 わが影の築地にひたと居待月
「続玉藻俳話」 |

|
『黒檜』(昭和15年8月13日、八雲書林刊)に収録されている歌である。「四度、鑑真和上を憶ふ」とある。 |
|
昭和27年(1952年)6月6日、阿波野青畝は鑑真忌に参詣している。 |
|
蟻地獄聖はめしひたまひけり
『紅葉の賀』 |
|
六月六日が鑑真忌、西の京唐招提寺という古寺は、天平時代に開山された唐僧の和上を供養して、特にこの一日だけ参詣者に有名な木造が公開される。 今は一条院の建物を移して安置しているが、この句の当時は「若葉しておん目の雫ぬぐはばや」の芭蕉句碑が立つ小さい堂にしずかに納まり、目をつむっておられたのである。それからまた東の隅にあたる林の中に和上の墳墓もあるので、必ずそこにも詣る。 ここには蟻もいるし、また蟻地獄が擂り鉢を掘っていた。素十の「蟻地獄松風を聞くばかりなり」を想い出す松風の音がよくきこえるところである。日本へ渡海するためにたびたび難破し、盲になり、それでも意をひるがえさなかった鑑真和上は、実に優しく親しめるような木像の慈顔を拝してみると、ひじりである。生けるひじりとかわらぬ感じだった。 |
|
昭和28年(1953年)、水原秋桜子は唐招提寺を訪れている。 |
|
唐招提寺 冬紅葉校倉寂びて暮れゆけり 短日の靄に金堂のうかぶのみ
『帰心』 |
|
昭和34年(1959年)8月10日、高野素十は唐招提寺の観月讚仏会に参加。 |
|
唐招提寺観月 月明の手のひら萩の一枝のせ
『芹』 |
|
昭和35年(1960年)、山口誓子は唐招提寺を訪れた。 |
|
唐招提寺 永き日を千の手載せる握る垂らす 開山忌盲(めしい)鑑眞起ちて出づ
『方位』 |
|
昭和35年(1960年)、山口誓子は唐招提寺の観月讚仏会に参加。 |
|
唐招提寺觀月 月の夜に開扉三處の三體佛 指さきにざらざらの香月に燻ぶ 奈良の月山出て寺の上に來る
『青銅』 |
|
昭和40年(1965年)6月、山口誓子は唐招提寺で芭蕉の句碑を見ている。 |
|
金堂を右手に廻って講堂と札堂の間を行くと、自然に開山堂に達する。その石階の左裾に芭蕉の句碑がある。自然石。 若葉して御目の雫拭ばや 「芳野紀行」には、「招提寺鑑真和尚来朝の時、船中七十余度の難をしのぎたまひ、御目のうち塩風吹入て、終に御目盲させ給ふ尊像を拝して」とあって、この句を掲げている。 「若葉して」が問題だ。私はそれを「若葉を以て」と解して句意を通らしめる。「若葉になって」ではどうにも句意が通らない。 建立は文政四年。
『句碑をたずねて』(大和路) |
|
昭和42年(1967年)4月9日、高野素十は唐招提寺に吟行。 |
|
同九日 芹吟行 唐招提寺 もろもろの御仏花に拝まばや 御仏を讃ふる経を花に誦す
『芹』 |
|
昭和45年(1970年)9月15日、水原秋桜子は唐招提寺の讃佛会に訪れている。 |
|
六時に門が開かれ、ここで大島君はじめ民郎研究会の人々、それに黒木君、羽田君にあう。門内に入ると向こうさがりにやや低く見える金堂が開け放たれ、照明によって諸佛が光りかがやいている。そこまでの左右にはいくつかの紙燭がおかれ、想像以上に好い情趣だと感心した。
「長崎と島原」 |