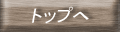鴫立庵〜碑巡り〜

|
寛文4年(1664年)、小田原の崇雪がこの地に五智如来像を運び、西行寺を作る目的で草庵を結んだのが始まりで、元禄8年(1695年)俳人の大淀三千風が入庵し鴫立庵と名付け、第一世庵主となりました。 現在では、京都の落柿舎、滋賀の無名庵とともに日本三大俳諧道場の一つといわれています。 崇雪が草庵を結んだ時に鴫立沢の標石を建てたが、その標石に「著盡湘南清絶地」と刻まれていることから、湘南発祥の地として注目を浴びています。 |

|
大正7年(1918年)11月から11月まで荻原井泉水は大磯に仮寓。それから13、4年後、鴫立庵を訪ねている。 |
|
其徑には左側から老松が枝を垂れかけてゐる。それが鴫立庵の松なのである。鴫立庵は正しく云ふと、大磯と小磯との境なる小流を越えて、小磯の方にある。
「大磯の春 ――鴫立庵を尋ねて――」 |

| 第一世庵主 大淀三千風 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 第二世庵主 大本朱人句碑 |

| 鴫きゝて名月そなるなほあハれ | 三千風居士遺章 |
||||||||||||||||||||||||
| ちり塚にもろしや花の菜大根 | 朱人居士遺吟 |
|
人しれぬ秘藏娘や華葵 |


|
戸田茂睡[1629〜1706]は歌学者・歌人。駿河の人。名は恭光(やすみつ)。通称、茂右衛門。号、梨本(なしのもと)・隠家。岡崎藩本多氏に仕えたが、のち江戸浅草に隠棲。 |

|
大淀三千風の建てたもので、堂内には西行法師坐像が安置されているそうだ。 |

| はこねこす人もあるらしけさの雪 |
|||||||||||||||||
| 春たちてまだ九日の野山哉 |
|||||||||||||||||
| みのむしの音を聞に来よ草の庵 |
|||||||||||||||||
| 日のみちや葵かたむく皐月雨 |

| 鴫立し沢辺の菴をふきかえて |
|||||||||||||
| こゝろなき身のおもひ出にせん |
|||||||||||||
| 鴫たつてなきものを何よぶことり |


|
百明房得らひたり昨烏歎書 |
|
明和8年(1771年)4月23日、諸九尼は鴫立庵を訪れている。 |
|
廿三日 大磯にいたり、鴫たつ沢の庵を音信けれど、あるじは留守なりければほゐ(い)なくて、 鴫の声なくてうらやミ麦の秋 かく書付て立出けるに、やがて帰たりとて、人して呼とめられて、また立帰りぬ。西行上人の像を拝ミ、鳥酔老人の塚などとぶらひぬ。松の嵐、磯うつ波の音、何となく物悲しく、心なき身にも哀ぞ添ぬる。 |

|
安永9年(1780年)4月17日、蝶夢は江戸からの帰途、鴫立庵を訪れている。 |
|
固瀬(カタセ)川・唐が原を過て、藤沢寺に参る。馬入河をこして、大磯の虎の石を見る。鴫立沢の庵によるに、いほぬしは、他国に行てあはず。 |
|
天明8年(1788年)4月18日、蝶夢は再び鴫立庵を訪れた。 |
|
平塚・大磯、和泉屋に泊。鴫立沢の庵主問ふ。 うき草の旅や流れのはなごゝろ と一句を残し帰らんとするに、庵主、脇を付て留らるゝを、 大磯の小磯の浦のうら風に 引ともしらずかへる袖哉 と旅宿にやどる。 |


|
寛政7年(1795年)2月、西上人六百遠忌正当法要。『衣更着集』(葛三編)刊。 |
|
文化3年(1806年)7月4日、菜窓菜英は鴫立庵を訪れたが、庵主葛三は留守。 |
|
庵主葛三は行脚の畄守とて暮玖と言 根方尺布の伯父なん人にまミへ(え)、す(し)はらくの もの語して、宿の案内も老か身すから なしくれ、心あり氣なる家に泊る。 こゆるきや旅の柱の一葉舟 |
|
文化5年(1808年)、多賀庵玄蛙は鴫立庵を訪れ5日滞在している。 |
|
鴫立沢に杖を留る事五日 旅の日は鴨の脛にも似たりけり |