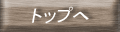大悲閣(千光寺)〜碑巡り〜

|
昭和12年(1937年)9月、コロムビアレコードから「進軍の歌」のB面として「露営の歌」が発売された。籔内喜一郎作詞、古関裕而作曲。 |

|
十一月十二日
訪愚庵鐵眼禅師于靈山下。與虚子遊嵐山舟遊詣大悲閣。虚子同宿。 松の木は現れにけりむら紅葉
「獺祭書屋日記」 |
|
明治二十五年の十一月に、私は子規と嵐山に舟遊したことがあるが、其時、舟を下りて大悲閣登つたかどうかはつきりした記憶が無いのである。がたゞ子規が、「花の山二丁登れば大悲閣」といふ、芭蕉の句のあることなどを話題に上せたかと思ふ。この句は、その芭蕉の句の二丁とある距離を訂正したやうな物であつて、なかなか二丁どころではない、木下闇を縫うて大悲閣まで登つて見たが八丁もあつたらうか、といふのである。大悲閣は私も訪ねたことがあつて角倉了以の木像の眼が光つてをつたことを覺えて居る。
高浜虚子『子規句解』 |
|
下闇や八丁奥に大悲閣
『寒山落木 巻二』(明治二十六年 夏) |

|
「だいひかく」 大悲閣。渡月橋より戸灘瀬滝を経て、石径を登ること二〇〇メートル。 黄檗宗千光寺なり。眺望よろし。 |
|
正しくは、嵐山大悲閣千光寺と号する禅宗の寺である。 慶長19年(1614年)、角倉了以によって、二尊院の僧、道空了椿を中興開山に請じて建立された。了以は、我が国の民間貿易の創始者として、南方諸国(主にベトナム)と交易し、海外文化の輸入に功績を挙げた人物で、国内においては、保津川、富士川、天龍川、高瀬川等の大小河川を開削し、舟運の便益に貢献した。晩年は、この地に隠棲し、開削工事に関係した人々の菩提を弔うため、この寺を建てたといわれている。 本堂には、了以の念持仏であった本尊の「千手観音像」及び遺言によって作られた法衣姿の木像了以像が安置されている。また、境内には、了以の子、儒学者でもあった素庵が建立した林羅山の撰文による了以の顕彰碑や夢窓国師の座禅石と伝えられる大きな石がある。 芭蕉の句「花の山 二町のぼれば 大悲閣」でも知られ、京都市街が一望できる客殿からの眺めは絶景である。
京都市
|

|
温泉旅館の手前の舟着場に上ると、碑が立っている。 花の山二丁のぼれば大悲閣 芭蕉 この句である。 「何だか名所案内のような句じゃありませんか」 「そう云えぬこともないが、まあ即興的に云ったものだろう、桜にうかれ騒いでいる、そこから僅か離れた所に静かな御堂がある。そういう気持を芭蕉は出したかったのだろう。それが感じられないこともない。
『随筆芭蕉』(嵐山) |

|
八月一日、嵐山に遊ぶ、大悲閣途上 さやさやに水行くなべに山坂の竹の落葉を踏めば涼しも |


|
この句、落柿舎の句也。「「雲置嵐山」といふ句作、骨折たる処」といへり。
『三冊子』(土芳著) |

|
○嵐山大悲閣上比肩す蓼太老人に對す 最一聲隱者の慾やほとゝきす |

|
その日も水量は多かったが、船頭は棹をさして川上へ遡って行った。小倉山が正面に見えるあたりで、船は岩にごつんとぶつかった。そこが大悲閣の下である。 山の登り口に 花の山二町登れば大悲閣 自然石の平らな面に彫られたこの句は里程標のような句碑だ。芭蕉の作とは信じ難い。明治十一年の建立。 曲折しつつ登ると、途中に乙字の句碑があるけれど、この地ゆかりの句とは思われない。さらに曲折しつつ登る。大悲閣に近づいて 六月や峰に雲おくあらし山 の句碑が、右側、岩の上にが立っている。元禄七年の六月、落柿舎にての作。私はこの句を褒めてこう書いた。 嵐山が峯に雲を置いたようだが、嵐山はそんなことは出来ない。それは芭蕉が置いたのだ。本来造化のなすべきことを人間がなしたとき、その人間は詩人と呼ばれる。 キザなことを云ったものだ。 大正五年の建立。字は落着いていない。
『句碑をたずねて』(京都) |

|
明治40年(1907年)8月20日、与謝野寛、木下杢太郎、吉井勇、平野万里の4人は大悲閣に登る。 |
|
大悲閣の懸岸に突き出した楼上、遙かに京の市街や東山を望んで語る。下から吹上げる川風に、浴衣の袖は羽が生へたやうに翻へる。小僧さんが渋茶を注いで呉れた。我等は備へてある四角な木の枕をして一時間許り午睡をした。余り凉しいので嚔(くしやみ)をして目が覚める。
「五足の靴」(京の山) |
|
明治42年(1909年)、大町桂月は大悲閣に上った。 |
|
嵐山と大井川とあるを以て、京都は、始めて山水秀麗の地也。春の櫻、秋の紅葉を以て世に著はれたるが、今や、一山の新緑、我が眼をよろこばす。渡月橋を渡りて、右岸を行く。山相を迫つて、水清く、境幽也。温泉場に、人の生動を見るも、境なほ幽也。二三町の山坂を喘ぎながら上りて、大悲閣に到れば、眼界やゝ開けて、京都平源を望む。『花の山二町上れば大悲閣』。煩悶せしものが頓悟したる時の心地も斯くや。 閣は木像了以の創建に係るとかや。堂内に其の像あり、堂外に其の碑あり。了以は、慶長年間、保津川を開鑿して、舟を通ずるやうにせり。今は、京都を見物して、保津川下りをなさずんば、眞に京都を見物したるものと云ふべからずとまで稱せらるゝか、こは了以の賜物也。
「嵯峨の二日」 |
|
嵐 山 だいひかく うつら うつらに のぼり きて をか のかなた のみやこ を ぞ みる |