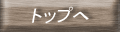『奥の細道』〜東 北

五月雨の降残してや光堂

|
元禄2年(1689年)5月12日(新暦6月28日)、芭蕉と曽良は一関に到着。翌13日、平泉へ。 |
|
十三日 天気明。巳ノ尅ヨリ平泉ヘ趣。
『曽良随行日記』
|
|
兼て耳驚したる二堂開帳す。経堂は三将の像をのこし、光堂は三代の棺を納め、三尊の仏を安置す。七宝散うせて、珠の扉風にやぶれ、金の柱霜雪に朽て、既頽廃空虚の叢と成べきを、四面新に囲て、甍を覆て雨風を凌。暫時千歳の記念とはなれり。 五月雨の降のこしてや光堂
『奥の細道』
|

|
経堂ハ別当留主ニテ不開
『曽良随行日記』
|

|
月花螢こや三衡のひかり堂 |


|
大正3年(1914年)、高浜虚子は光堂を訪れ、芭蕉の句碑を見ている。 |
|
前にも言つた日光の建物は徳川氏の豪奢を想はしめるが金色堂――一名光堂――の、柱壁は申すに及ばず床も屋根も悉く黄金で塗り立てたといふ其の思ひ切つた贅澤、其に精巧を極めた螺鈿細工の如きに至つては却て日光で見ることの出來ぬより以上の豪華を想はしめる。金色堂の傍に苔蒸した石があつて其に芭蕉の「五月雨の降り殘してや光堂」の句が刻してある。私と渡邊氏とが其を見てをる時に暫く上つてゐた五月雨は又降り出した。
「汽車奥の細道」
|
|
昭和28年(1953年)6月19日、水原秋桜子は金色堂を見ている。 |
|
金色堂は藤原氏三代の理想浄土なり 青梅雨の金色世界来て拝む 優曇華(うどんげ)や金箔いまも壇に降る 華鬘(けまん)揺れ浄土の梅雨ぞ寂びにける
『帰心』
|
|
昭和40年(1965年)、山口誓子は中尊寺の句碑を訪ねている。 |
|
光堂と経堂の境のところに句碑が立っている。然も光堂の修理小屋の裏のせせこましいところに立っている。「むざんやな」である。 墓碑のようだ。しかしいい句碑だ。正面下に「芭蕉翁」。上に 五月雨の降残してや光堂
『句碑をたずねて』(奥の細道)
|
|
元禄9年(1696年)、天野桃隣は中尊寺を訪れ、句を詠んでいる。 |
|
少行テ一ノ関、是ヨリ高舘・平泉。義経像堂一宇。弁慶桜、中尊寺入口ニ有。亀井が松、田の中ニ有。北上川・衣川・衣の関・関山・金鶏山。 弘台寿院中尊寺は東叡山末寺、当住浄心院。当寺は慈覚大師開基、貞観四年、元禄九マデ八百八十五年ニ成。金堂・光堂是也。 ○金堂や泥にも朽ず蓮の花 ○田植等がむかし語や衣川 |
|
享保元年(1716年)5月、稲津祇空は常盤潭北と奥羽行脚。光堂を訪れている。 |
|
鐘楼跡は見えす。如来堂、弁天祠、左に光堂、東むき、秀衡三代の石の棺を納む。七宝荘厳の巻柱ふりたり。宝物色々しるすにいとまなし。後に経堂、白山宮、姥杉一本、十囲はかり、大さ牛をかくす。円隆寺、嘉祥寺、泉水のかた計残り、西に和泉が城、月山見ゆ。泰衡が館のあとは金鶏山の麓に茫々たり。 英雄の跡植のこせ夕早苗 |
|
元文5年(1740年)、榎本馬州は『奥の細道』の跡を辿る旅で平泉に着く。 |
|
聞えしは此夏草の夢二つ 辨慶はかうも破つたか冷し瓜 |
|
寛延4年(1751年)、和知風光は大雪の中を中尊寺の光堂を訪ねた。 |
|
衣関中尊寺光堂 大雪中ヲ登ル 降こめる雪の晴間や光堂 |
|
明和2年(1765年)秋、大島蓼太は平泉を訪れている。 明和6年(1769年)4月、蝶羅は嵐亭と共に中尊寺を訪れ句を詠んでいる。 |
| 中尊寺 光堂 |
||||||||
| 雨の日やほたる飛かふひかり堂 | 蝶羅 |
|||||||
| ありがたや若葉のなかにひかり堂 | 嵐亭 |
|
安永2年(1773年)、加舎白雄は光堂を訪れた。 |
|
ひかり堂おがみて ふりし代のひかり身にしむ巻ばしら |
|
安永5年(1776年)、不二庵風五は光堂で句を詠んでいる。 |
|
光 堂 金色堂 傾く日の惜しさや秋の光堂 吹入れて秋風さひし光堂
『水蛙集』(三編)
|
|
光堂 露の身に明りさしけり堂の隅 乙二 |



|
金色堂修復の棟札から鎌倉期の正応元年(1288年)の建立とされてきたが、現在は建築様式から室町中期と考えられているそうだ。 |