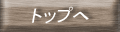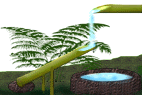
高山寺〜秋桜子の句碑〜

高尾の神護寺、槙尾の西明寺、栂尾の高山寺が三尾である。
|
明治25年(1892年)11月11日、正岡子規は三尾を訪れた。 |
|
川一つ處々のもみぢ哉
「獺祭書屋日記」 |
|
明治38年(1905年)10月1日、長塚節は栂尾を訪ねた。 |
|
十月一日、栂尾 栂尾の槭(もみぢ)は青き秋風に清瀧川の瀬をさむみかも |
西明寺が見える。

|
昭和32年(1957年)7月24日、水原秋桜子は高山寺に赴く。 |
|
二十四日午前、栂尾高山寺に赴く。境内の石水院は、 明恵(みようゑ)上人の住みたまひしところなれば、清 瀧川の谷をへだてて深瀬山に対し、幽邃きはまりなし 唖蝉も来て聴聞す明恵伝 明恵上人つたへける茶の夏茶碗
『蓬壺』 |
西明寺は紅葉の名所

| 京都 栂尾高山寺 |
|||||||||||||
| 恋に疲れた 女がひとり |
|||||||||||||
| 大島つむぎに つづれの帯が |
|||||||||||||
| 影を落とした 石だたみ |
|||||||||||||
| 京都 栂尾高山寺 |
|||||||||||||
| 恋に疲れた 女がひとり |
高山寺の参道に水原秋桜子の句碑があった。

ひくらしやここにいませし茶の聖
昭和34年(1959年)11月21日、『馬酔木』同人桂樟蹊子建立。
水原秋桜子は句碑の除幕式に参列した。
|
高山寺 散紅葉鳥獣絵巻かくれなし 香焚いておろす蔀や山紅葉
『旅愁』 |
『秋櫻子句碑巡礼』(久野治)によれば、第7番目の秋桜子句碑である。
高山寺に「日本最古之茶園」がある。
|
鎌倉時代初期、臨済宗の開祖栄西は宋から茶の種をもって帰国した。それを授けられた高山寺の開祖明恵は栂尾の地に植えたそうだ。 |
北山杉の間の参道

|
昭和37年(1962年)7月15日、高浜年尾は高山寺で京都ホトトギス会。 |
|
七月十五日 京都ホトトギス会 栂尾高山寺 峠越え来れば涼しき峡となる 木下闇高くうつろを為しゐたり |
|
昭和38年(1963年)6月22日、高野素十は高山寺を訪れている。 |
|
同二十二日 栂尾高山寺 夏山に鳥獣戯画の巻を舒べ
『芹』 |
|
昭和39年(1964年)10月15日、星野立子は高山寺へ。 |
|
十月十五日 冨士子の案内で秀好の家を訪問 栂尾高山寺へ |
|
前山の松の姿ぞ秋深し 紅葉には早やかりしかど美しき |
|
青い中に早紅葉見えている山を私等は見ても倦かぬ思い であった。 |
石水院が見える。

石水院は国宝。
高山寺に伝わる『鳥獣人物戯画』も国宝。
石段を登ると、金堂がある。

高山寺金堂

宗派は真言宗御室派系単立。
|
昭和42年(1967年)11月16日、荻原井泉水は高山寺の紅葉を見る。 |
金堂の左に開山堂。

|
明和元年(1764年)9月、多賀庵風律は田子の浦の帰途、高雄山の紅葉を見ている。 |
|
もみちの比ハ四方山をなかめて目の行所枝折となれはいつくと定かたきに神護寺東福寺を最上といへり高雄山にて 古郷へハぬすミて帰る紅葉哉 |
嵐山へ。
平成6年(1994年)、古都京都の文化財は世界遺産に登録。
2008年〜京 都〜に戻る