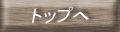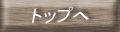2006年〜茨 城〜
筑波山〜女体山頂〜

筑波山神社から筑波山鋼索鉄道で筑波山へ。

大正14年(1925年)10月12日、筑波山鋼索鉄道営業開始。
昭和6年(1931年)2月25日、与謝野晶子は筑波神社を参拝し、翌26日にはケーブルカーで山頂近くの御幸ヶ原に登る。
筑波山は日本百名山のひとつである。
筑波山頂駅から女体山頂(標高877m)に行く。
セキレイ石

ガマ石

女体山御本殿

筑波女大神伊弉冉尊(いざなぎのみこと)を祀る。
女体山頂

山頂は人がいっぱい。
貞亨3年(1686年)、大淀三千風は筑波山に登った。
○筑波山頂 はやましげ山の腰に、筑波の里、六百宇。知足院中禅寺、いと奇麗なり。これよりも頂上へ一里半の苔滑にして、たらたら雫をしのぎ、屹々と彌山、信に馬耳の名にしおゐて、二峯に男躰女體権現鎮し給ふ。椎柴を摘て、眞折手草にかざし、偖も當山は、神佛秘藏の寄(よさし)あり。ここに陰高きしげみは、大君の御影に比し、和歌の良材おもだちがほに、歴々たる富士淺間はさらなり。廣々たる湖潮麓をまはり、月日をむすぶ常陸帶、とくにとかれぬ神宿世かなと、古代の神詠も思ひ出されて、
元禄9年(1696年)、天野桃隣は筑波山に登り、句を詠んでいる。
麓ヨリ二里登ル、かたのごとく難所、岩潜・岩の立橋・千尋の谷。春夏の中、巓ニ茶屋五軒、魚肉酒禁断。馬耳峯の間十丁余有、頂上ニ登て四方を見るに眺望不斜(ななめならず)。
右の外、霊山の奇瑞おほし。
○土浦の花や手にとる筑波山
○筑波根や辷(スベツ)て転(コケ)て藤の花
享保元年(1716年)4月7日、稲津祇空は奥羽行脚の途上砂岡我尚・常盤潭北と筑波山に登った。
男躰の霊社絶頂にあり。小社あまたまはりをかこみ、石の色蒼潤山骨奥巧たり。遠坂曲折にして雲は麓を白峰に綿のことく変態もつとも常ならす。その観るもの奇なれとも形状を悉にすり事あたはす。松は盖のことし。すなはち纏を出て室をむすふのおもひあり。四五町をくたりて女躰にまいる。社頭のさま男躰とおなし。匂ひし花の名残ともなしと、ありし風雅のすしにあふきけんもありかたくこそ。
寛保元年(1741年)、白兎園宗瑞は筑波山に登る。
筑波は嶮山にして照れる日は暑に苦しむけふは曇りて幸ひよしと汗かきの東休にすゝめられていさとおもひ立二三子打つれ椎の尾山より登るに馬はもとより駕さへ及はぬ山道なれは歩行よりそ行
宝暦3年(1753年)、横田柳几は筑波山に登り、句を奉納している。
討ものは筆はかり也櫻狩 布袋庵 柳几
是を矢立の初として騎西の町にかゝり栗橋の驛にいたる。利根川をわたれは下總の地也。
男躰山にいたりて頭をめくらせは士峯は坤(ひつじさる)にあたつて雲をつらぬき、鹿島か崎湖來の入江は巽(たつみ)に見下し手に取はかり。万山千峯一眼の内に盡たり。絶勝又いふへくもあらす。
二峯法樂吟
華さくや男山女山の諸しら髪
安永2年(1773年)7月、加舎白雄も「奥羽紀行」の旅で筑波山を訪れた。
にゐはり筑波山御製および其外いふにやおよぶ言の葉のかたみつきすまじくおもふつきすまじ
ふみづきやげにげに夜の筑波山
女体山頂からの眺望

ミなの川 さくら川 香取 鹿島 若国山 霞ノ浦
板敷山 皆眼下也
天明元年(1781年)5月1日、大島蓼太は翠兄の案内で筑波山へ。
山上
兩峰雙立してもろこしの羅浮山もかくやと道けはしく靈運か木履も着ましく石滑かなるに
鐵線や岩に鎖も誓より
(※「鎖」は「金」+「巣」)
寛政3年(1791年)6月10日、鶴田卓池は筑波山に登る。
嘉永4年(1851年)12月17日、吉田松陰は筑波山に登る。
十七日 晴。驛を出で、筑波の二巓を極む。一を男體と曰ひ、一を女體と曰ふ。是の日天氣晴朗、眺望特に宜しく、關東八州の形勢歴々として指すべし。山としては富士・日光・那須、水としては刀根・那珂、皆目前に聚まる。
明治39年(1906年)9月6日、河東碧梧桐は筑波山に登った。
東に霞が浦、西に両毛の平野を瞰下する。青いのは田で、白いのは水で、黄色いのは豆畑である。喜怒、利根も糸筋ほどにうねうねしており、豆の葉の黄色さは、時に菜の花かとも疑われる。東京はこちらかとばかりで、烟霞漠々として望み窮りない。習志野の砲声じゃそうな、ドロドロズシンし屡々響く。
女体山頂から男体山頂(標高871m)を望む。

昭和5年(1930年)、富安風生は筑波山で句を詠んでいる。
私もケーブルカーで下山。
筑波山神社に戻る。
2006年〜茨 城〜