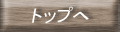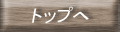大淀三千風
『日本行脚文集』

巻之六
貞亨3年(1686年)閏3月14日、大淀三千風は京を出て東山道に赴き、美濃の大垣へ。
○かくてみのゝ大垣俳人のがりまかでしに。いせ櫻にときゝて。せうぞこしてをき侍れは。明の春脇句にまた發句そへてをくられし。
粧たる櫻を留守に風流(いたり)哉
|
|
三里追うつ笠の蝶々 美濃大垣
| 木因
|
|
其後は風のいずこに行櫻
| 仝
|
○伊津貫川の鮎くむなど見て。岐布に里稲葉山を左になし。はや本道に出。鵜沼の里に泊る。
尾張への追分。中津川にかり寢して。美(みの)と信(しなの)の境橋。馬籠村を過。
○寢覺床 ころは貞享。寅うそふく風のあととふ。又の櫻月ちりかいくもるねさめの床の朝霞。不染(そめで)やむへき筆の色かな。
中山道から善光寺街道を行き、善光寺へ。

○即時に一軸かきちらし。揚松梯彌生坂。福島。宮越。鳥居峠本山。松本仇坂矢坂。青柳猿峠丹波島。川中島に出。むかし信玄謙信鼻々したまふ戰塲をかたり。善光寺日野屋なにがしが亭につく。先珠數とりて。其名も高き佛日の善光(よきひかり)ある御寺の境内繁々たる。
善光寺から姨捨山の麓を通り、句を詠んでいる。

○卯月四日荒鞍山。園原山を過。又善光寺の如来にいとま乞して。苅萱寺を拜し。義仲の古城兼平が領地。伏屋の里。更科山の陰を通りがてら。
御代田町塩野の真楽寺を訪れている。

かくて上田海野小諸鹽野につく。明れは卯月八月八日會日なれは、みちづれあまたあり。さしも名高き淺間の嵩、天狗山、無間澤などたどりて、禅頂煙洞の内輪まで四里半。於(あゝ)雲のかけはし、煙のちまた、膽をひやし、人々逃まろぶ。漸々麓に下向して、大沼山眞樂寺に淺間記一軸を殘す。略。
淺間山あさく見るへき煙かは吾身も終の空にくゆれは
4月12日、蓮生山熊谷寺に参り、江戸に着く。
蓮生山熊谷寺

○かくて松枝板橋高崎を過、熊谷に一宿して蓮生法師の寺にまいり、鴻巣大宮うち過て、余(うづき)十二日、江戸本町富山氏に着ぬ。
貞亨3年(1686年)5月4日、大淀三千風は熱海を訪れている。
○五月四日。離襟(さらば)の聲耳に傳ふ。山彦山の峠にかゝり。大磯がよひのむかしを思ひ。祐成が塚に廻向して。曾我古郷をうち過。小田原にかりふして。伊豆行脚と心ざし。海を左に。石橋山を右になし。根府河の關をこえ眞鶴の海岸。頼朝卿のかくれ給ひし窟を過。戸井杉山古々井森。伊豆權現をふし拜み。走湯におり。熱海の湯本。なにがし羽生屋に宿かり。旅づかれをはらし。げにもきこふる名湯に神骨まめやかに。四日計ひたゝれし。偖しも此湯口。晝夜に六たび岩口ヨリ吐出す。その猛煙奇妙の湧ざま。又二なきめづら物也。浴斛(みぶね)の間に温泉記一軸して。町長なにがしに送し。記略。
○はまりけり湯口の曇鵑(ほとゝぎす)
大淀三千風は伊東の佛現寺の事を書いている。

○彼赤君を沈し松が枝の渕、日蓮聖人滴(たく)所、佛現寺、けさかけ松のむかしとりあつめ、伊藤の記長編せし。略す。
蛭ヶ小島を訪れている。
北條の古城、蛭が小島、江馬、江川、此ほか名所打ながめ、原木實和寺方丈の記をかく。當所よりは富士の眺望よし。
○鼻にのせて富士を嗅(※「鼻」+「臭」)ぬる颪哉
大淀三千風は身延山を訪れた。

又これより難所なれば案内者をたのみ竈口の綱橋を過、藤川の縁道、嶮岨嶮岨をたどり、からふじて三日ばかりに甲州身延山の總門にいり、山本坊にて當山景望の一軸長編略。
甲府を訪れ、善光寺にて興行。

○偖寺中かなたこなたにまねかれ。庭の記屏風腰ばり何くれと書投(かきすて)。四日逗留して同廿二日甲府柳町伴野氏につく。親子饗應大かたならず。情にほだし八日留る。善光寺にて興行。天神畫像に。
酒折宮を訪れた。

○當所酒折天神は連歌の濫觴なり。徃古日本武尊東夷征伐の時の行宮なり。無言抄の序に、新治筑波の詞よりおこれりと云々。尊の御句に、
○新治筑波を出てき(ママ)夜かぬる。甲府の連宿一萬句奉納、その發句を金板に寫し、巻頭の句をして小序をつけて書と所望せられ、ぜひなくかき侍りし。其發句、序は略。
貞亨3年(1686年)、大淀三千風は差出の磯などを見て、恵林寺を訪れた。
恵林寺三門

○かくて甲府を立つ。さし出の磯、鹽の山、鵜飼寺を見て、かの信玄公菩提所、乾徳山惠林寺に案内して、荊山老和尚に謁し、旅行のはふれをはらす。當寺は古跡にて境内二里四方、殿閣重重(づしやか)に靈寳みな昔を戀る。種(くさはひ)也。例の虫喰牙を噛出し、長編を半軸記す。
猿橋を通りがかる。

○大月猿橋を過、上の京關柳吉野小原小佛を越て、武藏八王子青木氏に泊る。
大淀三千風は行徳から香取神宮を右に見て、鹿島神宮を訪れた。
鹿島神宮

行徳・白井・大森、木颪のなみにゆられ、右は下總香取の神、常陸の湖水にながれこし、志田の浮島、浮洲の宮、旅のとまりは鹿島なる、大舶着にぞあかりける。
筑波山に登った。
女体山頂からの眺望

○筑波山頂 はやましげ山の腰に、筑波の里、六百宇。知足院中禅寺、いと奇麗なり。これよりも頂上へ一里半の苔滑にして、たらたら雫をしのぎ、屹々と彌山、信に馬耳の名にしおゐて、二峯に男躰女體権現鎮し給ふ。椎柴を摘て、眞折手草にかざし、偖も當山は、神佛秘藏の寄(よさし)あり。ここに陰高きしげみは、大君の御影に比し、和歌の良材おもだちがほに、歴々たる富士淺間はさらなり。廣々たる湖潮麓をまはり、月日をむすぶ常陸帶、とくにとかれぬ神宿世かなと、古代の神詠も思ひ出されて、
大淀三千風は安達が原から会津へ。円蔵寺に参詣。
霊巌山圓蔵寺

同葉月廿二日に川俟を立、安達原、黒塚、檀(まゆみの)里、二本松に笠舎(やどり)して會津にかゝり。先柳津靈光山圓藏寺虚空藏に詣し。抑當山は。法相唯識の徳一大師開基の地。中尊は空海御作。靈驗佛。猶山河岩樹の風景。無双の眺望なり。
巻之七
このページのトップに戻る
『日本行脚文集』に戻る