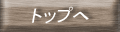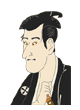
法然院〜野風呂の句碑〜

|
二十日、雨、法然院 ひやゝけく庭にもりたる白沙の松の落葉に秋雨ぞ降る 竹村は草も茗荷も黄葉してあかるき雨に鵯ぞ鳴くなる |



|
大正9年(1920年)、日野草城等とともに「京鹿子」創刊。 昭和21年(1946年)4月3日、句碑建立。 昭和46年(1971年)3月10日、野風呂は83歳で死去。 |
|
昭和21年(1946年)10月14日、高浜虚子は法然院に遊ぶ。 |
|
寺なれば秋蚊合点厠借る 十月十四日 京都、東山、ミューラー初子邸。立子等と共に。 法然院に遊ぶ。
『六百五十句』 |
|
本坊書院の庭に高浜虚子「念仏の法のあやめのかへり花」の句碑があるそうだ。 |
|
昭和32年(1957年)、高野素十は法然院を訪れている。 |
|
法然院 むささびのとびたる春の夜を訪ひし
『芹』 |

|
松尾いはほは本名巌。京大卒。高浜虚子・大谷句仏等に師事。京大医学部教授・同附属病院長。 |
|
昭和38年(1963年)11月22日、81歳で没。 昭和39年(1964年)11月22日、句碑建立。 |
|
昭和40年(1965年)6月、山口誓子は金福寺から鹿ヶ谷の法然院を訪ねた。 |
|
金福寺を出て白川通を南下。鹿ヶ谷の法然院に着く。 階を登って、左に進むと、左側に巨大な自然石が立っている。句碑だ。 椿落ちて林泉の春動きけり 「いはほ」とあるのは松尾巌。京大医学部の教授だった巌に私も診察して貰って、肺尖カタルの病名を附けられたことがある。一診の恩を受けたのだ。私の大学時代のことだ。 しかし、この句碑はその大きさに於いて格を逸している。 その辺から正面に見える法然院の小門はいい。 本堂の庭には野風呂の 鶯や今日の本尊にこやかに の句碑が立っている。二三幹の松の下、低い句碑だ。本堂では如是師が導師となってお勤めがつづいている。木魚の音がいつまでもつづく。 法然院を訪えば墓地へ足を向けざるを得ない。
『句碑をたずねて』(京都) |
|
昭和45年(1970年)12月13日、高浜年尾は関西ホトトギス同人会で法然院へ。 |
|
十二月十三日 関西ホトトギス同人会 京都法然院 雪嶺をいくつも越えし旅なりし 院庭の冬紅葉こそ今日の景 |


|
昭和40年(1965年)、阿波野青畝は法然院で谷崎潤一郎の生前の墓所を見た。 |
|
空・寂の小墓二つやいとざくら
『甲子園』 |
|
昭和40年(1965年)7月30日、谷崎潤一郎死去。享年80。法然院に納骨。百日法要で、東京都豊島区の慈眼寺にある両親の墓に分骨。 |
|
京都東山の法然院には知名人が墓となって楽しく眠っている。噂にきいた谷崎潤一郎の生前の墓所がある。そのときは熱海に静養されまだ健筆をとっていたのである。墓所はやや小高みの静かな一郭が仕切られてある。二個の小じんまりした自然の丸石に、空を右側に、寂を左側に一字しか彫っていないのを、浄き砂のまん中に据えてある。まだ芽を出さぬ若木の糸桜は後立てとして枝をしだれている。いいお墓だと心を打たれた。生長すればこの糸桜が春濃艶な環境をつくり出して、それでこそ谷崎好みを見せるであろう。私の背後へしずかな衣ずれが近づいて細雪の女性におどろかされるのではないかという気分。そういった墓所にさっきから鶯の声がしきりにきこえていた。 文豪谷崎潤一郎も今や故人となり、その墓に望みどおり安らかに憩うておられよう。 |

|
貞享5年(1688年)、『笈の小文』の旅の帰路、岐阜の長良川で鵜飼を見て詠まれた句。 |