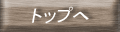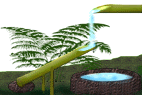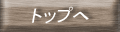安政7年(1860年)3月3日、大老井伊直弼は桜田門外で暗殺された。
|
|
文久2年(1862年)、村山たか女は金福寺に入る。
|
祖省塔

「村山たか女」の参り墓
たか女は、明治9年金福寺で14年間隠棲し、67才の生涯を閉じた。当時この寺は圓光寺の末寺であったので、本墓は圓光寺にたてられた。金福寺でも彼女の菩提を弔うため本墓の土を埋め、彼女の筆跡を刻み、参り墓とした。
徂く春や京を一目の墓どころ
| 虚子
|
昭和37年(1962年)、中村草田男は金福寺を訪れている。
金福寺を訪ふ。芭蕉を追慕して蕪村の建立せる芭蕉庵あり。
その傍に「憂き我をさびしがらせよ閑古鳥」の句碑あり。こ
の句の初案「……秋の寺」を、後日「……閑古鳥」に改めた
りと言ひ伝ふるものなり。一句。
「秋の寺」かよ「閑古鳥」かよ憂き身一つ
同地域内に蕪村自身の墓もあり。やや久しく三人にて附近を
逍遥す。二句。
画俳離俗冬日自楽の碑文字肥ゆ
われは小石を友は木の実を形見とす
『萬緑』
山口誓子は金福寺に芭蕉の句碑を訪ねている。
そのあたりに金福寺がある。芭蕉の句碑があると云うので訪ねて来たのだ。詩仙堂の南に当り、同じ一乗寺町。階を登って門を入り、直ぐ右の庭に入る。
そこに御影石角石のかなり大きな句碑が立っている。連記。
花守は野守に劣るけふの月
西と見て日は入りにけり春の海
前者は蕪村、後者はその弟子百池の作。
私は百池のこの句を好む。現代にも通用する句だ。
その庭を通り過ぎ、東の小高い丘に登って行くと、平地に芭蕉の句碑が立っている。芭蕉庵という庵の裏だ。
低い自然石。
うき我をさびしがらせよかんこ鳥
ひどく苔づいているが、見る角度によって字ははっきり読める。
2010年〜京 都〜に戻る