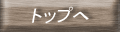『奥の細道』〜東 北〜

静さや岩にしみ入る蝉の聲
芭蕉の句碑
『奥の細道』〜東 北〜

静さや岩にしみ入る蝉の聲


|
松尾芭蕉のおくのほそ道の紀行文に、 山形領に立石寺という山寺あり。慈覚大師の開基にして、殊に清閑の地なり。一見すべきよし、人々の勧むるによりて、尾花沢よりとつて返し、その間七里ばかりなり。日いまだ暮れず。麓の坊に宿借り置きて、山上の堂に登る。岩に巌を重ねて山とし、松栢年旧り、土石老いて苔滑らかに、岩上の院々扉を閉ぢて物の音聞こえず。岸を巡り、岩を這ひて、仏閣を拝し、佳景寂寞として心澄みゆくのみおぼゆ。 閑かさや岩にしみ入る蝉の声 芭蕉翁の句をしたためた短冊をこの地に埋めて、石の塚をたてたもので、せみ塚といわれている。 |

|
台石に壷中・吟里をはじめ、18名の俳号が刻まれている。天童の俳人浦夕・池青の名もある。 |
|
壷中・吟里の両風子、故翁の短冊を納て蝉塚をいとなめることは、俳祖の光徳の固きよりと、尚更尊く覚へて |
| 其声や築は今も蝉の塚 | 五竹坊 |
|
『蝉塚集』 |
| 梢より紅葉もをりて神迎 | 池青 |
||||||||||||||||||||||
| 山寺や蝉のもぬけの置所 | 浦夕 |
|
『諸国翁墳記』に「蝉 塚 羽州岩上立石寺ニ在 山口吟里 林嵜壷中建」とある。 |

|
いにし年ならん、最上林崎駅の壺中といふ俳士、此山中に翁の塚を築き、此短冊を埋て、蝉塚と名づく。
蓑笠庵梨一『奥細道菅菰抄』 |
|
宝暦5年(1755年)4月30日、南嶺庵梅至は立石寺で「せみ塚」を見ている。 |
|
下れハ立石寺の庭に祖翁の墳墓有此山の吟詠を塚の神とせり 彼句に曰 |
| 閑さや岩に染ミ付く入蝉の聲 | 翁 |
|||||||||||||
| 蝉塚や其閑さを山の骨 |
|
宝暦8年(1758年)、梅田徳雨は立石寺を訪れて「せみ塚」を見ている。 |
|
我翁も七里の道を立帰て静さや岩にしみ入る蝉の声と諷吟有しを後の人石にしるして今に残れりかゝる深山幽谷ににも翁の遺風や誠に俳神と云つへしもし吾故郷に帰らはと感涙を落して今此一集にもとつき千鳥墳のちなみとはなれりける |
|
寛政3年(1791年)5月22日、鶴田卓池は山寺を訪れ、「せみ塚」を見ている。 |
|
山寺 宝珠山立石寺 慈学大師ノ開基 薬師堂 坐禅石 護摩ノ虚石 念仏堂 七福神岩 山王権現ト慈学大師ノ対面石 山上迄登九丁 知行 千四百二十石 奥ノ院 釈迦堂 開山堂 慈学大師 入定ノ窟トツカウ水天狗岩 拝ミ所都合四十八ヶ処 コトコトク岩山ニテ至テ清閑也 翁ノ碑 しつかさや岩にしみ入る蝉の声
『奥羽記行』(自筆稿本) |
|
天保12年(1841年)7月7日、最上稲沢の稲州は翁の句碑を拝まんと立石寺に詣でる。帰路、漆山の半沢亭に立ち寄り3泊する。 |

|
嘉永4年(1851年)頃、桑折の俳僧一如庵遜阿は山寺で「せみ塚」を見ている。 |
|
立石寺 羽中之勝景、世謂之山寺、七月七日大祭、夜念仏、獅子踊興行、開山慈覚大師之化教云 碑云 しづけさや岩にしみ入るせみの声 芭蕉翁 |
|
昭和3年(1928年)7月29日、荻原井泉水は山寺で「蝉塚」を見ている。 |
|
その日の夕方、私は山寺の石道を登っていた。「おくのいんみち」と標してあり、桜の木の下に蝉塚といって、芭蕉の蝉の句を刻した碑がある、そこから山にかかるのだ。木立もすっかり影って、もう汗を感じないほどに凉しくなっていた。
『随筆芭蕉』(凉しさや、閑かさ) |
| 昭和33年(1958年)7月、加藤楸邨は「蝉塚」を見ている。 |
|
蝉塚は路の屈曲するやや平坦な部分にある。最上の壷中が建てたもの、蝉の句の短冊を埋めた塚であるといわれている。碑の右側の上の方に小さく 閑さや岩にしみ入る蝉の声 と刻まれて、ここまでたどりついた人が汗を拭いながら読むにふさわしい。私がたどりついたときは、ちょうど読経の終ったところで、蝉の声が幾つかきこえていた。
『奥の細道吟行』・下 |
|
昭和40年(1965年)、山口誓子は立石寺の茶店の前に句碑を訪ねている。 |
|
石階の途中に平地があって茶店の床几が出ている。私は思わずその床几に腰を卸した。眼の前にやや高く、右から「芭蕉翁」「せみ塚」「壷中居士」と三つ並んでいる。私は卸した腰を揚げて、その碑に近づいた。「芭蕉翁」の碑が即ち「せみ塚」だ。円筒形の自然石。「せみ塚」の碑は角柱標石。「壷中居士」は建立者の碑、建立の年を明和六年と刻んでいる。 私が句を探しあぐねていると、茶店の女が、「蝉塚」の右脇に彫ってあると教えて呉れた。 静さや岩にしみ入蝉の声 「しみ入」の「み」がよく読めない。「ミ」なのか。 根本中堂脇の句碑よりもこの方が八十四年前に建てられた。此には「静」、彼には「閑」即ち一は「寂静」他は「閑寂」。
『句碑をたずねて』(奥の細道) |