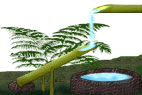
小塚原刑場跡〜首切地蔵〜

|
江戸のお仕置き場(刑場)は、品川の鈴ヶ森と千住の小塚原の2つである。 小塚原の刑場は、間口60間余(約108m)、奥行30間余(約54m)で、明治のはじめに刑場が廃止されるまでに、磔、斬罪、獄門などが執行された。 首切地蔵は、この刑死者の菩提をとむらうため、寛保元年(1741年)に建てられたものである。
荒川区教育委員会 |
|
明和8年(1771年)、蘭学者杉田玄白・前野良沢らは小塚原刑場において刑死者の解剖(腑分け)に立ち合った。 |

|
小塚原での刑死者の菩提をとむらうため、寛保元年(1741年)に建立されたこの地蔵は、27個の花崗岩を組み合わせた全体の高さが4mに近い坐像で、台座には発願者・石工の名が刻まれている。奥州街道沿いにあったので、江戸に出入りする多くの人が目にしたという。明治28年(1895年)に土浦線(現常磐貨物線)敷設工事のため、線路の南側から現在地に移されたが、人々に安らぎを与えてきた慈悲の姿は変わるところがない。 |
|
十日 折々雨 去五月廿二日 町奉行所 小田切ノ白州ニテ三人切殺シタル金エ衛門小塚原ニて梟首 四十六
『七番日記』(文化7年8月) |

|
小塚原 科札に天先時雨給ひけり
『七番日記』(文化11年11月) |
|
曇りて風あり。午後電車にて千住小塚原に至る。刑場跡の地藏尊は猶汽車線路土手下にたちてあり。回向院別院を訪ひ鼠小僧と直侍との墓を掃ふ。 |
|
寛文7年(1667年)、小塚原刑場で処刑された人々を供養するため、両国回向院の別院として小塚原回向院が創建された。 |
|
安政6年(1859年)10月7日、橋本左内は小伝馬町牢屋敷において斬刑となり、小塚原回向院へ埋葬される。 安政6年(1859年)10月27日朝、吉田松陰は死罪を申し渡され、同日午前10時に伝馬町牢屋敷で刑が執行される。松陰は罪人として回向院に葬られた。 文久3年(1863年)、吉田松陰の墓所は高杉晋作らによって世田谷区若林の長州毛利藩藩主毛利大膳大夫の所領大夫山に改装される。 |

