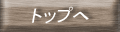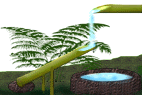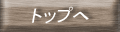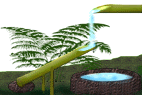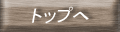2008年〜京 都〜
芭蕉堂〜西行庵〜
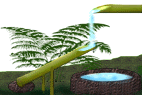
金閣寺から円山公園へ。

円山公園の南に芭蕉堂があった。

芭蕉堂
この堂は、江戸時代中期、俳聖松雄芭蕉をしのぶため、芭蕉にゆかりの深いこの地に加賀の俳人高桑闌更が営んだことに始まる。
鎌倉時代の初め、諸国を旅して自然を友とした西行が、この地に阿弥陀房を訪ね、
柴の庵と聞くはくやしき名なれども よにこのもしき住居なりけり(『山家集』)
と詠んでいる。芭蕉は、この西行を心の師とし、西行を慕って旅の生涯を送ったが、この地で先の西行の作歌を踏まえて、
しばの戸の月やそのままあみだ坊(小文庫)
の一句を詠んだ。この句を生かして闌更が営んだのが、この芭蕉堂である。
堂内には、芭蕉十哲の一人森川許六が刻んだ芭蕉の木像を安置する。
毎年4月12日には花供養、11月12日には芭蕉忌が行われる。
なお、東隣の西行庵庭内には各務支考が芭蕉十七回忌に建てた「かな書の碑」がある。
京都市
明和2年(1765年)3月12日、蓑笠庵梨一は雙林寺の墨直しに参列している。
三月十二日は東山雙林寺祖翁の石碑墨直しの会式にして、ことしは洛の蝶夢法師是をつとむ、出席の風士三十人はかり、百韻の俳諧あり、おのおの桜の発句して碑前に手向ぬ、予は其巻頭の役にさされて、
影落て朝日も白きさくらかな
天明6年(1786年)、京都東山雙林寺に芭蕉堂を創立。
寛政2年(1790年)3月10日、朝暮園傘狂は京都東山雙林寺で主催芭蕉百回忌取越法要を主宰。田上菊舎も参列する。
寛政7年(1795年)夏、小林一茶は芭蕉堂の高桑蘭更を訪問して歌仙を巻く。
芭蕉堂之会
|
|
|
|
月うつる我顔過ぬほとゝぎす
| 闌更
|
|
|
風こゝちよき入梅晴の道
| 亜堂
|
西行庵

昭和11年(1936年)3月19日、種田山頭火は芭蕉堂、西行庵へ歩いた。
三月十九日 晴。
朝は寒く昼は暖か。
どこといふあてもなく、歩きたい方へ歩きたいだけ歩いた。――
八坂の塔、芭蕉堂、西行庵、智恩院、南禅寺、永観堂、銀閣寺、本願寺、等々等。
清水寺に向かう。
二寧坂・産寧坂は人がいっぱい。清水坂は歩けないほどだった。
清水寺に行くのは止めて帰る。
2008年〜京 都〜に戻る