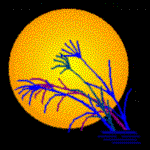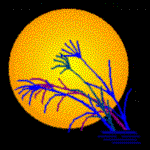東海道
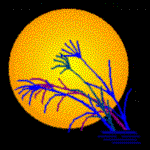
『十六夜日記』(阿仏尼)
弘安2年(1279年)、阿仏尼が京都から鎌倉へ下った折の道中記。10月16日、京都を出発し、29日、鎌倉に到着。50代後半のことである。
今日は十六日の夜なりけり。いと苦しくて、うち臥しぬ。いまだ月の光かすかに残りたる明ぼのに、守山を出でて行く。野洲川渡る程、先立ちて行旅人の駒の足音ばかりさやかにて、霧いと深し。
旅人も皆もろともに先立ちて駒うち渡す野洲の川霧
十八日、美濃国関の藤河渡る程に、先づ思ひ続けける。
わが子ども君に仕へんためならで渡らましやは関の藤河
不破の関屋の板庇は、今も変らざりけり
隙多き不破の関屋はこの程の時雨も月もいかにもるらん
墨俣とかや言ふ川には、舟を並べて、まさきの綱にやあらん、かけとゞめたる浮橋あり。いと危う(ふ)けれど渡る。此川、堤の方はいと深くて片方(かたかた)は浅ければ、
片淵の深き心はありながら人目づゝみにさぞせかるらん
仮の世の往き来と見るもはかなしや身を浮舟の浮橋にして
とぞ思ひ続ける。
阿仏尼の歌碑

又、一宮といふ社を過ぐとて、
一の宮名さへなつかし二つなく三つなき法を守るなるべし
阿仏尼の歌碑

一の宮といふやしろをすくとて
|
|
一のみや名さへなつかしふたつなく
|
|
みつなき法をまもるなるへし
|
廿日、尾張国折戸といふ駅を行く、避(よ)きぬ道なれば、熱田の宮へ参りて、硯取り出でて書きつけて奉る歌五、
祈るぞよわが思ふこと鳴海潟かた引く潮も神のまにまに
鳴海潟和歌の浦風隔てずは同じ心に神も受くらむ
満つ潮のさしてぞ来つる鳴海潟神やあはれとみるめ尋ねて
雨風も神の心にまかすらんわが行先の障りあらすな
契あれや昔も夢にみしめ縄心にかけてめぐりあひぬる
潮干の程なれば障りなく干潟を行折しも、浜千鳥いと多く先立ちて行くも、しるべがほなる心地して、
浜千鳥鳴きてぞ誘ふ世中に跡とめむとは思はざりしを
隅田河のわたりにこそありと聞きしかど、都鳥といふ鳥の觜と足と赤きは、この浦にもありけり。
言問はむ觜と足とはあかざりし我住む方の都鳥かと
二村山を越えて行に、山も野もいと遠くて、日も暮れはてぬ。
はるばると二村山を行過ぎて猶末たどる野辺の夕闇
八橋にとゞまらんといふ。暗きに、橋も見えずなりぬ。
さゝがにの蜘蛛手危う(ふ)き八橋を夕暮かけて渡りぬる哉
高師の山もこえつ。海見ゆるほどいとおもしろし。浦風あれて、松のひゞきすごく、浪いとあらし。
わがためや風もたかしのはまならむ袖のみなとの浪はやすまで
いとしろきすさきに、くろき鳥のむれゐたるは、鵜といふとりなりけり。
白はまにしみの色なるしまつとりふでもおよはゞ繪にかきてまし
濱名の橋より見わたせば、かもめといふ鳥、いとおほくとびちがひて、水のそこへもいる、岩のうへにも居たり。
かもめゐるすさきのいはもよそならずなみのかずこそ袖に見なれて
今宵は、引馬(ひきま)の宿といふ所にとゞまる。此所の大方の名は、浜松とぞ言ひし。親しといひしばかりの人々なども住む所なり。住み来し人の面影も、さまざま思ひ出られて、又めぐりあひて見つる命の程も、返々(かへすがへす)哀なり。
浜松の変らぬ影を尋ね来て見し人なみに昔をぞ問ふ
其世に見し人の子孫(こうまご)など呼び出でてあひしらふ。
今宵は遠江(とをつあふみ)見付の里といふ所にとゞまる。里荒れて物恐ろし。傍に水の井あり。
誰か来て見付の里と聞くからにいとゞ旅寝ぞ空恐ろしき
廿四日、昼に成て、さやの中山越ゆ。事任(ことのまゝ)とかやいふ社の程、もみぢいと面白し。山陰にて荒も及ばぬなめり。深く入まゝに、遠近(をちこち)の峰続き、異山に似ず、心細く哀也。麓の里に菊川といふ所にとゞまる。
越え暮す麓の里の夕闇に松風送るさよの中山
暁、起きて見れば、月も出にけり。
雲かゝるさやの中山越えぬとは都に告げよ有明の月
河音いとすごし。
阿仏尼の歌碑

雲かかるさやの中山越えぬとは都に告げよ有明の月
廿五日、菊川を出でゝ、今日は大井川といふ河を渡る。水いとあせて、聞きしには違ひてわづらひなし。河原幾里とかや、いと遙か也。水の出でたらん面影、推し量らる。
思ひ出る都のことは大井川幾瀬の石の数も及ばじ
廿六日、藁科川とかや渡りて、興津の浜に打出づ。「なくなく出し跡の月影」など、先づ思ひ出でらる。昼立ち入たる所に、あやしき黄楊の小枕あり。いと苦しければ、打臥したるに、硯も見ゆれば、枕の障子に、臥ながら書きつく。
なを(ほ)ざりのみるめばかりをかり枕結びおきつと人に語るな
暮れかゝる程、清見が関を過ぐ。岩越す浪の白き衣を打着するやうに見ゆる、いとお(を)かし。
清見潟年経る岩に言問はん浪の濡衣幾重ね着つ
程なく暮て、其わたりの海近き里にとゞまりぬ。浦人のしわざにや、隣よりくゆりかゝる煙、いとむつかしきにほひなれば、「夜の宿なまぐさし」と言ひける人の詞も思ひ出でらる。夜もすがら風いと荒れて、浪たゞ枕に立騒ぐ。
ならはずよよそに聞こし清見潟荒磯浪のかゝる寝覚は
富士の山を見れば、煙も立たず。昔、父の朝臣に誘はれて、「いかに鳴海の浦なれば」など詠みし比、遠江国までは見しかば、富士の煙の末も、朝夕確かに見えし物を、いつの年よりか絶しと問へば、さだかに答ふる人だになし。
誰が方になびき果ててか富士の嶺の煙の末の見えずなるらむ
伊豆の国府といふ所にとゞまる。いまだ夕日残る程、三嶋の明神へ参るとて詠みて奉る。
あはれとや三島の神の宮柱たゞこゝにしもめぐり来にけり
を(お)のづから伝へし跡もあるものを神は知るらん敷島の道
尋ね来てわが越えかゝる箱根路を山のかひあるしるべとぞ思ふ
廿八日、伊豆の国府を出でては箱根路にかゝる。いまだ夜深かりければ、
玉くしげ箱根の山を急げどもなを(ほ)明けがたき横雲の空
足柄山は道遠しとて、箱根路にかゝるなりけり。
ゆかしさよそなたの雲をそばたててよそになしぬる足柄の山
丸子川といふ河を、いと暗くてたどり渡る。今宵は酒匂といふ所にとゞまる。明日は鎌倉へ入るべしといふ也。
このページのトップに戻る
東海道に戻る