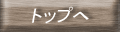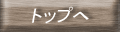私の旅日記〜2010年〜
清見寺〜句碑橋〜

静岡市清水区興津清見寺町の東海道本線沿いに清見寺(HP)という寺がある。

臨済宗妙心寺派の寺である。
清見寺総門

天武天皇の白鳳年間に清見関が設けられ、清見関の鎮護として建立された仏堂が清見寺の始めと伝えられている。
寛元4年(1020年)、菅原孝標女は父の任果てて上京。清見が関を行く。
清見が関は、片つ方は海なるに、関屋どもあまたありて、海までくぎぬきしたり。けぶりあふにやあらむ、清見が関の浪も高くなりぬべし。おもしろきことかぎりなし。
貞応2年(1223年)4月13日、京都に住む隠者は鎌倉に下る途中、清見関の跡を訪ねる。
清見関ヲ見レバ、西南ハ天ト海ト高低一ニ眼ヲ迷シ、北東ハ山ト磯ト嶮難同ク足ヲツマヅク。盤(いはの)下ニハ浪ノ花、風ニ開春ノ定メナリ、岸ノウヘニハ松ノ色、翠ヲ含テ秋ニオソレズ。浮天ノ浪ハ雲ヲ汀(みぎは)ニテ、月ノミ舟夜出テ漕、沈陸ノ礒ハ磐ヲ路ニテ、風ノ便脚、アシタニスグ。名ヲ得タル所必シモ興ヲエズ、耳ニ耽(ふけ)ル処必ズシモ目ニ耽ラズ、耳目ノ感二ツナガラ従(ゆるし)タルハ此浦ニアリ。波ニ洗テヌレヌレ行バ、濁ル心モ今コゝニ澄リ。宜ナル哉、此処ヲ清見ト名付タル。関屋ニ跡ヲトへバ松風空ク答フ、岸脚ニ苔ヲ尋レバ橦花変ジテ石アリ。関屋ノ辺ニ布タゝミト云処アリ。昔関守ノ布ヲトリオキタルガ、積テ石ニ成タルト云リ
吹ヨセヨ清見浦風ワスレ貝ヒロフナゴリノ名ニシオハメヤ
語ラバヤ今日ミルバカリ清見潟オボエシ袖ニカゝル涙ハ
仁治3年(1242年)8月、『東関紀行』の作者は鎌倉へ下る途中、清見が関でしばし休む。
清見が関も過うくてしばし休らへば、沖の石、むらむら塩干に顕(あらはれ)て波にむせぶ。礒の塩屋、所々風にさそはれて煙なびにけり。東路の思出とも成ぬべき渡り也。昔朱雀天皇の御時、将門といふ者、東にて謀反を(お)こしたりける。是をたい(ひ)らげんために、宇治民部卿忠文をつかはしける、此関に至りてとゞまりけるが、清原滋藤といふもの、民部卿にともなひて、軍監といふ司にて行けるが、「漁舟の火の影は寒くして波を焼く、駅路の鈴の声はよる山を過ぐ」といふ唐の歌をながめければ、涙を民部卿流しけりと聞にもあはれなり。
清見潟関とはしらで行く人も心ばかりはとゞめを(お)くらむ
弘安2年(1279年)10月26日、阿仏尼は清見が関を通る。
暮れかゝる程清見が関を過ぐ。岩越す浪の白き衣を打着するやうに見ゆる、いとお(を)かし。
清見潟年経る岩に言問はん浪の濡衣幾重ね着つ
文正元年(1466年)、宗祇が関東に下向する途中、駿府に義忠を訪ねた。宗長は義忠の仰せで宗祇を清見が関に案内した。
二十九日、宗祇故人先年当国下向思ひ出でて、折に合ひはべれば、年忌の一折張行。
思ひ出づる袖や関もる月と波
この心は、先年この寺に引誘して、関にて一折の発句、宗祇
月ぞゆく袖に関もれ清見潟
思ひ出づるといふ愚句なるべし。新古今に、
見し人の面影とめよ清見潟袖に関もる波の通ひ路
この歌、本歌にや。
『宗長日記』
文亀2年(1502年)8月11日、宗長は清見が関へ。
道のほど、たれもかれももの悲しくてありし山ぢのうがりしも、なきみわらひみかたらひて、清見が関に十一日につきぬ。夜もすがら磯の月をみて、宗長
もろともに今夜清見が関ならばおもふに月も袖ぬらすらん
宝永5年(1708年)4月、明式法師は江戸に下る途上、清見潟に泊る。
ゆきゆきて、月の清見潟に枕を柱(さゝ)ふ。阿佛尼のなまぐさきめにあへるも此浦の旅寢ならむ。
明和8年(1771年)4月20日、諸九尼は清見が関を過ぎる。
廿日 清見が関を過るに、岩こす波の、白き絹を打きするやうにミゆと有、ふるき文の言葉、げにとおもひ出られて、あかず詠侍る。
清見寺山門

明治22年(1889年)、東海道本線が境内を通過。
雪舟も清見寺を訪れ、後年富士・三保・清見寺の景色を画いているそうだ。
徳川家康が今川氏の人質として駿府にいた頃、清見寺住職太原和尚に教育を受けていたそうだ。
天正18年(1590年)4月、豊臣秀吉は清見寺に滞在、伊豆韮山城攻めに清見寺の鐘を陣中で使用したと言われている。
清見寺仏殿

天保15年(1844年)、落成。
貞亨4年(1687年)4月26日、大淀三千風は薩垂峠を過ぎ、清見寺へ。
同卯月廿六日吹上の松。薩垂峠を過。清見寺にのぼる。三國一の風景。言翰のをよぶ所にあらず。されども獨つぶやく。
元禄元年(1688年)2月、鬼貫は伊丹を立ち、清見寺を訪れている。
元禄3年(1690年)9月29日、鬼貫は江戸に向う旅の途上清見寺で句を詠んでいる。
江尻を過て、清見寺にのぼる。
庭上秋深うして佛閣靜に高し。海
原見やる所望めば、こゝろのび、
また心よはくなれり。
秋の日や浪に浮たる三穂の邊
元禄5年(1692年)7月15日、森川許六は清見寺を訪れて句を詠んでいる。
七月十五日到清見寺
|
|
盆棚やむかひは冨士よ清見寺
| 許六
|
元禄11年(1698年)6月7日、岩田涼莵は清見寺で句を詠んでいる。
元文2年(1737年)6月、白井鳥酔と秋瓜は沼津から清見寺を訪れている。
清見寺
|
|
折から掃除日とて
|
寺僧のあまたおり立ければ
|
|
箒とる坊さま涼し清見潟(寺)
| 秋瓜
|
|
清見とは松の葉越の鰹ぶね
| 西奴
|
白井鳥酔は『海道記』のことを書いている。
むかし朱雀天皇の御時將門といふ者東にて逆謀起しけるに是をたいらけん爲にうちの民部卿忠文をつかはしける此關に到りてとゝまりけるか清原重藤といふ者民部卿伴ひてぐんかんと云つかさにて行けるか漁舟の火の影は寒うして浪を燒驛路の鈴の聲は夜山を過ぐといふから哥をなかめけれは民部涙をなかしけると聞て哀なり 清見かた關とはしらす行人も心はかりはとゝめおくらん折から名物にたはむれて
新蕎麥や目をとゝめたる人通り
清見寺大方丈

文政8年(1825年)、改築。
十一面観世音菩薩坐像を安置する。
大野伴睦の句碑

秋晴や三保の松原一文字 萬木
大方丈の前に「臥龍梅」がある。
家康公御手植えの松と言われている。
龍臥して法の教えを聞くほどに梅花開く身となりにけり
与謝野晶子が臥龍梅を詠んだ歌である。
昭和12年(1937年)1月11日、与謝野晶子は清見寺を訪れている。
東海の表の國のうるはしき山山見ゆる清見臺かな(清見寺にて)
寒ざくら清見の寺に唯だ一枝偲ぶむかしのある如く咲く
御寺よりまかり出づれば美くしく夕明りさす清見潟かな
清見潟さくらの散るに勝りたる光りをそそぐ波の上の日
清見潟空明るくて淡雪の降るごとひろぐ波の立つかな
臥龍梅の下に歌碑があったが、半ば生け垣に埋もれていた。
清見寺書院

慶応3年(1967年)、落成。
享和元年(1801年)3月1日、大田南畝は大坂銅座に赴任する旅で清見寺を訪れた。
右のかたに石坂あり。三曲にして門にいれば清見寺なり。庭に大きなる梅の木横たはれり。客殿の椽に永世孝享の額あり。また諸仏宅の三字は朝鮮の青螺山人の筆なり。此門前は清見がせきの跡なりといふ。春の海づらきよくして、右に三穂の松原さしいでゝ、田子の浦とをし。かゝる詠めをさしをきて、書院の庭に石を畳み、水はしらせたらんもいかゞならんと、さしのぞきしまゝにて出ぬ。
清見寺中庭

昭和11年(1936年)、国の名勝に指定された。
句碑橋

芭蕉の句碑「西東あハれさおなし秋の風」が石橋になっている。
出典は『笈日記』。
貞亨3年(1686年)8月、去来は妹千子と『伊勢紀行』の旅をした。その跋文に添えて贈った句。
清見寺の五百羅漢石像は島崎藤村の小説「桜の実の熟する時」の最後の場面になっている。
興津の清見寺だ。そこには古い本堂の横手に丁度人体をこころもち小さくした程の大きさを見せた青苔の蒸した五百羅漢の石像があった。起ったり坐ったりして居る人の形は生きて物言ふごとくにも見える。
誰かしら知った人に逢へるといふその無数な彫刻の相貌を見て行くと、あそこに青木が居た、岡見が居た、清之助が居た、ここに市川が居た、菅も居た、と数えることが出来た。
連中はすっかりその石像の中に居た。捨吉は立ち去りがたい思をして、旅の風呂敷包の中から紙と鉛筆とを取出し、頭の骨が高く尖って口を開いて哄笑して居るやうなもの、広い額と隆い鼻とを見せながらこの世の中を睨んで居るやうなもの、頭のかたちは円く眼は瞑り口唇は堅く噛みしめ歯を食いしばって居るやうなもの、都合五つの心像を写し取った。五百もある古い羅漢の中には、女性の相貌を偲ばせるやうなものもあった。
磯子、涼子それから勝子の面影をすら見つけた。
私の旅日記〜2010年〜に戻る