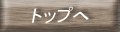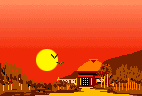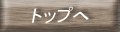酒匂川に望む。折から雨後の瀬例より汎漲とし目くるめきて、猶々老の足にかなふへからすと打詠居たるに、そこの村長鈴木氏杉鳥子は元より同門の交り深し、はからすもそこへ杖ひき來りやゝ日の影永う傾く迄語り別るゝに、ありあふをのことも數多下知せられて、輦臺といふものに打乘り人に骨をおらせて越けるは、翅に風を得たるに似たれは、一章をもて臺の歸りに乘せて謝す。
蝶々や吹れてわたる川の上
|
享和元年(1801年)2月28日、大田南畝は大坂銅座に赴任する旅で酒匂川を渡る。
|
酒匂川の水落て瀬浅し。土橋三ツあり。三月六日には橋をひくといふ。河原広くして蛇籠などもみゆ。かの梶原が、ければぞ波はあがりける、といひけん鞠子川もこれなるべし。
|
文化2年(1805年)11月17日、大田南畝は長崎から江戸に向かう途中で酒匂川を渡る。
|
十七日夜明てたつ。酒匂川をわたり、梅澤をすぎ、大塚平塚をこゆるに、風出たり。馬入川をわたり、南湖をへて、藤澤の宿、藤兵衛がもとにやどる。
|
嘉永4年(1851年)4月7日、吉田松陰は肩車で酒匂川を渡っている。
|
一、七日 翳。卯後、小田原を發す。肩輿にて酒匂川を渡り、大磯・平塚を經てて、舟にて馬入川を渡る。
|
東海道五拾三次之内・小田原「酒匂川」(安藤広重)

「酒匂のかは」は『東海道中膝栗毛』にも出ている。
打わらひつゝあゆむともなしいつの間にか曾我の中むら小八わた八まんの宮を打すぎ、さかわ川にさしかゝりければ
われわれはふたり川越ふたりにて酒匂のかはに〆てよふたり
此川をこへゆけば小田原宿のやど引はやくも道に待ちうけて、
|
街 道〜東海道に戻る