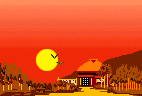この松は、陸奥の歌枕のなかでもその詠歌の多いことでは屈指の名木である。
千年余前、陸奥の国司として着任した藤原元良(善)が植え、以後能因・西行をはじめ多くの歌人に詠まれるようになった。
元禄2年5月4日(1689年、現在の6月20日)、この松を訪れた松尾芭蕉は、「武隈の松にこそめ覚る心地はすれ……めでたき松のけしきになん侍し。」と『おくのほそ道』に記して「桜より松は二木を三月越シ」の句で結び、曾良の『随行日記』には、「岩沼入口ノ左ノ方ニ、竹駒明神ト伝有リ、ソノ別当ノ寺ノ後ニ武隈の松有、竹がきヲシテ有。ソノ辺、侍やしき也」とある。
この松は、植え継がれて七代目といわれ、文久2年(1862年)に植えられたものと伝えられている。
昭和44年(1969年)5月29日、市の文化財に指定された。
平成元年3月
岩沼市教育委員会 |
「武隈の松」は、藤原元善の歌が文献初出だそうだ。
陸奥守にまかり下れりけるに、武隈の松の
枯れて侍けるを見て、小松を植へ(ゑ)継がせ侍て
任果てて後、又同じ国にまかりなりて、かの
前(さき)の任にへ(ゑ)し松を見侍て
藤原元善の朝臣
栽(うゑ)し時契(ちぎり)やし剣(けん)武隈の松をふたゝび逢ひ見つる哉
|
歌碑があった。

宇恵し登きち起里やしけ舞多計久満の
|
松をふたたびあ飛見つ留嘉那
| 藤原元良
|
|
堂希久満の松八二木越美屋古人
|
い可ゞと問ハゞみ起とたたへ舞
| 橘 季通
|
万葉仮名で書かれている。
明治34年(1901年)、岩沼の醸造家松尾小左衛門建立。鈴木省三(号…雨香)書。
昭和3年(1928年)7月22日、荻原井泉水は「二木の松」で歌碑を見ている。
|
この松の後に植継ぐべきものとして、小松が別に育ててある、そこには碑を立てて、この松に関する古歌が刻してあった。
|
うゑしときちぎりやしけむたけくまの
| 藤原元良
|
|
松をふたゝびあひみつるかな
|
|
たけくまの松は二木を都人
| 橘 季通
|
|
いかゞととはゞ三木とこたへん
|
|
『随筆芭蕉』(武隈の松) |
芭蕉の句碑があった。

桜より松は二木を三月越し
真蹟懐紙には「ちりうせぬ」とある。
平成3年(1991年)3月、建立。
武隈の松は『源氏物語』(薄雲)で明石母子の別れにも出ている歌枕である。
西行も訪れている。
武隈の松は昔になりたりけれども、跡をだにとて見に罷りて詠みける
|
枯れにける松なき跡の武隈はみきと言ひても甲斐なかるべし
|
武隈の松も枯れていたようだ。
二木の松(武隈の松)

文明19年(1487年)、道興准后は武隈の松に立ち寄っている。
|
武隈の松蔭に暫らく立ち寄りて、ふりぬる身のたぐひなりと、思ひよそへてよみ侍りける
徒らに我も齢はたけくまのまつことなしに身はふりにけり
|
元禄9年(1696年)、天野桃隣は武隈の松を訪れ、句を詠んでいる。
|
金が瀬ヨリ岩沼へかゝり、橋の際左へ二丁入て、竹駒明神アリ。社の乾(いぬゐ)の方へ一丁行テ、武隈の松アリ。松は二木にして枝打垂、名木とは見えたり。西行の詠に、「松は二度跡もなし」とあれば、幾度か植継たるなるべし。
○武隈の松誰殿の下涼
|
「西行の詠」は能因の誤り。
陸奥国にふたゝび下りてのちのたび、武隈の
松も侍らざりければよみ侍りける
能因法師 |
武隈の松はこのたびあともなし千歳をへてやわれは来つらむ
|
享保元年(1716年)5月、稲津祇空は常盤潭北と奥羽行脚の途上武隈の松を見にいった。
|
岩沼にやとる。行末のまた遠けれは、といひて武隈の松を夜るみにまかる。
夏痩や更たけくまの松の月
|
元文3年(1738年)4月24日、田中千梅は松島行脚の途上、武隈の松を見ている。
|
此夜は岩沼の宿にやとる明れハ武隈の松を見る
|
寛保2年(1742年)、大島蓼太は奥の細道行脚の旅に出て武隈の松を訪れている。
延享4年(1747年)、武藤白尼は横田柳几と陸奥を行脚して武隈の松を訪れている。
|
名にあふ武隈の松は竹駒明神の辺にあり二タ木の松ともいへり
|
|
|
寛延4年(1751年)、和知風光は『宗祇戻』の旅で俄の時雨のため武隈の松に行くのを止めた。
|
武隈の松見んとせしに俄にしくれしきりなれは行事やみぬ
|
武隈の松こそ見せね大しくれ
|
宝暦13年(1763年)4月、蝶夢は松島遊覧の帰途、武隈の松を訪ねている。
|
「都の土産に見きといはん」と武隈の松をたづぬ。いでや、此松の栄枯度々なる、元善・季通は茂りしを称し、能因・西行は枯しをなげかれしに、いづれのころ植しにや、二木の陰たれて千とせの色ふかし。
一木づゝ調べ合すや青あらし
|
明和2年(1765年)、大島蓼太は再び武隈の松を訪れている。
|
ふたゝび武隈の松にいたりて
我老も松のおもはむ下すゞみ
|
明和7年(1770年)、加藤暁台は奥羽行脚の旅で二木の松を訪れている。
|
此松に古きことくさにも云ひつたへて常にもおもひもふけしに、たかはね蒼髯二幹に立わかれて、角もじやいかで一木とはいふべくもあらず
|
松かげや左右にわかれて下涼み
| | 暁台
|
|
扇にのせてすり流す墨
| | 休粋
|
|
|
明和8年(1771年)6月12日、諸九尼は武隈の松を見て句を詠んでいる。
|
岩沼に出て、ミきとこたへんと有し、武隈の松の二木を見る。
風薫る松やいづれを相夫恋
|
安永2年(1773年)、加舎白雄は武隈の松を訪れた。
|
たけくまの松にて
松がもとふた木の露をうけしらむ
|
寛政3年(1791年)5月29日、鶴田卓池は武隈の松を訪ね、白石の城下へ。
|
名取川を過て岩沼に宿る。道祖の社、笠島の実方塚は、足のいたみに心いそぎて見残はべりぬ。武隈のまつを尋ね、あぶくま川をわたりて、白石の城下にいづる。
|
寛政6年(1794年)、倉田葛三は奥羽行脚の途上武隈の松で句を詠んでいる。
|