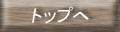『奥の細道』では第1日目の宿泊地が草加宿のようにも読めるが、『曽良随行日記』には「廿七日夜 カスカベニ泊ル。江戸ヨリ九里余」と記されている。
千住から草加まで2里8町(約9km)。芭蕉の『奥の細道』の旅としては近すぎる。やはり春日部に泊まったのであろう。
いずれにしても、『奥の細道』に「早加と云宿にたどり着にけり」とあるので、草加には芭蕉像がある。
|
芭蕉像

芭蕉像があるだけで、何の説明もない。
昭和10年(1935年)、麦倉忠彦は草加市に生まれる。
昭和29年(1954年)、春日部高等学校卒業。
平成元年(1989年)3月、奥の細道旅立ち300年記念に設置。
平成11年(1999年)、草加市文化賞受賞。
平成12年(2000年)、afternoon制作。 |
宝暦13年(1763年)3月17日、二日坊は江戸を立ち、草加に泊まっている。
|
けさまてハ栄耀の土地にありて、今宵ハ物うらめしき寝覚也ける
|
|
|
明和6年(1769年)4月5日、蝶羅は奥羽行脚の途上草加で句を詠んでいる。
|
草加といふ宿にて
|
|
泊れとて散らすや藤は夏ながら
| 蝶羅
|
|
|
安政6年(1859年)正月25日、市原多代女は須賀川を立ち、江戸に向かう。
|
草 加
江戸ちかくなるや雲雀のいくところ
かねは上野か浅草か、そゞろにこゝろさはぎて、句も出ずなりぬ
|
正岡子規の句碑があった。

梅を見て野を見て行きぬ草加まで
明治27年(1894年)の句。
子規は虚子と千住街道を草加迄行き、さらに西新井の大師堂を拝み、最終汽車で帰ったそうだ。「籠さげて若菜つみつみ関屋まで」という句もある。
|
さゝやかなる神祠(ほこら)に落椿を拾ひあやしき賤の女に路程(みちのり)を尋ね草加に着きぬ
|
巡禮や草加あたりを歸る雁
| 虚子
|
|
梅を見て野を見て行きぬ草加まで
|
|