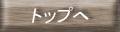護国八幡宮〜木曽義仲〜
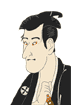

|
■御祭神 主神 八幡大神 産業・文化・勝運の神 宮縁起によれば、奈良時代養老年間に宇佐八幡宮の御分霊を勧請(お迎え)したのに始まり、天平時代には越中の国守大伴家持が国家安寧を祈願したと伝えられる。 平安時代の末、寿永2年(1183年)5月、木曽義仲は倶利伽羅山で平維盛の大軍と決戦するに当たり、埴生に陣をとり、当社に祈願をこめて著しい霊験があった。このことは、平家物語、源平盛衰記などの中に語られている。 以来、蓮沼城主遊佐氏、武田信玄、佐々成政など、戦国武将の信仰が篤く、江戸時代には、加賀藩主前田侯の祈願社となった。社名の「護國」とは、江戸の始め、地方に凶作が続いたため、前田利長卿が当社に祈願せられ、この尊号を奉ったことによる。 社殿は、大正13年国宝となり、現在は国指定重要文化財となっている。 ■例祭 9月15日、特殊神事「宮巡り」が行われる。 ■境内 約2万坪、日本一の源義仲像、「鳩清水」(とやまの名水)がある。 |


|
一 十五日 快晴。高岡ヲ立 。埴生八幡ヲ拝ス。源氏山、卯ノ花山也。クリカラヲ見テ、未ノ中刻、金沢ニ着。
『曽良随行日記』 |

|
元禄14年(1701年)6月、各務支考は今石動を訪れ、護國八幡宮に句を奉納している。 |
|
詣埴生八幡 此みやしろは、そのかみ木曾殿の願状をこめ給ひて、覺明か名をとゝめし地也、我は西花坊。むかしは一紙の願状にほこり、今は一篇の風雅にあそふ。いつれか先、いつれか後ならん。たゝかりの世にかりの名なるへし。 |
|
奉 納 白鳩の木末に凉し神の御意 |
|
明和8年(1771年)、加舎白雄は北陸行脚の途上、護国八幡宮を訪れている。 |
|
倶利伽羅嶺を越る麓に応神廟を祭る。木曾殿の願書覚明坊が筆とりしも此おゝん神の前にてときくに、 盧橘や御燈に筆を取りし跡 |
|
大正14年(1925年)8月28日、荻原井泉水は護国八幡宮で義仲戦勝祈願書を見ている。 |
|
長い、退屈な石動の町を出はずれて、当今の国道(天田越)と離れて、私のいわゆる「早稲の香」の村道を十町ばかり来ると、埴生という小さな村があった。ここが旧北陸道、すなわち倶利伽羅越のかかりである。「よくとれるむぐらとるきかい」と書いた札などさげて、雑貨を売ったり茶店もする家で私は草鞋を求めてつけた。この村の護国八幡宮に詣でて、木曾義仲が戦勝を祈った願文も見せてもらった。そのとき、源氏勢は七手にわかれて陣取ったのだが、総帥義仲の率いる一隊はこの埴生に屯していたのだった。
『随筆芭蕉』(倶利伽羅越え) |