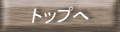東京プリンスホテル〜有章院(徳川家継)霊廟〜
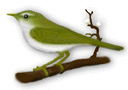
2022年〜東 京〜
東京プリンスホテル〜有章院(徳川家継)霊廟〜
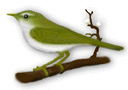
| ザ・プリンスパークタワー東京の東エントランスから都道409号日比谷芝浦線(日比谷通り)へ。 |
|
午後芝の御靈屋觀むとて行く。増上寺三門前電車通の古松は悉く伐られて今は一株もなし。三門内の假小屋にて切符を購ひ初に北側の御廟二箇所を拜觀し次に南側の廟及奥の院を拜觀す。境内の樹木も枯れて伐去られしが多し。また拜殿の内部壁画の前に置かれし器物も大方今は無し。余三田の大學に通勤せし折々來り觀し時に比すれば荒廢の氣味彌深きものあり。囘顧すれば三十年を經たればさもあるべきことなり。南側台徳院霊廟唐門の前水屋のほとりに立ちし槇の大木も枯れかけたり。こゝの水屋は石の柱に隳青の彩色を施せしをその頃余は殊に珍しく思ひたりしが今日來りみればその彩色大方剥落したり。北側なる御廟の中そのはづれなる廟の中門外に立並びし唐金の燈籠は大方取除かれて石の臺のみを殘したり。今頃はいづこかの工場にて鑄潰されしなるべし。然るに廟の外に立てる後藤象次(ママ)郎の銅像は依然として恙なきを見る。軍人政府の政策常に公平ならざること實に此くの如し。 |

| 港区指定有形文化財 |
|
重要文化財「旧台徳院霊廟惣門」の左右に安置している寄木造り、砥粉地(とのこじ)彩色の仁王像で、方形の台座に乗った岩坐(いわくら)の上に立っています。 平成16年から17年に行われた修理の際に、体内から修理銘札が発見され、元は埼玉県北足立郡戸塚村(現在の川口市西立野)の西福寺(真言宗)仁王門に安置されていたもので、寛政元年(1789年)、弘化3年(1847年)の2度にわたり修理が行われていることがわかりました。さらに 安政2年(1855年)の暴風で破損したまま同寺の観音堂の片隅に置かれていたものを、昭和23年(1948年)、同寺三重塔の修理と同時期に3度目の修理が行われた後で、東京浅草寺に移されたことも記載されています。その後の経緯は詳らかではありませんが、昭和33年ごろまでには この惣門に安置されたと考えられます。 本像は18世紀前半までには江戸の仏師によって制作されたと推測され、江戸時代の仁王像として破綻のない作行きを示す貴重な作品です。 像高 阿形 243.5センチメートル 吽形 247.0センチメートル
港区教育委員会 |

| 東京都港区指定文化財 |
|
増上寺の方丈(庫裡)の表門であったので方丈門とよばれ、また全体が黒漆塗であったために黒門とも呼ばれた。 四脚門で、建造年代を明らかにする棟札などの記録は見出せないが、江戸時代初期の特徴を示す様式から十七世紀後半のものと推測される。 蟇股には唐獅子や牡丹が浮彫されていて、精巧で写実的な図柄は、近世の建築彫刻の特色を示している。長年の風蝕のため、古色をおびているが、桃山建築の豪華さのおもかげがうかがえる。
港区教育委員会 |

|
慶長16年(1611年)に徳川家康公の助成により、幕府の大工頭・中井大和守正清によって建立され、元和8年(1622年)に再建されました。 この門は、増上寺で唯一の江戸時代初期の面影を残す建造物で、重要文化財に指定されています。 三解脱門は、別名「三門」と呼ばれ、3つの煩悩「貪欲(とんよく・むさぼり)、瞋恚(しんに・いかり)、愚痴(ぐち・おろかさ)の三悪を解脱する悟りの境地を表しています。 建築様式は三戸楼門、入母屋造、朱漆塗。唐様を中心とした建物に、和様の勾欄などが加味され、見事な美しさを見せています。 その大きさは、間口10間余(約19メートル)奥行5間(約9メートル)高さ7丈(約21メートル)の二重建て構造。さらに左右には3間(約5.4メートル)の山廊を有しています。 上層部(楼上)内部には、中央に釈迦三尊像、脇壇に16羅漢像が安置されています。 |
|
凡夫の心は 物に従いて移り易し 喩えば猿猴の 枝に伝うが如し 実(まこと)に散乱して動じ易く 一心静まり難し
『法然上人行状絵図』 |

|
燈刻芝口に飯して後芝公園を歩む。神明宮祭禮なり。増上寺三門前の老松枯れし後切去られて今は殆無し。御靈屋門際の松も一二本殘れるのみ。これも遠からず枯死すべし。此日晴れて日の光照りわたれり。
『斷腸亭日乘』(昭和16年9月20日) |

| 昭和55年(1980年)5月3日、東京プリンスホテルにて「ホトトギス会」1000号記念祝賀会。 |

|
現在の東京プリンスホテル敷地には、戦前、六代将軍家宜の文昭院霊廟と並んで、七代将軍家継の有章院霊廟がありました。プリンスホテル正面の二天門は有章院霊廟の惣門です。霊廟は八代将軍吉宗が享保2年(1717年)に建立しました。 その結構は日光に劣らぬと伝わる程でしたが、昭和20年(1945年)に東京大空襲で焼失しました。 この焼け残った二天門は銅板葺、切妻造りの八脚門で、左右に仏法守護の役目を持つ広目天、多聞天の2点が祀られています。焼けた文昭院霊廟の門に持国天、増長天が置かれ、合わせて四天王としてまつられていました。 |