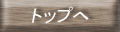〜芭蕉翁生家〜
芭蕉ゆかりの地

〜芭蕉翁生家〜


|
昭和38年(1963年)10月12日、芭蕉翁270年忌記念に芭蕉翁顕彰会建立。大西徹山作。 |

|
この処は俳聖芭蕉の生家である。芭蕉翁は正保元年(1644年)ここで生まれた。 父は与左衛門、母は藤堂宮内の移封に従い伊予国宇和島から名張に随従してきた桃地氏の女と伝えられる。与左衛門夫婦には2男4女があり、長男は又半左衞門命清(のりきよ)、次男はのちの芭蕉翁で、幼名を金作、長じて宗房を名乗った。ほかに通称を甚七郎、別に忠左衞門といった。 芭蕉翁が19歳の頃に仕えた藤堂藩伊賀附の侍大将藤堂新七郎家の息主計(かずえ)良忠は蝉吟と号して、北山季吟門に俳諧を学んでいた。俳諧好き芭蕉翁は新七郎家の文学サロンにも一座するようになり、めきめきと頭角をあらわした。その集大成ともいうべきものは、後の処女撰集『貝おほひ』の版行であった。 生家の後庭に建つ釣月軒は若き日の芭蕉翁の書斎である。芭蕉翁はここで『貝おほひ』(俳諧発句合)を編み、寛文12年正月25日、産土神である上野天神宮(上野天満宮とも)に奉納して文運を祈願し、その春江戸へと赴いた。江戸で俳諧宗匠となった芭蕉翁は故郷に幾度となく帰省したが、その故郷観は「代々の賢き人々も、古郷はわすれがたきものにおもほへ侍るよし。我今ははじめの老も四とせ過ぎて、何事につけても昔のなつかしきままに(下略)」という心情にしめされている。 |
|
『芭蕉翁全傳』に「正保元甲申の年、此國上野の城東赤坂の街に生る。」とある。 『奥細道菅菰抄』(梨一著)の「芭蕉翁伝」に「祖翁は、伊賀ノ国拓殖郷の産にして、弥平兵衛宗清が末裔。」とある。 |

|
釣月軒は芭蕉翁の生家松尾氏の後園に建てられた草庵である。 寛文12年(1672年)正月25日 ここで芭蕉は自撰の処女集である『貝おほひ』を執筆し 上野天神に奉納して江戸に下ったといわれている。 この『貝おほひ』は「三十番俳諧合」というごとく、芭蕉が郷里の上野の諸俳士の発句に自句を交えて これを左右につがえて三十番の句合とし、更に自ら判詞を記して勝負を定めたものである。 書名は遊戯の「貝おほひ」の「合せて勝負を見る」ところによったもので 序文に「寛文十二年正月二十五日 伊賀上野松尾氏宗房 釣月軒にしてみづから序す」とある通り、芭蕉が上野においてこの書を編み、折から菅公770年の忌日にこれを奉納したものと思われる。 版行は久しく不明であったが、昭和10年天理図書館が所蔵している。 本書は29才のときの芭蕉撰集であるとともに、芭蕉の生前中自署し、自著として刊行した唯一の出版物である。 芭蕉の判詞は当時の軽妙な洒脱を自由自在に駆使したもので、その闊達で奔放な気分は 談林俳諧の先駆的なものとなったことはいうまでもない。 いわば釣月軒は芭蕉翁立志の端緒をしめす文学遺跡であり、芭蕉文学の思想作風などの変遷を知る大切なものである。 |

|
元禄元年(1688年)芭蕉45歳の作。季語「冬籠り」で冬。『笈の小文』の旅・『更科紀行』の旅を終え、8月下旬、芭蕉は久しぶりに江戸深川の芭蕉庵に戻った。門人たちは残菊の宴や月見の宴など盛んに俳席を設け芭蕉を歓待している。こうして年の瀬を迎えた芭蕉が、その折の心境をしみじみと述懐し詠んだ句。出典は『曠野』等に所収。「またよりそはむ」「此はしら」の語に、住み馴れた草庵に戻り、いつも背を寄せ親しんだ庵の柱がいとおしく思われ、これからやすらいだ気持で冬籠りしようとする心情がうかがえる。一所不住の境涯を求めながらも、馴れ親しんだ棲家に心惹かれる芭蕉の姿がある。 「無名庵」は伊賀の芭蕉五庵の一つ。伊賀の門人たちが芭蕉に贈るため、ここ生家の裏庭に建てた庵で、元禄7年8月15日、芭蕉は新庵披露をかね月見の宴を催し、門人たちを心からもてなした。 句意は「今年は久しぶりに自分の草庵で冬籠りをすることになった。いつも背を寄せ親しんできたこの柱に、今年もまた寄りかかって、ひと冬閑居を楽しむことにしよう。」 |

|
昭和38年(1963年)10月12日、芭蕉二百七十回忌に芭蕉翁顕彰会建立。 |
|
本句碑の句は芭蕉翁記念館所蔵の翁の真蹟を拡大転写したものであります。この軸には翁の弟子杉山杉風が書いた「芭蕉翁筆」と言ふ極めがあり、まことに貴重なものであります。たまたま翁の二百七十年忌を記念して旧田中荘保存会の寄附によってこゝに句碑を建立しました。 |
|
元禄7年(1694年)7月15日、大津から帰郷し、一家で墓参。 |
|
甲戌の夏、大津に侍りしを、このかみのもとより消息せられければ、旧里に帰りて盆会をいとなむとて |
| 家はみな杖にしら髪の墓参 | 芭蕉 |
|
9月8日、芭蕉は支考、惟然を連れて、難波へ旅立つ。 |
|
九月八日、支考、惟然をめしつれて、難波の方へ旅立ち給ふ。こは奈良の舊都の九日を見むとなり。 |
|
伊賀上野なる芭蕉生家を訪ふ 正(まさ)しう聞きぬ呱々の声又秋の声
『大虚鳥』 |