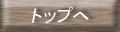身延山久遠寺〜日蓮宗総本山〜



|
貞亨3年(1686年)、大淀三千風は身延山を訪れた。 |
|
又これより難所なれば案内者をたのみ竈口の綱橋を過、藤川の縁道、嶮岨嶮岨をたどり、からふじて三日ばかりに甲州身延山の總門にいり、山本坊にて當山景望の一軸長編略。 |
|
元禄5年(1692年)5月21日、貝原益軒は身延山を訪れている。 |
|
今夜は身延にとゞまる。身延は名所なり。古歌あり。身延の寺は身延山久遠寺と号す。高き山の下、谷の上にあり。三方には山あり。いとものふかき谷の中なり。まへなる川に橋の長五六間なるあり。柱はなくて桁ばかりにて、上に板をならべり。大なる惣門あり。内にいれば町あり。 町を過て寺へゆけば、大なる三門あり。門上は閣なり。其高大美麗なる事、京都相国寺、南禅寺などの三門にもおとるまじと見ゆ。 三門を過れば甃(イシダゝミ)一町ばかりありて、やうやく高し。其上にけづれる石階の高きあり。両のかたはらにきれる石をもて、へりとす。のぼり行ほど石階八所にありて、其間にたいらかなる所、各一間ばかりあり。八所つらなれるきざはしのかず、すべて三六七級あり。最下より下をのぞめば、八所の石階、一に連り見へて高き事、天をのぞむがごとし。通計は凡百間ばかりもありなん。きざはしをのぼりつくせば上に二王門あり。二天門といふ。門にいれば即本院なり。 |
|
元禄8年(1695年)、山口素堂は葛飾阿武の草庵を出て故郷の甲斐に赴き、生前母の願いであった身延詣を果たす。 |
|
はき井の村につきて其夜はふもとの坊にやどりし。元政上人の老母をともなはれし事をうらやみて、 夢にだも母そひゆかばいとせめて のぼりしかひの山とおもはめ |

| 塵点の刧をし |
||||||||||||||||||||||||||
| 過ぎていましこの |
||||||||||||||||||||||||||
| 妙のみ法に |
||||||||||||||||||||||||||
| あひまつりしを |
|
安永5年(1775年)、加舎白雄は身延山に参詣している。 |
|
身をのべ山に登りしに嶽々渓(浣)々にみちみてる素袒(祖)纜の声にそふものは水の音や松の響に観彼久猶遠如今日と聞へしをおもひ合て、 またやまたけふをむかしに咲事か
「甲峡記行」 |

|
天明8年(1788年)3月14日、蝶夢は江戸へ下る途中で身延山に参詣した。 |
|
双門の額に「開会関」と有。夫より左右に町屋・坊舎ところどころにありて、三門を登れば、伽藍・僧坊・回廊、棟を並ぶ。幽の谷の底に壇所現然たり。西上人の歌によみ給ひし鶯谷は、今の回廊の所とぞ。 |
| 囀の真似して渡る小僧哉 |
|||||||||||||||||||
| 日にそふて桜匂ふか久遠山 |

|
文化3年(1806年)6月28日、菜窓菜英は身延山を参拝した。 |
|
外、堂塔樓閣数を知らず、短き筆の記に 餘れハ、南部六郎の霊といふに詣り、名たゝる 階の急なるを見て、なたらかなる阪路を下り て宿坊に帰る。 |


|
文政元年(1818年)5月、半場里丸は江戸に出て成蹊と会い、身延山詣でに出立。甲州の俳人を訪ね、信州から上州・下野・武州を巡歴。 |

|
文政7年(1824年)、佐賀の雲左坊は松島行脚と途上身延山に参詣している。 |
| 甲州身延山 |
||||||||
| 去年の秋ならん、諸堂回禄して今や仮 |
||||||||
| 建の尊像を拝し、いと哀にも又尊くも |
||||||||
| 元のことく並へや法の花甍 | 坊 |

|
昭和33年(1958年)4月13日、高浜虚子は身延山久遠寺に参詣した。 |
|
四月十三日。 比叡山、鞍馬山、高野山等には行つた事がある。それ等はみんな山上に大きな寺がある。 昔の坊さんはよく名山を相してそこに寺を造つた。身延も其の一つであらう。 身延には今迄詣る機會がなかつた。 (中 略) 下部ホテルで晝食。 われ等は自動車で、他の諸君は電車で、身延驛に逆行。 富士川に沿うて身延町がある。 少し上りになつて久遠寺著。 久遠寺參詣。 書院にて小松淨祐師等と會談。
「身延行」 |
|
昭和44年(1969年)3月3日、富安風生は身延山久遠寺へ。 |
|
身延山・久遠寺 二句 如月の柳緑あはきお山かな 思親閣は懐ふのみ 父母恋ふと枯れて千すじの糸桜
『米寿前』 |
|
昭和45年(1970年)10月、山口誓子は久遠寺を訪れている。 |
|
久遠寺 曼珠沙華願ひを蕊に擴げたる
『不動』 |