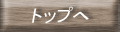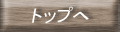山口素堂
「甲山記行」(山口素堂)

元禄8年(1695年)8月11日、山口素堂は葛飾阿武の草庵を出て故郷の甲斐に赴き、生前母の願いであった身延詣を果たす。9月8日、葛飾に帰庵。
それの年の秋甲斐の山ぶみをおもひける。そのゆゑは予が母君いまそかりけるころ身延詣の願ありつれど、道のほどおぼつかなうてともなはざりしくやしさのまゝ、その志をつがんため、また亡妻のふるさとなれば、さすがになつかしくて、葉月十日あまりひとつ日、かつしかの草庵を出、むさしの通を過て
かはくなよわけこし跡はむさしのゝ
月をやどせるそでのしら露
其日は八王寺(ママ)にやどり、十二日の朝駒木根の宿を過、小仏峠にて
山窓や江戸を見ひらく露の底
上野原に昼休、これより郡内領なる橋泊。橋の長さ十六間、両方より組出して橋柱なく水際まで三十三尋、水のふかさも三十三ひろあるよしをまうす。
「郡内領なる橋」は猿橋であろう。

十三日のたそがれに甲斐の府中につく。外舅野田氏をあるじとす。十五夜、
またもみむ秋ももなかの月かげに
のきばの富士の夜のひかりを
はき井の村につきて其夜はふもとの坊にやどりし。元政上人の老母をともなはれし事をうらやみて、
夢にだも母そひゆかばいとせめて
のぼりしかひの山とおもはめ
翌朝山上に至り上人の舎利塔拝て、かひの府より同道の人、
上人の舎利やふんして木々の露
祖師堂

北のかたへ四里のぼりて七面へ詣けるに山上の池不レ払して一点のちりなし。此山の神法会の場に美女のかたちに見え給ふよしかたりけるに
よそほひし山のすがたをうつすなる
池のかゝみやかみのみこゝろ
下りには一里ばかりの間松明の火にてふもとの坊に歸りぬ。
翌日甲斐の府へ帰路の吟
蔕(へた)おちの柿のおときく深山哉
重九の前一日かつしかの草庵に歸りて
旅ごろも馬蹄のちりや菊かさね
山口素堂に戻る