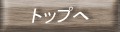石山寺〜芭蕉の句碑〜


石山寺東大門

石光山石山寺は西国順礼第十三番札所。
東寺真言宗大本山である。
| 明和7年(1770年)3月晦日、諸九尼は京都岡崎の湖白庵を跡にして、石山寺に詣でた。 |
|
石山寺に南華法師のいまそかりけるに、いとま申入んとてまうでけるに、都よりしたしき人のあまた送来り、水うミに影みゆるかぎりハと聞えけるを、とかくいひなぐさめて、爰より立かへる波の音もせずなりにき。 |
本堂を見下ろす。

| 明和8年(1771年)9月4日、諸九尼は再び石山寺に登り、旅の無事を謝している。 |
|
七ツ下りのころ石山に着て、世尊院の方丈に、頭陀袋をほどく。誠に大とこたちの、朝夕に祈たび給へりしゆへ(ゑ)にや、あやしの老の身の、つゝがなく、二度まミへ(ゑ)参らするも、大慈大悲の御恵ミなるべしと、なきミわらひミ物がたりて、夕ぐれの程に御堂に登り、所願成就の法施奉り、月見の亭に行てミれば、夕附夜の空はれて、風は律といふ調にやかよふらんと、やゝ時をうつす。 はらりはらり荻ふく音やびはのうミ |
世尊院は石山寺の塔頭。
辺りは色づき始めている。

| 享和2年(1802年)3月23日、太田南畝は石山寺を訪れ「源氏の間」を見ている。 |
|
左右に七軒の寺家あり。右に二王門あり。石山寺と言額あり。門を入り左右子院四軒あり。家居のさまもつきつきしく見ゆ。左のかたの奥なるは別當なるべし。知行五百七拾九石餘ときくもむべなり。右のかたにたてる石黒くさかしくみゆ。坂をのぼれば高さ丈にあまれる石つらなり峙り。本堂は南向にて本尊は觀世音とかや。紫式部源氏の間といふ有りて、カ(※「穴」+「果」)頭口に翠簾をたれたり。本堂に額あり。其文にいはく、 江州北郡浅井備前守息女亜相 当寺諸伽藍者 秀頼卿御母堂為二世安楽御再興也 とあり。拝殿もあり。三十八社の明神・多宝塔・叉庫(アゼクラ)等あり。鐘楼の鐘は人々のつく事をゆるすとみえて、かはるがはるつく音かしがまし。早鐘無用の札いでたるもおかし。 |
芭蕉の句碑があった。

曙はまたむらさきにほとゝきす
| 元禄3年(1690年)4月、芭蕉は紫式部が『源氏物語』を執筆したといわれている「源氏の間」を拝観。 |
『芭蕉句選拾遺』には「あけぼのやまだ朔日にほとゝぎす」とある。
嘉永2年(1849年)4月、建立。梅室筆。
瀬田尓泊りて暁石山寺尓まうてかの源氏の間をミて
| 願主 信州筑广郡會田郡矢久村 | 松風斎梅朗 |
右芭蕉翁真蹟画賛一軸 | 石山寺尓寄附して一墳建立 | 于時嘉永二己酉閏四月 梅室書 |
|
| 明治23年(1890年)8月30日、正岡子規は石山寺に行き、芭蕉の句碑を見ている。 |
|
川にそうて石山寺に行く 此あたりの景色湖とはかはれども却てうつくしく思はる 寺は壯大にして奥ゆかし 堂はいくつともなく高低にたてならべ鐘つき堂、月見堂などのみやびたる源氏の間のむかしなつかしき皆有がたき思ひあり 庭に芭蕉の句をゑりて立てたり 曙はまたむらさきにほとゝきす 此寺のほとりに大なるくしき石いとおもしろく立ちならびたるは石山といふ名のおこりにやあらん |
紫式部像があった。

多宝塔

国宝である。
| 昭和8年(1933年)、斎藤茂吉は石山寺の多宝塔にに案内された。 |
|
多寶塔の鍵をあけつつ導きしわかき法師をわすれかねつも |
心経堂

石山寺から石山寺観光駐車場へ向かう途中の右手に芭蕉の句碑がある。
義仲寺へ。
2008年〜滋 賀〜に戻る