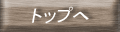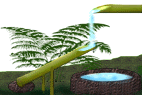
西本願寺〜世界文化遺産〜

|
天正19年(1591年)、豊臣秀吉により寺地の寄進を受け、大坂天満から現在の堀川六条に移転。 慶長7年(1602年)、徳川家康は寺地を寄進し、東本願寺が始まる。 |


|
天明元年(1781年)、田上菊舎は西本願寺の報恩講に参詣している。 |

|
文化8年(1811年)3月、田上菊舎は西本願寺の親鸞聖人五百五十回忌に参詣。 |

|
享和2年(1802年)3月22日、太田南畝は西本願寺、東本願寺を訪れている。 |
|
七条河原をわたりて、かの石川五右衛門が烹られし跡を見つゝ珠数屋町に出て、六条東本願寺にいたり、名に(おふ)門の彫物をみ、西本願寺の門をみれば、この比あらたに営み建て、三月廿六日供養ありとて、いまだかこひをとらず。されど東の大きなる門には、たちも及ぶべからず。 |

|
元治元年(1864年)6月5日「池田屋騒動」以降、新選組は隊士が増え、慶応元年(1865年)3月10日、屯所を壬生から西本願寺に移した。 境内に「新選組本陣」の看板を掲げ、北東にあった北集会所と太鼓楼を使用したそうだ。 |
|
昭和44年(1969年)3月12日、高浜年尾は清交吟社吟行で西本願寺飛雲閣へ。 |
|
三月十二日 清交吟社吟行 京都西本願寺飛雲閣 大寺のどの部屋もみな隙間風 睡蓮の古葉に添うて生ひそめし 水草生ふ水面を雨の叩くなり 冴返るひとしほ京の春の雨 |