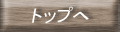『湖白庵集』(諸九尼)

有井浮風・諸九
『湖白庵集』(諸九尼)

| 子規聞はや雨の世話もなし | 諸九 |
||||||||||||||||||||||||||
| 名もあらたまる軒の若竹 | 文下 |
||||||||||||||||||||||||||
| 五献目は波のたつほと引うけて | 蝶夢 |
||||||||||||||||||||||||||
| また夜は深いなんの明ふそ | 吟風 |
||||||||||||||||||||||||||
| 洛 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 背競を裾てほめたる柳かな | 文下 |
||||||||||||||||||||||||||
| 隣から隣も遠し桃のはな | 只言 |
||||||||||||||||||||||||||
| また咲ぬ躑躅も見へて諫皷鳥 | 蝶夢 |
||||||||||||||||||||||||||
| 浪華 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 扇とはちかふた物よはつあらし | 南華 |
||||||||||||||||||||||||||
| 竹の子やもふ一つ身の胸あはす | 舊國 |
||||||||||||||||||||||||||
| 備後 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 三原 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 浦の月背向て居る家もあり | 梨陰 |
||||||||||||||||||||||||||
| 備中 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 倉敷 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 七草をきぬたはしめやあちの里 | 暮雨 |
||||||||||||||||||||||||||
| 安藝 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 廣嶋 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 鴫たつや我片膝もひとり立 | 風律 |
||||||||||||||||||||||||||
| 筑前 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 直方 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 恐ろしい我足音や虫の音 | 文沙 |
||||||||||||||||||||||||||
| 飯塚 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 牛の舌とゝけは逃る柳かな | 依兮 |
||||||||||||||||||||||||||
| 内野女 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 蝉啼や一頻つゝ蒸やうな | なみ |
||||||||||||||||||||||||||
| 筑後 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 善道寺 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 後の月夜は柳から更にけり | 而后 |
||||||||||||||||||||||||||
| 伊勢 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 山田 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 陰日南なしに働く柳かな | 麦浪 |
||||||||||||||||||||||||||
| 津 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 麦蒔や飯呼ふ聲を吹ちきり | 二日坊 |
||||||||||||||||||||||||||
| 駿河 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 吉原 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 聞知た寺の鐘さへ秋のくれ | 乙児 |
||||||||||||||||||||||||||
| 江都 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 椎の木の下にあかるき椿かな | 秋瓜 |
||||||||||||||||||||||||||
| 物かけてつい寐た顔や朧月 | 鳥酔 |
||||||||||||||||||||||||||
| 烏明 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 鶯やしつまりかへる奈良の町 | 蓼太 |
||||||||||||||||||||||||||
| 常陸 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 水戸 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 髪ゆふた子共からまつころもかへ | 三日坊 |
||||||||||||||||||||||||||
| 陸奥 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 仙臺 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 秋さひし蚊も相人には足らぬほと | 丈芝 |
||||||||||||||||||||||||||
| 津經 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 秋さひし蚊も相人には足らぬほと | 里圭 |
||||||||||||||||||||||||||
| 加賀 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 金沢 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 夜はついに明て只居る蛙かな | 麦水 |
||||||||||||||||||||||||||
| 薪にも足らて残るやかれ柳 | 半化坊 |
||||||||||||||||||||||||||
| 松任 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 初しくれ水にしむほと降にけり | 素園 |
||||||||||||||||||||||||||
| 近江 | |||||||||||||||||||||||||||
| 粟津 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 六条に汐も焼かとおほろ月 | 既白 |
||||||||||||||||||||||||||
| ことことと水もいぬるや秋のくれ | 可風 |
||||||||||||||||||||||||||
| あたゝめる硯も雪の朝かな | 文素 |
| 柳居 |
|
| 八合の月見はおかし升の市 |
|
| 火縄ひへ行松原の中 | 梅従 |
| 京の手も碪はおもふ響せて | 杜菱 |
| 額はしらに眠る馬引 | 浮風 |
| 市の升油は入れし後の月 | 杜菱 |
| 何買に言の葉屑を升の市 | 梅従 |
| 升買ふて松露拾はん十三夜 | 浮風 |
| 後の月杖を寶の市人数 | 風之 |