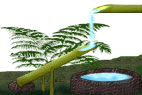下 町 ・ 文京区
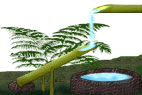
護国寺〜夏目漱石〜
東京メトロ有楽町線「護国寺駅」を出ると、護国寺(HP)がある。

護国寺は真言宗豊山派の寺院。山号は神齢山。
天和元年(1681年)、徳川綱吉の母桂昌院の発願により創建。
江戸三十三観音第13番札所である。
文化14年(1817年)8月17日、国学者高田与清は護国寺の観音に詣でている。
○おとはのごゝくじのくわんおん・ざふしがやのきしも神などにまうでゝ、しひなまち・長崎・かみいたばしなどいふ所をすぎゆく。
御府内八十八箇所の第87番札所でもある。
護国寺惣門

この惣門は護国寺の方丈への軸線上にあり、寺院の門と共に住宅のという性格をあわせもっている。
形式は、社寺系のものではなく、江戸時代武家屋敷の5万石以上の大名クラスの格式に相当する形式と偉容をもっている。当寺が幕府の厚い庇護のもとで高い格式を保持した歴史を反映している。
大名屋敷表門で現存するものは、いずれも江戸時代後期のものであるのに対して、この門は中期元禄年間のもので、特に貴重な文化財である。
−郷土愛をはぐくむ文化財−
文京区教育委員会
不老門の下に「からすの赤ちゃん」の碑があった。

からすの赤ちゃん
海沼実 作詞・作曲
からすの赤ちゃん なぜなくの
|
こけこっこの おばさんに
|
あかいおぼうし ほしいよ
|
あかいお靴も ほしいよと<
|
かあかあ なくのね
|
不老門

昭和13年(1938年)4月、建立。
不老門を入ると、観音堂(本堂)の前で「薬師如来の潅頂」が行われていた。

観音堂(本堂)

元禄10年(1697年)、5代将軍徳川綱吉の命により建てられた。
本尊は如意輪観世音菩薩。
榎本其角は護国寺に遊んでいる。
元禄13年(1700年)5月16日、京都嵯峨清涼寺の釈迦如来像が護国寺に出開帳。
護国寺にあそぶ時
馬にてむかへられて
白雲や花に成行(なりゆく)顔は嵯峨
年々の春秋武江の寺社に廻
り給ふなる霊仏霊神君を
守りのあとしめて興廃の御
威現あらたなる中にも当
時の開帳はさかの御てらと
札をうたれて官駕鄙馬のさ
かひに暑をなやます霍
乱虫気のさはりもなく蟻の
ことくにまふてつたふ行程の
遠近を辻番にたつねて
まはらは廻れ振舞水の下向道
文化3年(1806年)4月27日、小林一茶は護国寺に参詣。
廿七日 曇 護国寺参 鳴停止(ちやうじ) 開帳ナシ
『文化句帖』(文化3年4月)
文化7年(1810年)8月1日から護国寺で信州座光寺村元善光寺阿弥陀如来開帳。元善光寺は長野県飯田市座光寺にある如来寺のこと。本田善光が善光寺の本尊を最初に安置した所という。善光寺に遷座された本尊の代わりに木彫りの本尊が残されているそうだ。
同年10月8日、一茶は松井と元善光寺開帳に参詣。
八 晴 松井ト元善光寺開帳参
『七番日記』(文化7年10月)
薬師堂

元禄4年(1691年)、建立。
文京区指定文化財
仁王門

夏目漱石の『夢十夜』に出てくる「山門」である。
運慶が護国寺の山門で仁王を刻んでいると云う評判だから、散歩ながら行って見ると、自分より先にもう大勢集まって、しきりに下馬評をやっていた。
『夢十夜』「第六夜」
若山牧水も護国寺で歌を詠んでいる。
音羽護国寺
むら立ちの異木に行かず山雀は松の梢にひもすがら啼く
この寺の森に寄る鳥とりわけて山雀のなくはあはれなりけり
第8歌集『砂丘』
昭和18年(1943年)1月7日、高浜虚子は護国寺を訪れている。
道のべの延命地蔵古稀の春
一月七日 小石川、護国寺。
『六百句』
下 町 ・ 文京区に戻る