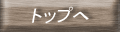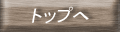芭蕉の句碑
『奥の細道』〜東 北〜

笈も太刀もさつきに飾れ紙のぼり
東北自動車道福島飯坂ICから国道13号に入り、県道3号を過ぎて右折する。

芭蕉ゆかりの地、医王寺がある。
医王寺

医王寺は丸山の大鳥城主であった佐藤基治一族の菩提寺。
藤原秀衡のもとにあった源義経(1159〜89)が平家討伐に向かう時、基治はその子継信・忠信を遣わした。兄継信は屋島の合戦において義経の盾となって矢を受け亡くなり、弟忠信は頼朝に追われた義経の身代わりとなって討ち死にする。
その後、義経は弁慶らと共に平泉に落ち行く途中で基治を訪れ、継信・忠信の遺髪を埋葬して法要を営んだ。
医王寺には佐藤基治、その子継信・忠信の墓がある。
何故か、お墓に参る気はしなかった。
元禄2年(1689年)5月2日(新暦6月18日)、芭蕉は佐藤基治の旧跡を訪れている。
次いで芭蕉は医王寺を訪れた。
「五月朔日」とあるが、実際は5月2日だったらしい。
医王寺に芭蕉の句碑がある。

笈も太刀もさつきに飾れ紙のぼり
かなり古びていて文字もよく見えない。
脇の新しい碑に説明がある。

寛政11年(1799年)、大江丸は句碑の文字をしたためる。
寛政12年(1800年)8月、大江丸は折からの雨で医王寺に行けなかった。
又やな川の渋川氏ばせを翁の笈も太刀もといへるほ句を碑にし、さバやのゝ医王寺とやらんへ建らるゝにつき、其石面の文字を我にのぞみ来り。去年の冬したゝめ下せしが、石面にきざませこのたび寺の庭に建られむとの結構にて、幸の下向をまち申さる。我もめづらしき事、たちこへ(え)供養のはいかいをもすべきあらまし、松しま仙台の古因もたづね申度こゝろ専なれど、折ふしの雨天に日頃は二日路斗りのみちも七八日もかゝるなどとの人のいふに恐れ、ひまどりてハ、かうづけの国にての第一の用事にを(お)くれなむ、はるばる下りし大旨をとりはづしてハと、家のわざにおもひかへし、夫々の断の文ども遣したり。
寛政12年(1800年)10月、芭蕉没後106年目に建立されたものだと書かれている。
昭和40年(1965年)、山口誓子は医王寺に芭蕉の句碑を訪ねている。
寺に入ると、左手に本堂、突きあたりに田舎の旧家のような寺の建物が見える。本堂の左手前に芭蕉の句碑がある。自然石。白っぽい苔が附いている。
笈も太刀もさつきにかざれ紙のぼり
その寺に伝わる弁慶の笈、義経の太刀も、端午の節句に飾った紙幟と一緒に飾れ、と云うのだ。
句碑の建立は寛政十二年。
『句碑をたずねて』(奥の細道)
医王寺の宝物館に芭蕉坐像や義経の太刀、弁慶の笈があるそうだ。
旅の途中なので、見なかった。
芭蕉は飯坂温泉に向かい、そこに泊まった。
私は穴原温泉へ。
『奥の細道』〜東 北〜に戻る