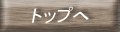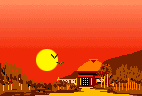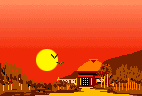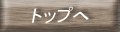東海道
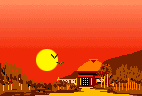
『更級日記』(菅原孝標女)
寛元4年(1020年)、菅原孝標女は父の任果てて上京。
その夜は、くろとの濱といふ所に泊まる。片つ方はひろ山なる所の、砂子はるばると白きに、松原茂りて、月いみじうあかきに、風の音もいみじう心細し。人々をかしがりて歌よみなどするに、
まどろまじこよひならではいつか見むくろどの濱の秋の夜の月
まだ暁より足柄を越ゆ。まいて山の中の恐ろしげなること言はむかたなし。雲は足の下に踏まる。山の半らばかりの、木の下のわづかなるに、葵のただ三筋ばかりあるを、世離れてかかる山中にしも生ひけむよと、人々あはれがる。水はその山に三所(みところ)ぞ流れたる。
「足柄の関伝承地」

富士の山はこの国なり。わが生ひいでし国にては西面(おもて)に見えし山なり。その山のさま、いと世に見えぬさまなり。さまことなる山の姿の、紺青を塗りたるやうなるに、雪の消ゆる世もなくつもりたれば、色濃き衣(きぬ)に、白きあこめ着たらむやうに見えて、山のいただきのすこしたいらぎたるより、けぶりは立ちのぼる。夕暮れは火の燃え立つも見ゆ。
清見が関は、片つ方は海なるに、関屋どもあまたありて、海までくぎぬきしたり。けぶりあふにやあらむ、清見が関の浪も高くなりぬべし。おもしろきことかぎりなし。
大井河といふわたりあり。水の世の常ならず、すり粉などを、濃くて流したらむやうに、白き水、早く流れたり。
ぬまじりといふ所もすがすがと過ぎて、いみじくわづらひ出でて、遠江にかゝる。さやの中山など越えけむほどもおぼえず。
そのわたりして浜名の橋に着いたり。浜名の橋、くだりし時は黒木をわたしたりし、このたびは、跡だに見えねば、舟にて渡る。入江にわたりし橋なり。外(と)の海はいといみじくあしく波高くて、入江のいたづらなる洲どもにことものもなく、松原のしげれる中より、波の寄せかへるも、いろいろの玉のやうに見え、まことに松の末より波は越ゆるやうに見えて、いみじくおもしろし。
それよりかみは、ゐのはなといふ坂の、えもいはずわびしきをのぼりぬれば、三河の国の高師の浜といふ。八橋は名のみにして、橋の方もなく、なにの見所もなし。ニむらの山の中にとまりたる夜、大きなる柿の木のしたに庵を作りたれば、夜ひとよ、庵の上に柿の落ちかゝりたるを、人々拾ひなどす。
二村山

尾張の国、鳴海の浦を過ぐるに、夕汐たゞ満ちに満ちて、こよひ宿らむも中間に、汐満ち来なば、こゝをも過ぎじと、あるかぎり走りまどひ過ぎぬ。
雪降り荒れまどふに、物の興もなくて、不破の関、あつみの山など越えて、近江の国、おきながといふ人の家に宿りて、四五日あり。
東海道に戻る