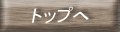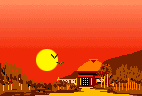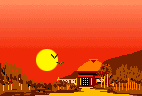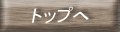街 道
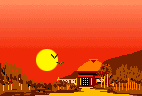
足柄古道〜足柄の関〜
小山町の県道78合御殿場大井線を行くと、足柄峠がある。

足柄峠

標高759m
倭建命(日本武尊)
『古事記』(和銅5年・712年完成)によれば、景行天皇の皇子 小碓命(おうすのみこと)は、九州の熊襲建を征服した後、倭建命と名を改めた。
九州から大和へ帰った命は、天皇より東征の命令を受け、上総(千葉県)へと出発した。
相模(神奈川県)では野火の難を草薙の剣で無事切りぬけ、いよいよ相模半島(三浦半島)から海路、目的地へ向った。船が大海原にさしかかった時、海の神の怒りにふれたか、平穏な海は一瞬にして怒濤さかまく荒海に変った。この時連れの弟橘媛は、荒狂う波間に身を投じ、神をなだめ海を静めた。上総の岸へ無事着いた命は、任務を果したその帰路、足柄峠の頂に立ち、再び見ることはないであろう東の海をながめ、あの橘媛を思い「吾妻はや」(あゝわが妻よ)と嘆き悲しんだのだった。
寛元4年(1020年)、菅原孝標女は父の任果てて上京。足柄峠を越える。
まだ暁より足柄を越ゆ。まいて山の中の恐ろしげなること言はむかたなし。雲は足の下に踏まる。山の半らばかりの、木の下のわづかなるに、葵のただ三筋ばかりあるを、世離れてかかる山中にしも生ひけむよと、人々あはれがる。水はその山に三所(みところ)ぞ流れたる。
足柄峠に「足柄の関伝承地」があった。

古代の足柄の関
足柄の関は昌泰2年(899年)、足柄坂に出没する強盗団、シュウ馬(※「シュウ」は、イ+就)の党を取り締まるために設けられた。関の通行には相模国の国司の発行する過所(通行手形)が必要だった。関の設置された場所や規模、関の停廃の時期などは分かっていない。
『源平盛衰記』に治承4年(1180年)のこととして、土屋宗遠が甲斐に越える時、「見レハ峠ニ仮屋打テ、(中略)夜半ノ事ナレハ、関守睡テ驚カス」と見える。また、鎌倉時代の歌人 飛鳥井雅経が、「とまるべきせきやはうちもあらはにて嵐ははげしあしがらの山」(『明日香井和歌集』)と詠んでいることから、源平の動乱の時代に、足柄峠に臨時の関が設けられ、鎌倉時代初期にはその残骸が残っていたことがわかる。
峠付近の路傍から採取された4,000年前の縄文土器片が語るように、この峠道の歴史は古く、鎌倉時代に箱根道が開かれるまでは官道・公道として利用され、東海道最大の難所として有名であった。また、歌枕として関・峠とともに、多くの歌に詠まれている。 この関は、昭和60年、黒沢明監督の映画『乱』の撮影で使われた城門のセットを足柄の関伝承地へ移築したものである。
(小山町観光協会)
貞応2年(1223年)4月15日、京都に住む隠者は鎌倉に下る途中、足柄峠を越える。
今日ハ足柄山ヲ越テ関下宿(せきのもとしゆく)ニ泊ルべキニ、日路(じつろ)ニ烏群リ飛テ、林ノ頂ニ鷺ネグラヲアラソヘバ、山ノ此方ニ竹ノ下ト云処ニトマル。四方ハ高キ山ニテ、一河谷ニ流、嵐落テ枕ヲ扣ク、問ヘバ是松ノ音。霜サエテ袖ニアリ、払ヘバ只月ノ光、寢覚ノ思ニタヘズ。独リ起居テ残ノ夜ヲ明ス。
見シ人ニ逢夜ノ夢ノナゴリ哉カゲロフ月ニ松風ノ声
深(ふく)ル夜ノ嵐ノ枕フシワビヌ夢モ宮コニ遠ザカリキテ
文明18年(1486年)、道興准后は足柄峠を越える。
あしがら山をこゆとてよめる、
足柄のやへ山越えて眺むれは心とめよとせきやもるらむ
文亀元年(1501年)、宗長は足柄山を越え、越後の国府に師の宗祗を訪ねた。
文亀はじめの年六月の末、駿河の国より一歩をすゝめ、足柄山をこえ、富士のねをよそに見て、伊豆の海、おきの小島による浪、こゆるぎの磯をつたひ、鎌倉を一見せしに、
寛政3年(1791年)6月26日、鶴田卓池は足柄の関を越える。
足柄の関を越えて、竹の下みちとよめる竹の下に草鞋をやすむ。
富士の雲瓜むくひまに替けり
廿六日 未ノ刻白雨アリ コウ山へ弐里半 関元へ
二里 道了権現へ一里余 大雄山最乗寺ト云
禅宗也 道了権現ヨリ矢倉沢ノ関迄壱里半余
是ヨリ足柄山也
さらに今都も恋し足からの関の八重山猶へたてつゝ
秋まてハ富士の高根に見し雪を分てこへぬる足柄の関
ふかき夜に関の戸出て足からの山もとくらき竹の下みち