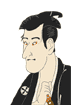
絵 島〜西行の歌碑〜




|
砂岩の小島で岩肌の縞模様が美しい。日本発祥の地、国生み神話の「おのころ島」の異名をもち、多くの歌人がその美しさを歌に詠んだ。『平家物語』の「月見」の巻に「福原の新都に移った人々が、海峡を渡り、絵島の月を愛でながら歌会を催した」と記述されている町の代表的な景勝地である。 |

|
寛永10年(1633年)10月11日、西山宗因は熊本から上京する途中の舟で岩屋の城を見ている。 |
|
右はあはぢしま、岩屋の城もみえたり。むかし関所のあとにて、かた計なるを見て、 君が代の治る時にさゞれ石の岩屋のしろも苔のむすらん
「肥後道記」 |
|
貞亨2年(1685年)11月10日、大淀三千風は明石から淡路島の岩屋に渡る。15日、岩屋から明石の月照寺に着く。 |
|
是よりむかひに立る淡路島におもむく。小船うごくとせしが。十日の朝風に岩屋村にあがる。かくて神のむかしの名所名所をながめて。 本の岩屋にたちかへれば。國守の舸(はやふね)に幸ありて。明石の月照寺につきにける。漸寒(やゝさむ)になれば旅衣も興つきて。霜月十六日明石を立つ。此道すがらは前巻に記しぬ。大坂に一宿して。古郷伊勢に越年し。明春寅に都にのぼり。東山道にこゝろざしぬ。
『日本行脚文集』(巻之五) |
|
明治44年(1911年)1月17日、河東碧梧桐は絵島を訪れ、その景色を酷評している。 |
|
絵島といえば和歌で名高い名所であるが、正直に言えばどこの海岸にも有勝な平凡な景色だ。かかる平凡な景色が名高くなったというのは、平安朝以後の淫靡趣味に堕落した一般の趣味性にも因ることであろうが、要するに歌人は座(いな)がら名所を知る、などという屁理屈を土台にして、直接経験を忘れた空想趣味の余累であると見るべきである。松帆の浦の夕凪になどあるその浦も遠くはないとの事であったが、絵島に懲りたのでついに見残した。 |
|
昭和8年(1933年)11月23日、星野立子は明石から船で岩屋へ。 |
|
十一月二十三日。神戸の若林さん方のおすゝめで淡路
島へ行くことに急にきまり、朝七時五十六分芦屋発の汽
車で明石へ向つた。明石から船で岩屋迄。冬晴のよい日
であつた。 稲こきの男見えさし淡路島 船長は毛糸編みをり舟静か 冬鴉とびては下りる渚かな |
|
昭和39年(1964年)12月20日、高野素十は絵島を訪れている。 |
|
二十日 淡路絵島舘 ゆづり葉会 海峡を流るる潮も十二月
昭和40年3月 芹 |
|
昭和44年(1969年)5月2日、高野素十は明石から岩屋を経て鳴門へ。 |
|
五月二日、三日 京都より明石−淡路岩屋−福良を経て明石海峡を 渡り鳴門に至る。鳴門三日会招待による 赤潮のきれぎれにある赤さかな 一海峡一潮流の明易き
昭和44年7月 芹 |