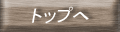大浦天主堂〜水原秋桜子〜

|
元治元年(1864年)、大浦天主堂竣工。正式名は日本二十六聖殉教者聖堂。殉教地である長崎市西坂に向けて建てられている。 |
|
大正11年(1922年)3月20日、高浜虚子は天主堂を見る。 |
|
彦影君に導かれて直ぐ上の天主堂を見る。此天主堂は慶應に出來たものであつて、丁度此日儀式があつて信者の男や女達が來會して居つた。我等の行つた時は晝休みであつたが、なほ女の信者が二三人柱の下にうづくまつて居るのがあつた。額には豐臣氏時代にスピノザ以下三十餘人の日本の信者が磔になつて居る圖が油繪になつて懸つて居た。これは西洋人の描いた油繪であるといふ事であつた。此地方はキリシタンバテレンの信仰の力と、それを壓迫する政府との爭鬪の痕が到るところに見られる。 |
|
昭和3年(1928年)10月、山口誓子は大浦天主堂を訪れた。 |
|
秋の暮使徒虐殺の圖にまみゆ 聖堂に嚏(はな)ひしひとや出で來たる
『凍港』 |
|
昭和7年(1932年)2月4日、種田山頭火は大浦天主堂で句を詠んでいる。 |
|
二月四日 曇、雨、長崎見物、今夜も十返花居で。…… ・冬雨の石階をのぼるサンタマリヤ(大浦天主堂) |
|
昭和8年(1933年)1月23日、文部省により国宝に指定。 昭和13年(1938年)8月、橋本多佳子は長崎へ旅行。大浦天主堂を訪れた。 |
|
雷をきき聖なる燭のもとにわれ 雷雨去り聖歌しづかなりつづく 虹ひくく天主の階を降りんとする
『海燕』 |
|
昭和20年(1945年)8月9日、原爆投下で甚大な被害を受けた。 昭和27年(1952年)5月23日、水原秋桜子は大浦天主堂を訪れた。 |
|
大浦天主堂は修理完く成り、石階上に日本聖母像を仰ぐ。 階下に僧院あり、薔薇、罌粟など咲けるが見ゆ 三句 午後の日の暈(かさ)に僧院は罌粟咲けり> 僧院は廊欄古りぬ薔薇の上 薔薇喰ふ虫聖母は見たまふ高きより
『残鐘』 |
|
昭和27年(1952年)6月30日、修復工事は完了。 昭和28年(1953年)3月31日、文化財保護委員会によって国宝に再指定。 |

|
平成30年(2018年)、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」として世界遺産に登録。 |