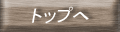原城跡〜天草四郎像〜
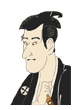

|
原城は慶長4〜9年(1599−1604)頃にキリシタン大名の有馬晴信(1567−1612)によって築かれた城郭とされています。宣教師の記録によると、有馬氏本城の日野江城が手狭で戦闘に不向きであったため、新たに巨大で堅固な原城が築城されました。 城は有明海に突き出す丘全体を縄張りとし、本丸はじめ二ノ丸、三之丸、鳩山出丸、天草丸などの曲輪があります。本丸は石垣造りで、直線的な稜線の曲輪となっています。一方、 他は自然地形を活かした土造りの曲輪が並立的に配置されるなど、中世城郭の名残りがある構造となっています。元和2年(1616年)、大和五條より入封した松倉重政が居城を島原へ移したため、原城と日野江城は廃城となりました。 寛永14〜15年(1637−1638)の島原・天草一揆では、度重なる飢饉や領主の弾圧に堪えかね、2万を超える農民が蜂起し、最終的に廃城となっていた原城に籠城しました。一揆勢のほとんどがキリシタンでした。一揆は約4ヶ月の長期戦となりましたが、兵糧攻めの末、寛永15年(1638年)2月末の幕府軍の総攻撃により鎮圧されました。一揆以後、ポルトガル船の来航禁止、宗門改帳の作成が実施されるなど、海禁(鎖国)政策やキリシタン禁制および領民の統制が強化されていきました。原城を主戦場としたこの戦いは、幕府の支配政策にも影響を与える大きな出来事でした。
南島原市 |

|
島原一揆の古跡として聞えておる原城の跡を枯腸子の案内で見巡った。今はただ一面穂麦の中に埋っておって、僅に城趾の石垣のみを存するのみだ。佐分利某の墓、板倉内膳正戦死の碑など見ておる中に、風雨で衣袂(いべい)もボトボトになった。切支丹の擁護の乱の裏面には、徳川政府顛覆の陰謀も含まれていたということと、多数の教徒が、城の崖から海中に投じて身を殺したという悲惨な話とに対照して、昔有馬氏がここに城を築いて追った頃は、海中に石垣を築き出して結構壮美を極め、土地の者は日暮しの城と称えて、その美観に憧憬しておったという話を、如何にも美美しい日永な感じのするように思うた。 |

|
原城本丸へと繋がる最後の門です。入口の空間へ入ると建物の基礎となる礎石が並んでおり、櫓門が建てられていたと考えられます。櫓門を抜けるとその先に階段が設けられており、城内へ続いています。他の門跡と同様に一揆後に破壊され、礎石の一部がなくなっており、階段の踏石はわづかしか残っていません。
南島原市教育委員会 |
|
昭和37年(1962年)、舟越保武は原城跡を訪れる。 昭和46年(1971年)、「原の城」制作。 |

|
ここは原城の本丸跡です。本丸とは城郭の中枢となる最も重要な場所です。本丸の曲輪は約8千㎡と広大であり、さらに城の西北側には本丸の守りを固めるため、枡形が連続する複雑で巨大な出入口(虎口)の空間が備えられていました。出入口の空間には本丸正門や本丸門など礎石建物を伴う門があります。また本丸の西側には櫓台があり、東側には搦手である池尻口門などがあります。 原城本丸は島原・天草一揆の際、総大将の天草四郎など指導者層が立て籠もり、最後まで籠城戦が行われた場所でもあります。一揆後は再び籠城の拠点とならないよう、幕府軍によって建物や石垣が徹底的に破壊され、地中に埋め尽くされていました。本丸の調査では戦いの凄惨さや一揆勢の信仰心を物語るよう、多くの傷ついた人骨や、十字架・メダイ・ロザリオ珠(だま)などの信心具も出土しました。
南島原市 |


|
佐分利九之丞(1578−1638)は、鳥取藩池田家で島原・天草一揆の時に使者として息子の成次、第五子成興らと共に有馬の地に来た人物です。寛永15年(1638年)2月27日の幕府軍の総攻撃の時に討たれ、死の直前、そばにあった石に自分の名と日付を刻んだと伝えられています。 佐賀鍋島家の記録に「池田家の使者佐分利九之丞同廿七日本丸の城戸にて討死す」とあり、この付近で亡くなったと考えられます。「本丸之内に佐分利九之丞と書く付ある石塔ぉれあり」と記した延宝2年(1674年)の古絵図も残っておりを、その頃より石碑が本丸にあったことがわかります。
南島原市教育委員会 |

|
天草四郎時貞は小西行長の家臣、益田甚兵衛好次の子で、本名は益田四郎時貞といい、洗礼名はジェロニモとかフランシスコなどといわれています。比較的恵まれた幼少時代を送り、教養も高かったといわれ、また長崎へ行って勉強したとありますが、詳細は不明です。 島原の乱に際し、若干15才という若さで一揆軍の総大将として幕府軍と対立しました。一揆軍は88日間この原城に籠城したが、圧倒的な幕府軍の総攻撃により終結しました。 四郎はこの本丸で首を切られ、長崎でもさらし首にされました。 この墓碑は、西有馬町にある民家の石垣の中にあったものをこの場所に移したものです。
南島原市教育委員会 |
|
昭和40年(1965年)11月16日、水原秋桜子は九州の旅に出る。 |
|
原城址 三句 蓼枯れぬ天使の翼折れし如 はたはたの残れど飛べる音もなし 甘藷掘りしあとはむかしの土塁かも 天草四郎の墓 対の花瓶一つ野菊を挿せるのみ
『殉教』
|

|
原城本丸に入る3ヶ所の門のひとつで、発掘調査で門と思われる礎石やその両側の石垣、階段などが発見されています。他の門跡と同様、島原・天草一揆の後に幕府軍に破壊され、埋め尽くされていました。破壊の激しさを示すよう階段の踏石には抜け落ちが目立ち、石垣は最大でも1.7m程の高さしか残っていません。特に石垣の隅角は、両側とも根石1石のみが残る状況です。
南島原市教育委員会 |

|
原城跡では本丸にのみ石垣が確認され、こかの曲輪は石垣を伴わない土造りとなっています。原城は17世紀初頭に築かれた近世の城郭ですが、中世城郭の名残りがみられる点も大きな特徴です。 原城本丸の石垣は緩やかの勾配で、直線的に積み上げられています。石垣の目地を横方向に通そうとする意図がみられますが、石材が企画的ではないため、必ずしも徹底はしていません。石垣に積まれる大きな石材(築石)には、粗割(あらわり)石や自然石が用いられ、割り面(つら)や、自然石の比較的平坦な面が石垣の表面となるよう積まれています。こうした積み方は、近世初頭頃の城郭石垣の特徴をよく示しています。
南島原市 |

|
前方にある谷状の地形は、本丸の守りを固めるために造られた空堀の跡です。 築城より400年以上の歳月を経過し、自然崩落などにより大きく広がっていますが、一揆の様子を描いた絵図資料には、縦5間(10m弱)、横20間(39m余り)と記したものがみられます。また空堀内部に小屋が立ち並ぶ様子を描いた絵図資料もあり、空堀の底にも一揆勢が所狭しに駐留したと考えられます。
南島原市 |
|
昭和45年(1970年)10月8日、高浜年尾は原城址へ。 |
|
原城址へ廻る 古城址の水も豊かに豊の秋 からいもといふ島原の甘藷畑 古老来て城址の話返り花 |
|
平成30年(2018年)、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」がユネスコ世界文化遺産に登録された。 |