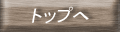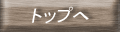芭蕉の句碑
『奥の細道』 〜東北〜

あやめ草足に結ん草鞋の緒
仙台市若林区木ノ下に陸奥国分寺(HP)がある。

天平期に聖武天皇の詔により全国に建立された金光明四天王護國之寺。
文治5年(1189年)8月、源頼朝の藤原氏追討の兵火により陸奥国分寺は悉く焼失してしまったという。
陸奥国分寺仁王門

宮城県指定有形文化財である。
薬師堂

慶長12年(1607年)、伊達政宗造営。
本瓦葺の仙台最古の建造物で、国指定重要文化財。
元禄2年(1689年)5月7日、芭蕉は薬師堂を訪れている。
元禄9年(1696年)、天野桃隣は『奥の細道』の跡をたどり、薬師堂に触れている。
山榴岡・釈迦堂・天神宮・木の下薬師堂。宮城野、玉田横野 何も城下ヨリ一里ニ近し。
現在の陸奥国分寺は真言宗智山派の寺である。
準胝(じゅんてい)観音堂

文治5年(1189年)焼失したが、享保4年(1719年)5月、建立されたという。現在の準胝観音堂は、延享2年(1745年)3月に再建したもの。
準胝観音堂の右手に芭蕉の句碑があった。

あやめ草足に結ん草鞋の緒
芭蕉句碑(仙台市指定有形文化財)
「あやめ草足に結ん草鞋の緒」とある。芭蕉は奥の細道の旅の途中、元禄2年(1689年)5月5日から7日までの3日間仙台に滞在したが、その時芭蕉を案内し、翌8日離仙の朝「紺の染緒つけたる草鞋2足」と餞別の品々を贈り、芭蕉をして「風流のしれ者」と感嘆させた俳人北野加之(画工加右衛門)への感謝の気持ちを詠じた句である。
この句碑は、天明2年(1782年)、駿河の俳人山南官鼠が来仙した折に建立したもので、裏面には官鼠自身の句「暮れかねて鴉啼くなり冬木立」と彫られている。
『泊船集』には「紐にむすはん」とある。
『諸国翁墳記』に「艸鞋塚 奥州仙臺國分寺ニ在 嵐雪四世六花菴建」とある。
加之は大淀三千風の高弟。
昭和3年(1928年)7月23日、荻原井泉水は陸奥国分寺を訪れて芭蕉の句碑を見ている。
芭蕉が詣でた薬師堂は木の下薬師と称してここにある。それは私も参拝した。この堂は聖武天皇の勅願国分寺の高堂十八伽藍のうちの一つで、慶長十年伊達政宗の再興にかかるものだという。
あやめ草足に結ん草鞋の緒 芭蕉翁
天明壬寅歳小春 行脚官鼠建之
この碑は準胝堂の右手にあった。
『随筆芭蕉』(仙台見物)
東性居士三千風翁之塚

大淀三千風供養碑
大淀三千風は、寛文9年(1699年)〜天和3年(1686年)までと、貞享3年(1686年)〜同4年(1687年)の計15年間仙台に滞在して、仙台の俳壇を開拓した伊勢国(三重県)の俳人で、偉大な俳諧指導者でもあった。この句碑は享保7年(1722年)、門弟の一人である万水堂朱角が師の供養のため自作の句を刻し建立したもので「名の風や水想観の花かほる」とあり、仙台の俳句史上貴重なものである。
望月宋屋の句碑もあった。

極楽や人のねがひの花の影
右が宋屋の句碑。
「京都 富鈴房」とある。富鈴は宋屋の別号。
宋屋は京都の俳人で、延享2年(1745年)数日仙台に滞在した時に建立された。
宋屋の自筆であるようだ。
奥仙臺國分寺木下藥師如來の堂前
|
に石碑を建て、不斷塚と号す。其
|
壷中へ、曇るまじ木の下陰に月不
|
斷 石面に自ら筆せし句
|
|
極樂や人の願ひの花のかげ
|
明和6年(1769年)4月23日、蝶羅は嘉定庵の社中に木の下薬師へ案内された。
翌日嘉定庵の社中にいざなハれ
|
木の下薬師宮城野を
|
|
堂庭も木の下闇の古びかな
| 蝶羅
|
天明6年(1786年)8月18日、菅江真澄は陸奥国分寺を訪れている。
野間が前、梅塚といふ処を、細道をあゆみ、木の下にいたる。薬師ぶちの御堂あり。天平九年に建たるとかや。いにしへは御堂あまたと聞へしが今わづかに白山社薬師堂ばかり見へたり。
『奥の細道』 〜東北〜に戻る